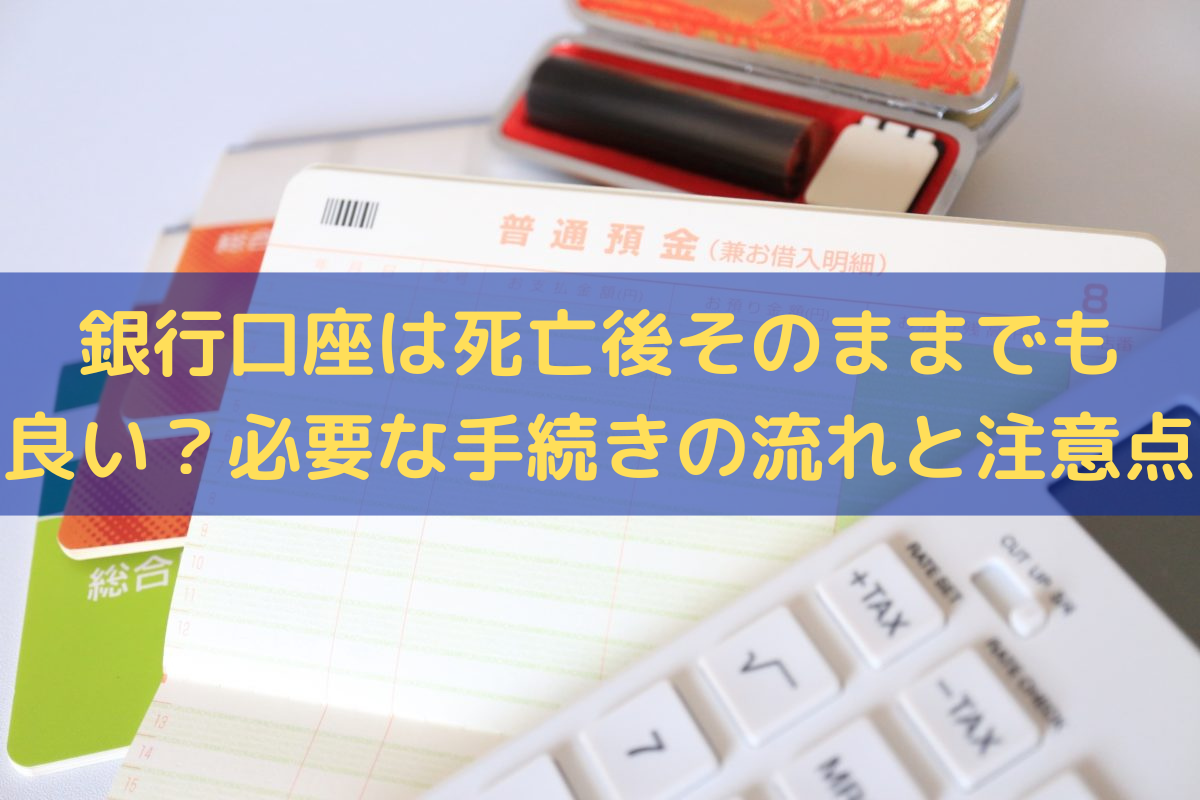家族が死亡すると、さまざまな手続きの必要性が生じます。中には、何から手を付けてよいのか分からない方や、慣れない手続きを面倒に感じてそのまま放置しておきたいと考えてしまう人もいることでしょう。
では、故人名義の銀行口座について、死亡後すぐにしなければならない手続きはあるのでしょうか?また、故人の銀行口座を死亡後もそのままにした場合、何か不都合は生じるのでしょうか?
今回は、死亡後に行う銀行口座の手続きについてくわしく解説します。
目次
銀行口座の名義人が死亡した際に必要な手続きの流れ

まずは、銀行口座の名義人が死亡した際の手続きの流れを、順を追って解説していきましょう。
提出する申請書類の書式や記入事項などは銀行によって異なることがあり、同じ銀行でも地域や支店によって取り扱いが違うこともあります。
一般的には次の流れで手続きを進めますが、実際の手続き方法は故人名義の口座がある銀行に問い合わせるようにしてください。
- 銀行に連絡する
- 必要書類を準備する
- 必要書類を提出する
- 預金の払い戻しを受ける
銀行に連絡する
亡くなった方の部屋で遺品整理を行い、銀行のキャッシュカードや通帳が見つかれば、どこの銀行に口座を開設していたのかが分かります。
故人が口座を持っている銀行を確認できたら、手続きをするためにまずはそれぞれの銀行に連絡を取りましょう。
連絡方法ですが、通帳やキャッシュカードに金融機関の電話番号が記載されている場合や、銀行ホームページに相続手続きをするときの連絡先が記載されている場合があります。
自宅から近い銀行なら窓口に足を運べば、次の手続きの説明も受けやすいでしょう。
なお、口座名義人の死亡を銀行が知ると口座は凍結されるので、入出金や振込、引落などの取引はそれ以降一切できません。
通帳の履歴などを確認して、公共料金の引落や家賃の振込などがされている場合には、引落元や振込元に連絡して公共サービスの解約などの手続きを行いましょう。
ちなみに口座名義人の死亡を銀行が知って口座が凍結されるのは、主に相続手続きをするために遺族が連絡したときです。
企業経営者などの場合は、取引のあった営業担当が新聞の死亡欄でたまたま見て知るなどということもありますが、一般的な個人の死亡であれば、銀行は家族などからの連絡があって初めて知ることになります。
必要書類を準備する
手続きで必要な書類は、遺言書の有無など相続が起きたときの状況によって異なります。
手続き書類は金融機関によって違うことがあるので個別確認が必要ですが、一般的には以下の書類が必要です。
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(遺言書が公証役場や法務局で保管されていた場合は不要)
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
- その預金を相続する人(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
また、銀行によっては独自の手続き書類を用意していることもあるので、その場合は金融機関指定の書類への記入・提出も必要です。
なお、2017年から法務局による法定相続情報証明制度が開始され、銀行によっては法務局発行の法定相続情報一覧図を提出することで煩雑な戸籍の提出が不要の場合があります。
必要書類を提出する
ステップ②で準備した書類を、故人名義の口座がある支店に提出します。
取引支店が遠方の場合は同銀行の近くの支店を通じての提出でも大丈夫なことも多いですし、書留など到着が確認できる方法での提出も可能です。
預金の払い戻しを受ける
書類の不足がなく手続きが進めば、2週間ほどで預金の払い戻しがされるのが通常です。
ただ、場合によっては1ヶ月ほどの時間がかかることもあります。
また、貸金庫を利用していて、開けて中に入っているものを確認するために直接取り扱い支店に行かなければならない場合のように、郵送ではできない手続きが発生することがあります。
銀行口座の解約手続きの代行を依頼する場合

銀行口座の名義人が死亡して手続きをしようと思っても、自分で手続きをする時間が取れない人もいるはずです。
そもそも銀行は平日しか開いておらず、平日の日中は仕事で忙しくて行けないという人も少なくありません。
その場合には、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に、銀行口座の手続きを依頼すると良いでしょう。
費用はかかりますが、自分で書類を集めたり銀行に提出したりする手間がかからずに済みます。
また、預金口座の解約手続きのサポートを行っている企業もあるので、手続きの代行業者に依頼するのもおすすめです。
銀行口座をそのままにしておいても良い?

ここまで手続きの流れを読み進めてきて、銀行口座の名義人が死亡したときの手続きは「自分でやるのも代行を頼むのも面倒だな」という感想をお持ちになったというのが正直なところでしょう。
実際、預金が少額だったり取引がほとんどなかったりする口座や、遺族にその存在が伝わらずに忘れられてしまった口座などは、届け出がされずそのまま放置されているケースが多いです。
口座名義人の死亡を銀行に届け出なかったとしても罰則を受けるわけではないため、「しばらくはそのままにしておいても良いのでは?」と考えられがちです。
ただ、例えば手続きが終わる前に相続人が亡くなって次の相続が開始すると、関係者の数が増えてしまい、手続きが複雑になって余計な手間がかかる場合があります。
また、そもそも手続きをしなければ預金を相続できないので、残された遺族の方の生活費などとして使うこともできません。
例えば、放置している間に振り込め詐欺の振込先などの犯罪に利用されてしまう可能性もあります。
そこまでの悪用はないにしても、親族間での相続トラブルの原因になることもあるので、なるべく早いうちに銀行へ連絡しておいたほうが良いでしょう。
銀行口座をそのままにしておいた方が良いケース
死亡した家族の銀行口座の手続きをせず、そのままにしておいた方が良いケースは存在するのでしょうか?銀行口座をそのままにしておいた方が良い主なケースは、次のとおりです。
相続放棄を検討している場合
相続放棄を検討している場合には、死亡した家族の銀行口座はそのままにしておくべきでしょう。
相続放棄とは、家庭裁判所で手続きをすることで、はじめから相続人ではなかったこととする手続です。たとえば、亡くなった人の借金が多くこの借金を相続してしまっては困る場合や、亡くなった人と長年音信がなく他の相続人とできるだけ関わり合いを持ちたくない場合などに、相続放棄を検討することとなります。
相続放棄をすると、プラスの財産も一切相続できなくなる代わりに、マイナスの財産も引き継がずに済むこととなるためです。
しかし、相続放棄には自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月という期限があるうえ、いったん「単純承認」をした後では、もはや相続放棄をすることはできません。そして、故人の銀行口座から預金を引き出したり、故人の銀行口座を解約したりする行為は、この単純承認にあたる可能性があります。
そのため、相続放棄を検討している際には死亡した家族の銀行口座は触らずに、そのままとしておくべきでしょう。
定期的な入金がある場合
死亡した家族が個人事業で不動産賃貸業をしていた場合などには、故人名義の銀行口座に定期的な振込入金がある場合もあるでしょう。この場合に、仮にその入居者などへ連絡する前に銀行口座を解約するなどしてしまえば、家賃の入金ができず、混乱が生じてしまいかねません。
そのため、死亡した家族の口座に定期的な入金がある場合には、その相手(例でいえば、入居者)へ振込先口座の変更を連絡するまで、故人の銀行口座はそのままにしておいた方がスムーズでしょう。
ただし、いつまでも故人名義の口座を使い続けるわけにはいきません。そのため、入居者などへ口座変更の連絡をしたら、すみやかに口座解約などの手続きを進めるべきです。
死亡後すぐに引き出せなくなる?

銀行に口座名義人の死亡を知らせた時点で、その口座を通じた取引は一切できなくなります。いわゆる「口座凍結」です。
口座からの引き出しや預け入れはもちろん、振り込みの受取や引き落としもできなくなるので、家賃収入や報酬などの受け取り予定がある場合や、固定費などの引き落とし口座に指定している場合は注意しなければなりません。
もし振込みや引き落としの予定がある口座であるなら、その予定日より前に先方に連絡をして振込先を変更したり、引き落とし口座の変更手続きを取ったりするなどの対応が必要になります。
相続手続きをしなくても預金を引き出すための方法

銀行に口座名義人の死亡を届け出て口座凍結がされると、先ほどお伝えしたような手続きでは対処できない困りごともあります。
例えば、死亡した本人の葬式費用を預金から引き出そうと思って窓口へ行ったのに、その場で凍結になってしまったというケースがあります。
他にも故人の名義の口座にある預金で、残された家族が生活している場合など、預金口座の凍結によって普段の生活が成り立たなくなってしまうことがあります。
遺産分割などのトラブルの防止のためには口座凍結は理にかなった方法なのですが、このような困った事態を防ぐためにできることはあるのでしょうか?
死亡前に引き出しておく
口座名義人が死亡前に病気や療養で入院していたり介護を受けていたりした場合は、遺族はその支払いに備えて亡くなる直前の時期に本人の口座からある程度の金額を引き出しておいたということもあるでしょう。
口座名義人が生きているときに、本人に依頼された人がお金を引き出し本人のために使う目的ならば、何ら問題はないはずですが、その直後に亡くなった場合などは注意が必要です。
税務署は、亡くなった方の預金口座の過去の入出金履歴を確認して、相続財産の調査をすることがあります。
そのため、死亡直前の預金からの引き出しは、本当に本人の意思によるものかどうかがわかるようにしておくことが重要です。
常日頃、親や兄弟などから依頼を受け、預金の引き出しやそのお金で買い物や支払いを頼まれることがある場合は、いつ不測の事態がおきても良いように記録をつけるようにしてください。
逆に記録がなくて税務署から指摘を受けた際に証拠を示せないと、「亡くなる直前に預金を引き出して相続財産を隠したのでは?」と疑われることになりかねません。
また、他の相続人から相続財産の使い込みを疑われてしまうこともあります。
支払い先からの領収書や内容の明細、購入したときのレシートなどはすべて保存しておき、さらに出納帳に収支を記載しておくようにすれば安心です。
死亡後引き出す
口座名義人が死亡しても、銀行に届け出をするまでの間、暗証番号を知っていればキャッシュカードで預金からの引き出しは可能です。
しかしながら、これは他の相続人とのトラブルの元になる可能性が高いので、決しておすすめできません。
相続人全員の書面による同意を得ている場合以外は、死亡後は預金の引き出しはしないようにしましょう。
また、のちほど解説しますが、亡くなった方に借金があるなどの理由で、相続放棄をする可能性がある場合も注意が必要です。
相続が開始した後に預金を引き出すと、遺産を相続することを認めた扱いになり、相続放棄ができなくなることがあります。
方法③:相続預金の仮払い制度を使う
口座の凍結により遺族がお金に困る事態を解決するために、2018年の民法改正では遺産分割前の相続預金から一定額の仮払いができる制度が新設され、2019年7月から施行されています。
この預金の仮払い制度は、葬儀費用に充てるためや、相続人である遺族の当面の生活費に充てるためであれば、口座凍結後でも預金を一定額まで引き出せる制度です。
遺産分割協議が整う前でも、また他の相続人との合意がなくても、相続人単独で手続きをして預金を引き出せます。
そして、この預金の仮払い制度には次の2種類の方法があります。
- 家庭裁判所に申し立てて、利用目的や金額の判断を受ける方法
- 家庭裁判所の判断がなくても、金融機関への手続きで引き出せる方法
どちらの方法を利用するのかは、必要としている金額や手続きにかかる期間をどれくらい待てるかなどに照らし合わせて選ぶことになります。
家庭裁判所に申し立てて預金を引き出す方法
家庭裁判所に申し立てて認められれば、預貯金に対する相続人の法定相続分に当たる全額またはその一部を仮払いで引き出すことができます。
ただし、申し立てをするための手間や費用がかかり、日数が比較的多くかかる点がデメリットです。
家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で手続きする方法
家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で手続きをする方法では、「150万円」と「預金残高×1/3×法定相続割合」のいずれか低い額を上限として、預金の払い戻しを受けられます。
裁判所での手続きが不要なので手間も日数も比較的少なくて済み、費用もほとんどかかりません。
ただし、金融機関で預金の仮払いを受けるためには、戸籍謄本などをそろえた上で一定の手続きが必要です。
家庭裁判所に申し立てをする方法に比べれば早く預金を引き出せますが、実際に預金を引き出すまでに多少の日数がかかることがあり、葬式費用の支払いなどに間に合わない場合があります。
銀行口座をそのままにしておいた方が良いケース

ここまでは、死亡した家族の銀行口座に関して遺族がいかに手続きをするかという視点で考えてきました。
逆に、口座の解約や引き出しなどの手続きはせずに、そのままにしておいた方が良いケースもあるので紹介しましょう。
ケース①:相続放棄するとき
現金や不動産などのプラスの遺産だけでなく、借金などのマイナスの遺産も相続財産に含まれて相続の対象になります。
相続放棄をすれば遺産を一切相続しないことになり、故人に借金がある場合でも相続人は返済義務を負わずに済みますが、「相続放棄ができなくなるケース」に注意が必要です。
たとえば、仮払い制度を使って預金を引き出して使ったり、口座の解約手続きをしたりすると、遺産を相続することを認めたと見なされて、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄ができなくなると、仮に故人に借金があった場合には、借金も含めてすべての遺産を相続しなければいけません。
そのため、遺産に借金が含まれていて相続放棄を検討している場合や、実家を相続しても使い道がなくて相続放棄をする可能性がある場合などには、預金の取扱いには特に注意してください。
このような場合に、もしも銀行に死亡の連絡だけはしておくなら、相続放棄を考えているので手続きはしない旨を伝えると良いでしょう。
ケース②:残高が少額のとき
遺族が死亡の届け出をせずに、銀行も口座名義人の死亡を知る機会のないまま、口座が凍結もされずに放置されたままになってしまうことがあります。
解約の手続きにかかる煩雑さや、交通費、書類の取得費などと天びんにかけたとき、残高がそれに見合わないほど少額だったら、解約の手続きをせずにそのままにしておくのが一番良いかもしれません。
最後の取引から10年経過した口座の預金は「休眠預金」と呼ばれます。
2016年に休眠預金等活用法が成立したことにより、休眠預金は民間公益活動に活用されることになりました。
口座名義人が死亡した預金口座内の預金を、民間公益活動で活用してもらうために寄付をしたと考えれば、良い選択肢かもしれません。
銀行での相続手続きを効率良く行うために
銀行口座の相続手続きを効率よく行うためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?主なポイントは、次のとおりです。
銀行に電話などで手続き方法を確認してから取り掛かる
死亡した家族の銀行口座の手続きをする際には、いきなり窓口へ出向くのではなく、まずは支店などに電話をして手続き方法を確認すると良いでしょう。なぜなら、最近は郵送などで手続きができる銀行も増えており、わざわざ窓口へ出向かなくても手続きができる可能性があるためです。
また、窓口へ出向くとしても必要な書類を持っていなければ、二度手間となってしまうかもしれません。そのため、効率よく手続を進めるためには、まず電話などで確認してから出向くことをおすすめします。
手続き時には予約をしてから出向く
銀行の相続手続きで窓口へ出向くこととなった場合には、予約をすることをおすすめします。予約をせずに出向けば長時間待たされる可能性が高くなるほか、担当者が不在で後日の出直しが必要となる可能性もあるでしょう。
代行サービスを利用する
故人の遺した銀行口座が多い場合や仕事などでなかなか銀行の開いている時間に出向けない場合、煩雑な手続きを自分で行いたくない場合などには、代行サービスの利用も検討すると良いでしょう。
銀行口座解約の手続き代行サービスは、主に司法書士や行政書士などが担っています。代行サービスを利用することで、自分でかける手間や時間を最小限に抑えることが可能となるでしょう。
銀行口座の相続手続きは早めの対策が大切
家族が亡くなって実際に相続が開始すると、多くの手続きが必要になり何かと忙しくなります。
生前に対策をしておくと相続開始後の相続人の負担を減らせるので、銀行口座についても早めに対策を講じておくことが大切です。
たとえば、どこの銀行に口座を持っているのかを親が子に生前に伝えておけば、相続が開始したときにどの金融機関に連絡すれば良いのかすぐにわかります。
銀行口座の存在に気付かずそのままにしてしまい、遺産を相続し損ねることもありません。
また、高齢の親がいくつもの銀行に口座を持っている場合には、口座を整理して預金を特定の銀行の口座にまとめてもらっても良いでしょう。
相続開始後に手続きをする金融機関の数が減れば、相続人が自分で解約手続きをするときの負担が減り、専門家に任せる場合でも依頼する手続きの数が減って費用を抑えられることがあります。
生前から対策をしておくと相続手続きがスムーズに進むので、早めの相続対策を心掛けるようにしましょう。
まとめ
口座名義人の死亡による銀行口座の手続きは、仮に放置をしても他人に迷惑がかかるものではなく、罰則もありません。
しかし、手続きをせずにそのままにすると預金を相続できず、相続に関するトラブルの原因になる場合があるなど、思わぬ不利益を被ったり不都合が生じたりすることがあります。また、時間が経つにつれて相続に関係する人の状況が変化して、手続きが難しくなっていく可能性もあるでしょう。
銀行口座や相続に関連する一連の手続きは面倒ですが、少々お金がかかっても代行サービスや専門家に依頼するなどして、なるべく早い時期に済ませておくことをおすすめします。
また、銀行口座の手続きの問題は、相続人としての立場からだけでなく、ご自身が亡くなった時の残された家族にもいつか降りかかることです。使用していないまま放置している自分の金融機関の口座があれば、早めに整理しておくと良いでしょう。