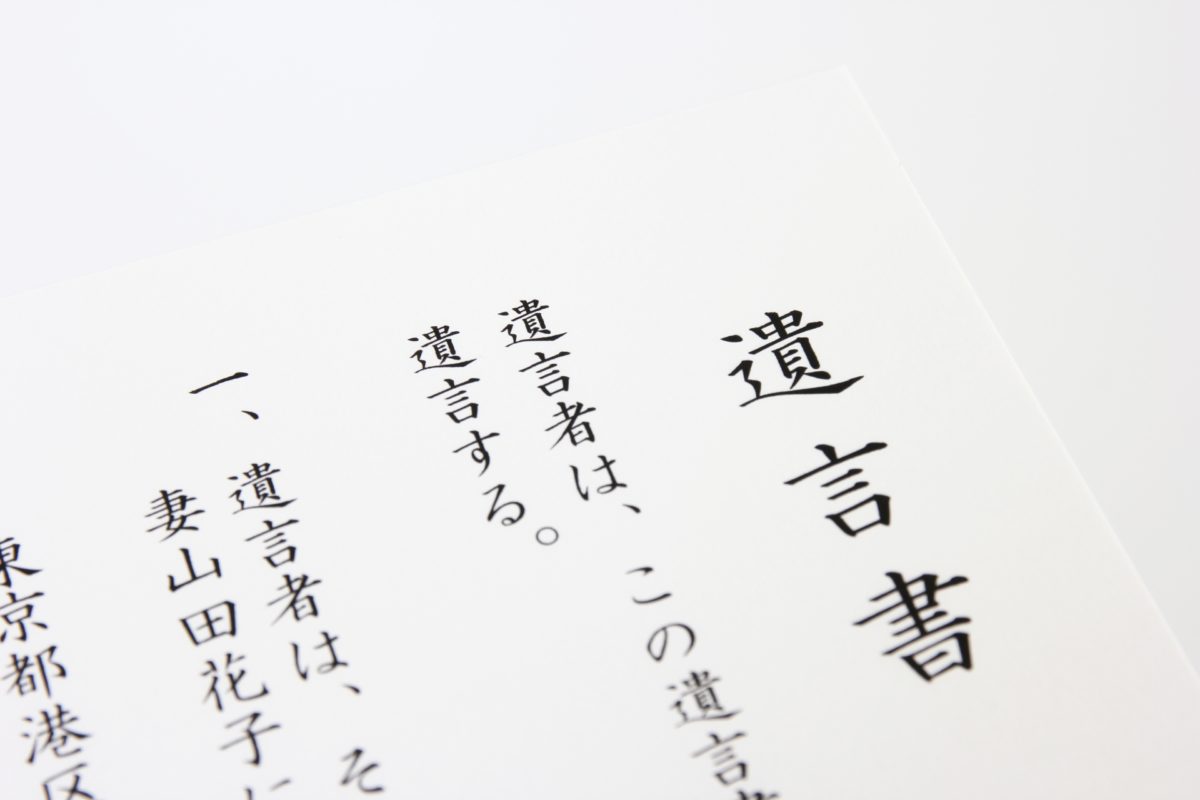財産の残し方を自分で決めることができる遺贈は、多くの人が活用している相続対策の一つです。しかし、一口に「遺贈」と言っても種類があり、贈与などの他の相続対策との違いも理解した上で活用しなければなりません。
この記事では、遺贈の概要や相続・贈与との違い、遺贈を行う場合の注意点を解説していきます。
目次
遺贈とは?
.jpg)
遺贈とは「遺言によって財産を渡すこと」です。自分の死後に効力を発揮する遺言を残しておけば、自分の財産を渡したい人に渡すことができます。
一方で、遺言を残すなどの相続対策を何もせずに亡くなった場合には、財産の分け方は残されたご家族などの相続人が決めることになります。「自分の死後には財産をこの人にもらって欲しい」といった希望がある場合に有効なのが遺贈です。
ただし、遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があり、異なる点があるため気をつけなければなりません。包括遺贈と特定遺贈は、財産を残す側・財産を引き継ぐ側それぞれにとってメリットもデメリットもあります。
遺言を残して遺贈を行う場合は、両者の特徴を理解した上で最適な方法を選択することが大切です。
種類①:包括遺贈
包括遺贈とは「渡す財産の割合を指定して、財産の全部または一定割合を渡す遺贈」です。「相続財産のうち4分の1をAに遺贈する」といった形で遺言書に書く遺贈を指します。
遺言書を作成してから実際に亡くなるまでの間に財産の内容が変わることがあっても、包括遺贈ではあくまで割合を指定しているだけなので問題ありません。ご自身が亡くなり相続が開始された時点の財産に対して、遺言で指定した割合を渡すことができます。
ただし、包括遺贈の財産には、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれるため注意が必要です。包括遺贈では財産のすべてが対象になるので、プラスの財産とマイナスの財産すべての資産に対する割合として、渡す財産の金額が決まります。亡くなった方に多額の借金がある場合、財産を受け取る者として指定された人は、借金を背負うことにもなりかねません。
このような場合には、財産を受け取る側は包括遺贈を拒否して放棄することができます。ただし、後述するように、包括遺贈を放棄できる期間は決まっているため注意が必要です。
種類②:特定遺贈
特定遺贈とは「渡す財産を特定の物に指定して行う遺贈」です。「〇〇県△△市××町1-1-1の土地をBに遺贈する」といった形で遺言書に書く遺贈を指します。
包括遺贈と比べたときのメリットは、指定する特定財産として借金などを指定しない限りマイナスの財産が含まれないことです。しかし、遺言書を作成してから亡くなるまでの間に指定した財産がなくなった場合は、特定遺贈そのものが無効になってしまいます。
包括遺贈とは違って、財産内容に変化が生じた場合に遺言書を作り直さなければいけないことがある点がデメリットと言えるでしょう。また、特定遺贈によって相続人以外の人に財産を渡すと、包括遺贈ではかからない不動産取得税がかかる点もデメリットです。
遺贈と相続の違い

生前に遺言書を作って財産の渡し方を決めておく遺贈は、相続とはさまざまな点で異なります。相続と遺贈の違いは、単に財産を残す側が残し方を決められるかどうかだけではありません。特に、税金や土地の手続きで違いがあるため、それぞれのメリット・デメリットを理解しておくことが大切です。
そこで、まずは相続が一体どのような制度で相続税はどう計算するのかを解説します。続いて、遺贈と相続の相違点を解説するので、遺贈を選択するかどうか決める際に参考にしてください。
相続とは
ある人が亡くなると、その人の財産は残された家族などが引き継いで相続することになります。
- 財産を相続する人が「相続人」
- 財産を残して亡くなって相続される人が「被相続人」
遺言書などによる指定がない場合には、法律によって規定された人が相続人(法定相続人)となって財産を相続します。
ただし、家族や身近な人であれば誰でも法定相続人になれるわけではありません。法定相続人になる人の範囲や対象は法律で決まっていて、法定相続人ごとに相続する財産の割合(法定相続分)や最低限受け取ることができる割合(遺留分)は法律で規定されています。相続を理解する上では、まずは「誰がどれだけ財産を相続できるのか」を知ることが大切です。
法定相続人
法定相続人とは「亡くなった人の財産を相続する人として法律で定められている人」のことです。遺言書の内容が優先されて法定相続人以外の人に財産を渡す場合は別ですが、被相続人が亡くなると法定相続人が財産を相続します。
配偶者は、常に法定相続人です。子・親・兄弟姉妹がいても、配偶者は財産の一定割合を相続できます。一方で、子・親・兄弟姉妹には相続できる順番があり、相続できるかどうかは次のとおりです。
| 法定相続人 | 法定相続の順位 |
|---|---|
| 配偶者 |
|
| 子や孫などの直系卑属 |
|
| 父母や祖父母などの直系尊属 |
|
| 兄弟姉妹 |
|
順位が上の法定相続人が先に相続権を取得して財産を相続します。順位が上位の人がいない場合は、次の順位の法定相続人が相続する仕組みです。
ただし、配偶者には内縁の妻は含まれず、子については再婚相手の連れ子は含まれません。相続放棄をしている場合も最初から相続人ではなかった扱いになるため対象外ですが、養子縁組をしている場合は実子として扱われるので第1順位の法定相続人になります。
法定相続分
法定相続分とは「法定相続人がどれくらいの割合の財産を相続するのかを定めた割合」です。法定相続人には配偶者・直系尊属・直系卑属がいますが、相続人が誰かによって法定相続分が異なります。
| 相続する人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者のみ |
|
| 直系卑属(子など)のみ |
|
| 配偶者と直系尊属(親など) |
|
| 直系尊属(親など) |
|
| 配偶者と兄弟姉妹 |
|
| 兄弟姉妹のみ |
|
法定相続順位が同順位の人が複数人いる場合は、上記の表の割合を均等に割った値が相続分です。例えば、配偶者と子2人が法定相続人の場合、表のとおり法定相続分は配偶者2分の1・子2分の1ですが、子が2人なので子1人あたりは4分の1となります。
遺贈と相続の相違点
法律で定められた法定相続人に財産が渡る一般的な相続と、遺言書によって財産を渡す遺贈では、次のような違いがあります。
- 相続税の2割加算・基礎控除
- 不動産取得税・登録免許税
- 不動産の登記手続き
- 農地法に基づく許可
- 借地権・借家権
遺贈を受けて財産を渡される側にとっても、かかる税金や必要な手続きが相続の場合とは異なります。相続対策として遺贈を検討する場合には、財産を残す側の事情だけでなく、残されるご家族などのことも考えて相続対策を検討・選択するようにしましょう。
相違点①:相続税額の2割加算・基礎控除
相続税の2割加算とは、配偶者と一親等の血族(親や子)以外の人が財産を取得した場合に相続税額が1.2倍になる制度です。故人と身近ではない人が財産を受け取った場合には、偶然性が高いということで、税額が加算される仕組みになっています。
相続によって法定相続人が財産を受け継ぐ場合、第3順位の兄弟姉妹が相続する場合は2割加算され、配偶者・子・親が相続する場合には2割加算はありません。しかし、遺贈では財産を渡す人を法定相続人以外に指定できます。
遺贈では、2割加算が適用されて相続税額が1.2倍になるケースが多いため注意が必要です。また、相続税を計算する際に相続財産価格から引く基礎控除額にも違いがあります。
基礎控除額の計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。遺贈によって、法定相続人以外の人が財産を受け取る場合であっても基礎控除額は増えません。仮に同じ財産を同じ人数で受け継いだ場合でも、基礎控除額は法定相続人の数のみに影響するため、基礎控除額が変わったり2割加算が適用されて相続税額が変わることがあります。
相違点②:不動産取得税・登録免許税
不動産を取得すると「不動産取得税」がかかり、不動産の所有者を変更するために登記手続きを行うと「登録免許税」がかかります。しかし、相続によって不動産を取得した場合には不動産取得税はかかりません。包括遺贈によって不動産を取得した場合も不動産取得税はかかりませんが、特定遺贈で法定相続人以外の人が取得した場合は不動産取得税の課税対象です。
不動産の登記手続きの際に発生する登録免許税は、遺贈でも相続でも不動産取得者に課されます。ただし、税率が異なっており、相続人が取得するケースでは0.4パーセントですが、遺贈によって法定相続人以外が不動産を取得すると2.0パーセントです。不動産は高額なので、税率がわずかでも異なると税額が大きく変わるため気をつけた方が良いでしょう。
相違点③:不動産の登記手続き
相続によって不動産を取得した場合には、取得した相続人が単独で登記を行うことができます。しかし、遺贈の場合には取得者が単独で登記手続きを行うことはできません。他の相続人と共同で手続きをする必要があり、争族になって他の相続人の協力を得られないと登記手続きが進まない可能性があります。
相違点④:農地法に基づく許可
取得した土地が農地の場合、法務局への登記手続き以外に農業委員会への届出も必要になります。農地は、他の土地と違って「農地法」によって特に保護されているからです。
さらに、相続人以外の人が特定遺贈によって農地を取得する場合には、農業委員会の許可を得なければなりません。許可が下りずに農地を取得できない場合があります。
一方で、相続によって法定相続人が農地を取得するケースや包括遺贈で取得するケースでは、許可は不要で届出のみ必要です。そのため、農業委員会から許可が下りずに却下される心配はありません。
農業に従事していない人や従事する予定のない人に特定遺贈によって農地を渡そうとしても、許可が下りないため可能性があるので慎重に検討してください。
相違点⑤:借地権・借家権
借地権とは建物を建てるために他人から土地を借りている人が持つ権利で、借家権とは建物を借りている人が持つ権利です。借地権や借家権も相続や遺贈によって渡すことができますが、地主や家主の承諾が必要かどうかという点で相続と遺贈では異なります。
相続によって借地権・借家権を受け継いだ場合は、地主や家主の承諾は不要です。仮に土地や建物の明け渡しを要求されても、相続による権利の取得であれば応じる義務はありません。しかし、遺贈によって借地権・借家権を取得する場合には、地主や家主の承諾が必要になります。
遺贈と贈与の違い

生前から何らかの相続対策をしておきたい場合、遺言書を作って遺贈を行う以外にも財産を直接贈与する方法が考えられます。
では、遺贈と贈与では一体どのような違いがあるのでしょうか?
財産を渡したい人に渡せる点では、遺贈も贈与も同じです。ただ、それぞれのメリット・デメリットを理解して正しく使い分けられるようになりましょう。
贈与とは
贈与とは、財産を無償で提供することです。法的には契約の一種であり、贈与者の意思表示だけでなく贈与される側(受遺者)が承諾することで成立します。
生前贈与
生前贈与とは、文字とおり生前に財産を贈与することを指します。通常の相続や遺贈のように自分の死後に財産を相手に渡すのではなく、生前に渡しておく方法です。
自分が死んで相続が発生した場合の相続財産を減らすことができ、将来の相続税を減らすために活用する人も多い相続対策の手法の一つです。
死因贈与
死因贈与とは、自分が死んだ際に財産を贈与することを贈与契約として生前に約束しておくことです。「私が死んだらこの土地をAに贈与します」といった形で生前に贈与契約を結びます。
死後に財産を渡す点では、死因贈与も遺言書を作成する遺贈も似ています。しかし、贈与は相手側の承諾が必要である一方、遺贈は遺言作成者が単独でできる行為です。その他の点でも遺贈と贈与は異なるので、この後詳しく紹介していきます。
遺贈と贈与の相違点
自分の財産を渡すという点では同じでも、遺贈と贈与には次のような違いがあります。
- 当事者間の合意の有無
- 撤回や放棄の可否
- 相続税と贈与税
- 不動産取得税・登録免許税
- 不動産の登記手続き
遺贈と贈与それぞれの特徴を理解して、ご自身やご家族にとって最適な相続対策を選択するようにしましょう。
相違点①:当事者間の合意の有無
贈与は、贈与者と受贈者の間で贈与契約を結ぶ必要があり、当事者間の合意が必要です。しかし、遺贈は財産を残す者だけの意思で行うことができ、相手側の同意は必要ありません。遺言書を作成した人が生きている間、財産を受け取る側の人が遺言の内容自体を知らないということも当然あり得ます。
相違点②:撤回や放棄の可否
遺言書は、作成者本人が自らの意思によって作成するものなので、内容を撤回したり別の内容で遺言書を作成し直すことが可能です。すでに遺言書を作成している場合でも、新たに遺言書を作れば日付が新しいものが優先されます。わざわざ以前の遺言書を撤回するための手続きは要りません。
また、遺贈によって財産を渡される側は、そもそも遺言の内容を事前に知らない場合もあります。そのため、遺贈を放棄して財産を受け取らないことも選択できます。
一方で、贈与は双方が合意して契約を結んでいるものなので、一方的な撤回や放棄はできません。ただし「契約自体をなかったことにしましょう」といった合意を別途することによって、事後的に契約を解除したり取り消すことは可能です。
なお、負担付死因贈与では事後的な撤回がもはやできない場合があるため注意してください。負担付死因贈与とは「△△をしてくれたら私の死後に〇〇をあなたに贈与します」といった形で、財産を贈与する条件として相手方に一定の負担を求める死因贈与です。契約内容のうち既に履行が終わっている部分は撤回することができないものとされています。
生前に何らかの負担を相手に求める負担付死因贈与では、生前からすでに負担に対応する部分が履行されていることが多く、撤回できないケースが少なくありません。贈与する側が生きている間に撤回することができないだけでなく、贈与者の死後に受贈者が放棄して贈与財産を受け取らないという選択もできないので注意が必要です。
相違点③:相続税と贈与税
遺贈と贈与では、かかる税金が異なります。遺贈で取得した財産は相続税の課税対象で、贈与で取得した財産は贈与税の課税対象です。
ただし、贈与の中でも死後に財産を渡す死因贈与は、性質が相続に近いため「贈与税」ではなく「相続税」がかかります。贈与税の方が相続税よりも税額が大きくなることが多く、同じ財産でもどちらの税金の課税対象になるかで税額が変わるので注意が必要です。
相違点④:不動産取得税・登録免許税
不動産を取得した場合は、不動産取得税や登録免許税がかかり、贈与によって取得した場合にも課税されます。遺贈の場合は、法定相続人以外の人が不動産を取得すると贈与の場合と同様に課税されますが、法定相続人が遺贈によって取得する場合は税制面で有利です。
遺贈によって法定相続人が不動産を取得する場合は、不動産取得税は非課税で登録免許税は税率が低くなります。
相違点⑤:不動産の登記手続き
死因贈与と遺贈は死後に財産を渡す点で同じですが、不動産を渡す場合には始期付所有権移転登記ができるかどうかで異なります。死因贈与では贈与者の生前から仮登記を行うことで、贈与者の死後に不動産の所有権が受遺者に移るようにあらかじめ手続きをしておくことが可能です。
しかし、遺贈では仮登記はできません。仮登記すれば、財産を受け取る側にとっては贈与を受けられる確実性が各段に増すことになります。
財産を受け取る側が安心できるように始期付所有権移転登記を行いたい場合には、遺贈ではなく死因贈与を選択すると良いでしょう。
遺贈に関する注意点

自分の死後に遺言が効力を発揮するためには、遺贈を行う際に注意すべき点があります。遺贈によって財産をもらう側も、自分が望まぬ形で財産を渡される可能性があるので注意が必要です。遺贈によって財産を渡す側も渡される側も、遺贈に関する注意点はしっかりと押さえておくようにしてください。
注意点①:遺贈する場合
遺言書を作成して遺贈によって、財産を残す側が特に注意すべき点は次のとおりです。
- 遺言書の形式不備による遺贈の無効化
- 遺言書の内容が遺留分に抵触しないかどうか
- 遺言の内容の確実な実行のための遺言執行者の選任
①遺言書の形式不備
遺言書は、形式が守られていてこそ有効です。形式不備によって無効になってしまうことだけは何としても避けなければなりません。一般的な感覚では「そんなことでも無効になるの?」と思えるようなことでも、遺言書が無効になることが多々あります。
例えば、遺言書を作成した日付で、2020年1月吉日などとなっていると、具体性に欠けるため無効です。2020年1月1日といった形で明確に記載しなければなりません。
自分の死後に遺言書が無効扱いになると、遺言のとおりに財産を渡せなくなってしまいます。遺言書の作成を検討している方は、形式不備による無効化を防ぐためにも、遺言書作成に詳しい専門家に相談した方が良いでしょう。
2.遺留分
配偶者や子などの一定の範囲の人には、相続財産のうち少なくとも相続できる割合が権利として法律で定められています。この「財産を相続できる権利として最低限保証されている相続割合」が遺留分です。
遺言書を作成して財産を遺贈する場合でも、遺留分という相続人の権利よりも被相続人の遺言の内容が優先されるわけではありません。
例えば、遺留分を持つ相続人がいるのに、他の人に全財産を渡すような内容の遺言書を作っても、遺留分にあたる割合の財産を受け取るための請求手続きを相続人は行うことができます。遺言を残した人の思いとは違う形で財産が渡ってしまうため、遺言を残す際には遺留分に注意が必要です。
配偶者・直系尊属(親など)・直系卑属(子など)には遺留分が認められており、相続人ごとに遺留分は次のように定められています。
| 相続する人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者のみ |
|
| 配偶者と直系卑属(子など) |
|
| 直系卑属(子など)のみ |
|
| 配偶者と直系尊属(親など) |
|
| 直系尊属(親など)のみ |
|
遺言執行者の選任
遺言がある場合でも、相続人同士の争いが起きて財産相続の手続きが遅々として進まないケースは多くあります。財産を受け取って欲しい人に実際に財産が渡るまでに時間がかかってしまうかもしれません。ご自身が亡くなって相続が開始されたときに、遺言の内容をより確実に実現するために遺言執行者を選任しておくと安心です。
遺言執行者とは「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者」のことを指します。遺言を作成したときに遺言執行者を指定するかは自由なので、選任しなくても問題ありません。
ただし、相続人の廃除を行う場合など、一定のケースでは遺言執行者が必要です。また、相続人を代表して不動産の登記手続きを行う権限などを持つ遺言執行者を選任しておけば、相続開始後の手続きがスムーズに進む可能性が高まります。遺言書の作成を弁護士や司法書士に依頼する際に遺言執行者にもなってもらい、遺言の内容が確実に実行されるようにしておくと良いでしょう。
注意点②:遺贈される場合
財産を渡されて遺贈される側が特に注意すべき点は「遺贈を放棄できる期間」です。
遺贈によって自分が望まぬ形で財産を渡されることになったり、財産を受け取っても高額な相続税を支払えないため拒否したい場合もあるはずです。遺贈の種類によっては、拒否して遺贈を放棄できる期間が短いので注意してください。
遺贈を放棄できる期間
特定遺贈であれば、相続開始後いつでも放棄をすることができます。しかし、包括遺贈では放棄する場合には相続開始後3ヶ月間しかできません。
この期間内に放棄をしないと財産を受け取ることになってしまいます。亡くなった方に借金などの負債があった場合でも引き継ぐことになるので注意が必要です。
ご家族などが亡くなってご自身が相続人になる場合には、遺言の有無や借金などのマイナスの財産の有無をすぐに確認するようにしてください。必要な場合には相続放棄の手続きを期間内に家庭裁判所で行うようにしましょう。
まとめ
遺言を作成して財産を渡したい人を指定する遺贈は、自分が望む形で財産の残し方を決められる相続対策の一つです。遺言書の形式不備などには注意が必要ですが、包括遺贈と特定遺贈それぞれの特徴を踏まえて遺贈を活用すると良いでしょう。
遺贈だけでなく、生前贈与や死因贈与など、財産の残し方・渡し方にはさまざまな方法があります。心情面だけでなく税務面や手続き面も含めて相続対策の検討を行って、財産を渡す側も渡される側も納得できる最適な選択を行うようにしてください。