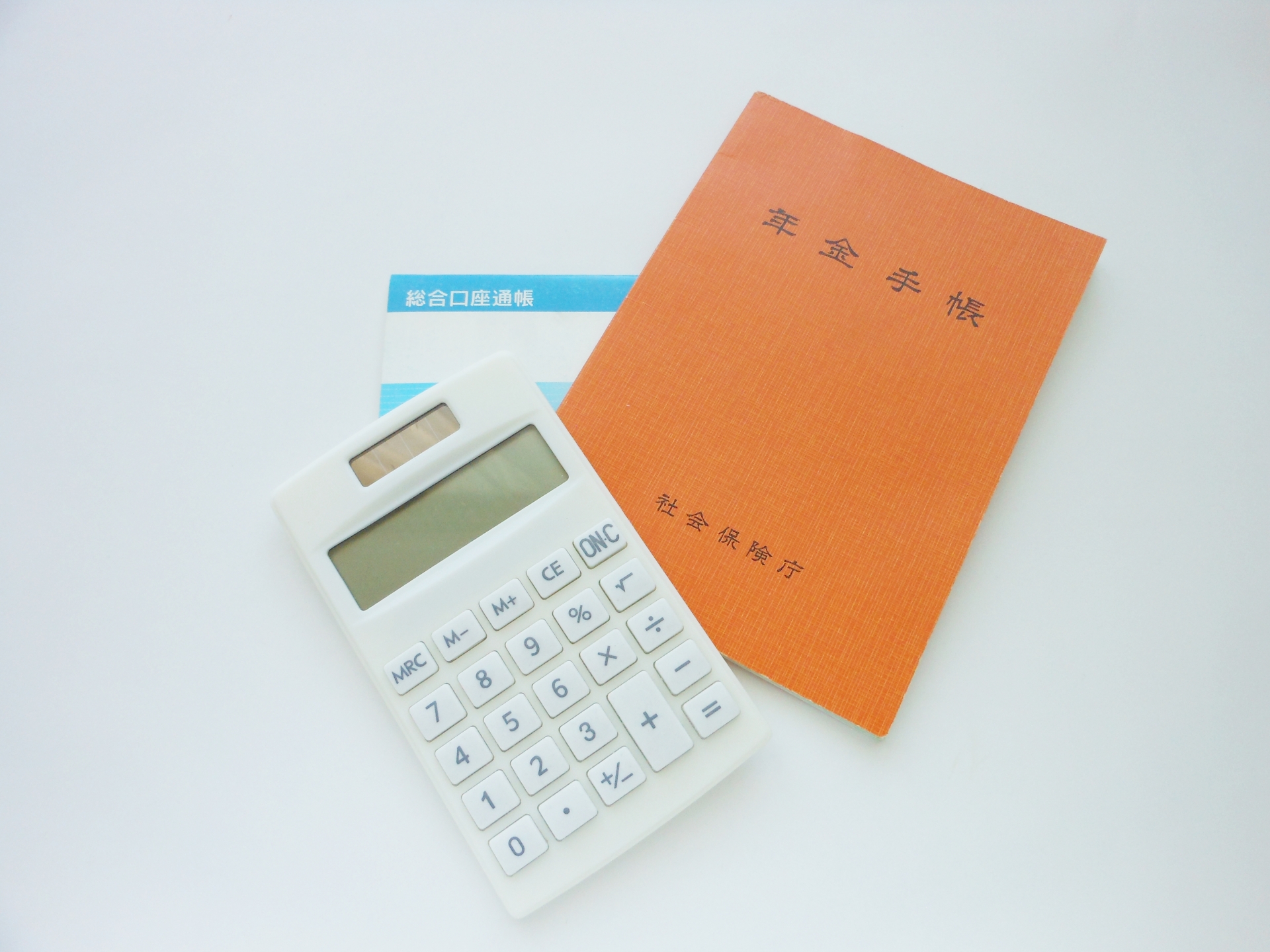遺族年金は、誰がいつまでもらうことができるのでしょうか?
今回は、遺族年金の種類ごとに、受給資格やいつまで受給できるのかといった点や受給するための手続きなどについて詳しく解説します。
目次
遺族年金の種類

遺族年金には、主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金とでは、受給できる人やもらえる額などが異なります。
まずは、ご自身が受給できる遺族年金がどちらに該当するのか確認しましょう。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等であった人が亡くなった場合にもらえる可能性のある遺族年金です。
受給には、亡くなった人が国民年金の被保険者等であったことの他、後述する複数の要件を満たす必要があります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等であった人が亡くなった場合にもらえる可能性のある遺族年金です。
こちらは、亡くなった人が厚生年金の被保険者等であったことの他、後述する複数の要件を満たすことで受給ができます。
「遺族基礎年金」は誰がいつまでいくら受給できる?

それでは、まず遺族基礎年金について解説していきましょう。
遺族基礎年金は、誰がいつまで受給することができるのでしょうか。
誰が亡くなったときにもらえる?
遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が亡くなった場合にもらえる可能性があります。
まずは、亡くなった人についての要件を確認しましょう。
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人であり、日本国内に住所を有している人
- 老齢基礎年金の受給権者
- 保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上を満たしている人
ただし、①、②の場合には、死亡日の前日において次のAまたはBの保険料納付要件のいずれかを満たしていることが必要です。
- A:保険料納付要件の原則:死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、免除期間等を含む保険料納付済期間が3分の2以上あること
- B:保険料納付要件の特例:令和8年3月31日以前に死亡した場合は、Aの保険料納付要件を満たさなくても、死亡日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと
もらえるのはどんな人?
遺族基礎年金を受給するには、遺族側の要件もあります。
遺族基礎年金を受給する資格のある人は、次のとおりです。
- 子のある配偶者で、死亡した者によって生計を維持されていた人
- 子で、死亡した者によって生計を維持されていた人
ここでいう「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子に限ります。
なお、配偶者と子がいる場合、どちらも受給できるわけではなく、配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子が遺族基礎年金を受給することはできません。
いくらもらえる?
遺族基礎年金として受給できる額(年額)は、次のとおりです。
- 780,900円+子の加算
※子の加算:第1子・第2子は1人につき224,700円、第3子以降は1人につき74,900円
なお、配偶者ではなく子が遺族基礎年金を受給する場合には、第2子以降についてのみ「子の加算」が適用されます。
いつまでもらえる?
遺族基礎年金は、原則として子が全員18歳の誕生日後初めての3月31日を迎えるなど、遺族基礎年金でいうところの「子」が誰もいなくなるまで受給できます。
具体的には、次のような事情が生じた場合に、その事情が生じた人の受給権がなくなると考えてください。
- 受給権者が死亡したとき
- 受給権者が婚姻したとき
- 受給権者が直系の血族・姻族でない者の養子となったとき
- 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を別にするようになったとき
- 遺族基礎年金の受給権を有する子が誰もいなくなったとき
- 子が離縁によって死亡した者の子でなくなったとき
- 子の18歳の誕生日後初めての3月31日が終了したとき(障害等級表の2級以上に該当する状態にある場合を除く)
- 障害基礎年金に該当する程度の障がいのある18歳以上の子が、その障がいの程度に該当しなくなったとき、または20歳になったとき
「遺族厚生年金」は誰がいつまでいくら受給できる?

続いて、遺族厚生年金について解説していきます。
遺族厚生年金は、誰がいつまで受給することができるのでしょうか?
誰が亡くなったときにもらえる?
遺族厚生年金は、次の要件のいずれかに該当する人が亡くなった場合にもらえる可能性があります。
まずは、亡くなった人についての要件を確認しましょう。
- 厚生年金の被保険者
- 厚生年金被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡した人
- 障害厚生年金又は障害共済年金(1級、2級)の受給権者
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人
ただし、①、②の場合は、死亡日の前日において次のAまたはBの保険料納付要件のいずれかを満たしていることが必要です。
- A:保険料納付要件の原則:死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、免除期間等を含む保険料納付済期間が3分の2以上あること
- B:保険料納付要件の特例:令和8年3月31日以前に死亡した場合は、Aの保険料納付要件を満たさなくても、死亡日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと
もらえるのはどんな人?
遺族厚生年金の受給権者は、死亡した者によって生計を維持されていた次の人です。
なお、受給権には順位があり、番号が若い遺族の優先順位が高く位置づけられています。
- 配偶者(夫は55歳以上)、子
- 55歳以上の父母
- 孫
- 55歳以上の祖父母
ここでいう子や孫は、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の人に限ります。
また、子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付です。
そして、夫や父母、祖父母が受給する場合には、支給自体は60歳からとされています。
なお、遺族厚生年金の受給要件と遺族基礎年金の受給要件をどちらも満たす場合には、遺族基礎年金と遺族厚生年金をいずれも受給することが可能です。
いくらもらえる?
遺族厚生年金は、「報酬比例部分」「中高齢寡婦加算」「経過的寡婦加算」の3つから構成されます。
原則として「報酬比例部分」が支給され、別途要件を満たす場合に、「中高齢寡婦加算」や「経過的寡婦加算」が上乗せされるイメージです。
それぞれ解説していきましょう。
報酬比例部分
遺族厚生年金の報酬比例部分は、原則として次の式で計算されます。
- ①平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数
- ②平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数
- ③(①+②)×3/4
ただし、上記で計算をした結果が、次の計算式で算出した額を下回る場合は、次の計算式で算出した額が支給されます。
- ①平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの加入月数
- ②平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の加入月数
- ③(①+②)×1.001×3/4
これらの計算式の中で登場する「平均標準報酬月額」とは、平成15年3月までの被保険者期間における各月の標準報酬月額の平均額です。
また、「平均標準報酬額」とは、平成15年4月以後の被保険者期間における各月の標準報酬月額と標準賞与額を合わせた平均額です。
遺族年金の受給原因が厚生年金の被保険者が死亡したこと、厚生年金被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したこと、又は障害厚生年金又は障害共済年金(1級、2級)の受給権者が死亡したことである場合で被保険者期間が300月(25年)未満のときは、300月とみなして計算することとされています。
遺族厚生年金の計算は複雑であるうえ、慣れていなければ計算に使用する平均標準月額報酬や平均標準報酬額を確認することも容易ではありませんので、受給資格の確認と併せて年金事務所などで金額も確認することをおすすめします。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算とは、遺族基礎年金の受給ができない妻が遺族厚生年金を受け取る場合、一定の要件をもとに遺族厚生年金に上乗せされる加算をいいます。
次のいずれかに該当する場合には、妻が40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算として、年額585,700円(令和3年度)を追加で受け取ることが可能です。
- 夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていたものの、その後子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなった妻
なお、ここでいう「子」も、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子と20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子に限ります。
経過的寡婦加算
経過的寡婦加算とは、遺族厚生年金を受給する妻が昭和31年4月1日以前に生まれた場合に、遺族厚生年金に上乗せして支給される加算をいいます。
これは、以前は専業主婦には国民年金の加入義務がなかったことから、年金額が少なくなってしまう妻を救済するために設けられている制度です。
経過的寡婦加算の額は妻の生年月日により異なり、最大585,700円、最小19,547円(令和3年度)が加算されます。
いつまでもらえる?
遺族厚生年金の受給期間は、原則として次のとおりです。
- 子のいない30歳未満の妻が受け取る場合:5年間
- その他の妻が受け取る場合:一生
- 子や孫が受け取る場合:18歳になる年度末まで(障害年金の障害等級が1級または2級の子であれば20歳を迎えるまで)
- 夫や父母、祖父母が受け取る場合:一生(受け取ることができるのは60歳からという制限あり)
なお、65歳になり受給者自身の老齢厚生年金を受ける権利が発生した場合には、老齢厚生年金の額と遺族厚生年金の額が調整して支給されます。
遺族年金をもらうための手続き

続いて、遺族年金をもらうために必要な手続きについて解説していきます。
- 手続き先を確認する
- 必要書類を集める
- 手続きをする
手続き先を確認する
遺族年金をもらうためには、まずその手続き先を確認してください。
手続き先は、下記のとおりです。
遺族基礎年金を請求する場合
遺族基礎年金の請求先は、原則として住所地の市区町村役場の窓口です。
ただし、亡くなった人が国民年金第3号被保険者期間中であった場合には、近くの年金事務所又は街角の年金相談センターへ請求します。
遺族厚生年金を請求する場合
遺族厚生年金は、近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ請求します。
必要書類を集める
次に、請求に必要となる書類を収集します。
遺族年金の請求に必要となる書類は、次のとおりです。
なお、状況によって年金証書などこれら以外の書類が必要となることもありますので、あらかじめ請求先の窓口へ確認すると良いでしょう。
必ず必要な書類
遺族年金を請求するにあたり、必ず必要となる書類は次のとおりです。
- 年金請求書(請求先の窓口で入手できます)・年金手帳
- 本人の死亡と、請求者との関係のわかる戸籍謄本等(死亡後かつ6か月以内に交付されたもの)
- 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記載すれば省略可)
- 死亡者の住民票の除票(マイナンバーを記載すれば省略可)
- 請求者の収入が確認できる所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等の書類(マイナンバーを記載すれば省略可)
- 子の収入が確認できる書類(マイナンバーを記載すれば省略可、義務教育終了前であれば不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証)
- 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- 遺族年金を受け取る請求者名義の銀行口座の通帳等
死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類
死亡の原因が第三者による行為である場合には、上記と併せて次の書類も必要です。
- 第三者行為事故状況届(所定様式)
- 交通事故証明または事故が確認できる書類
- 確認書(所定様式)
- 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類(源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど)
- 損害賠償金の算定書
手続きをする
書類が揃ったら、手続き先へ出向いて手続きをします。
あらかじめ電話などで予約をしてから出向くとスムーズです。
手続きに時間がかかることもありますので、時間に余裕をもって出向くようにしましょう。
遺族年金の他に受給できる可能性があるもの

家族が亡くなった場合、遺族年金のほかにも受け取ることができる可能性のあるものもあります。
受け取る権利がある場合には、漏れなく手続きをするようにしましょう。
- 寡婦年金
- 死亡一時金
- 労災保険
寡婦年金
寡婦年金とは、夫を亡くした妻が60歳から65歳になるまでの間受け取れる可能性のある年金です。
寡婦年金を受け取るための要件は、次のとおりです。
- 死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間等が10年以上ある夫が死亡したこと
- 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていたこと
- 夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続していたこと
- 夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けたことなく死亡したこと
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないこと
死亡一時金
死亡一時金とは、一定の要件を満たした場合に一定の遺族が受け取ることのできる一時金です。
死亡一時金を受け取るための要件は、次のとおりです。
- 死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が死亡したこと
- 死亡した人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなったこと
- 死亡した人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であること(先に記載した人が優先的に受給できます)
死亡一時金の額は保険料の納付期間により異なり、最大で32万円です。
なお、遺族基礎年金や寡婦年金を受け取る場合には、死亡一時金を受給することはできません。
労災保険
労災保険とは、業務災害又は通勤災害により死亡したときに遺族が受け取ることのできる給付を指します。
一定の要件を満たした場合に遺族が年金か一時金を受け取ることができますので、ご家族が業務に関連して亡くなった際には管轄の労働基準監督署へ確認すると良いでしょう。
まとめ
遺族年金の支給要件や支給金額の計算は複雑ですので、遺族年金を受け取れる可能性がある場合にはすみやかに各窓口へ相談し、漏れなく請求手続きをしておきましょう。
なお、亡くなった日の翌日から5年が過ぎると遺族年金を請求できなくなることには注意してください。