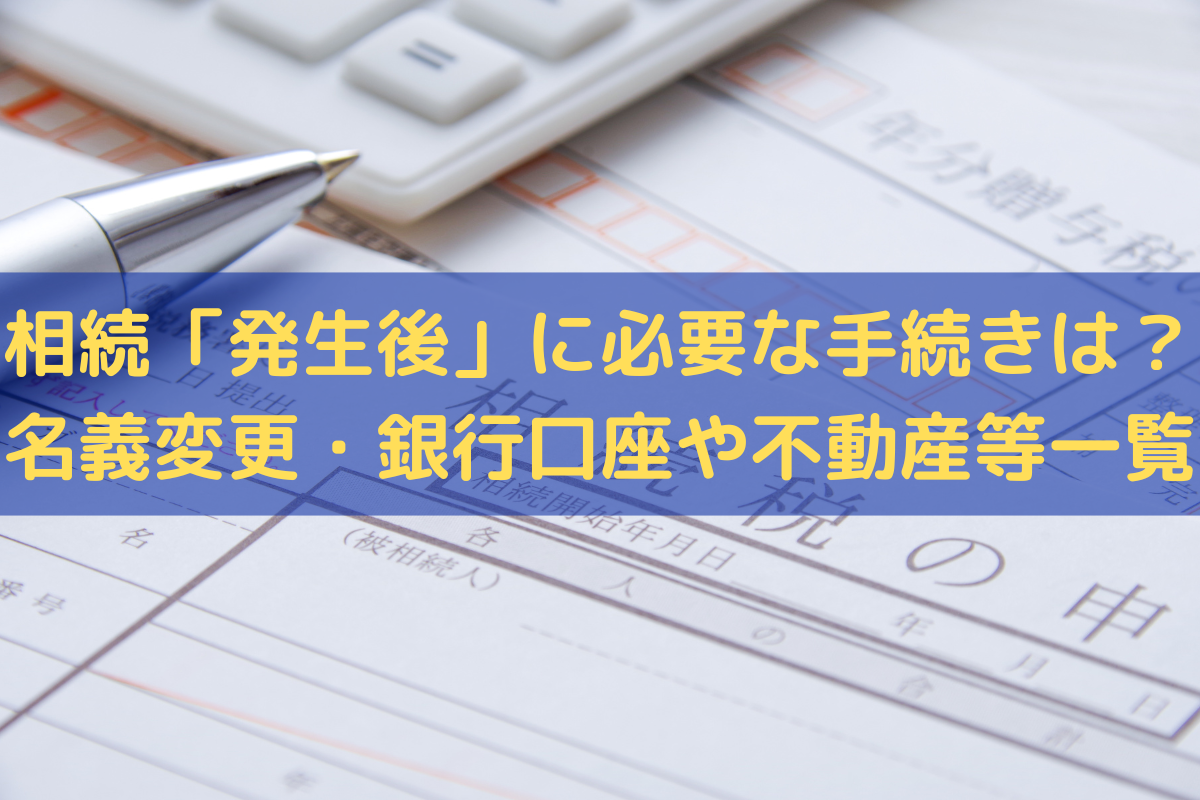相続が発生すると必要になるのが、相続財産の名義変更や解約などの手続きです。しかし、一口に「相続財産」といってもその種類は多岐にわたり、名義変更の手続きをするにもそれぞれ申請する場所も必要な書類も異なります。
そこで今回は、相続に伴って必要となる手続きをわかりやすくまとめて解説します。申請場所や必要な書類、手続きの手順についてもくわしく解説するので、ぜひ相続発生後に手続きをする際の参考としてください。
目次
相続発生後のチェックリスト
相続発生後には、行うべきことが非常に多く発生します。ここでは必要な手続きの概要を表にまとめて紹介しますので、一つずつ進めていきましょう。
| 期限 | 手続の内容 | 行うべきケース | 手続き先 |
|---|---|---|---|
| 死亡後すぐ | 死亡診断書または死体検案書の受領 | すべて | 病院または警察 |
| 葬儀の手配 | すべて | 葬儀会社 | |
| 7日以内 | 死亡届の提出・火葬許可申請 | すべて | 市区町村役場 |
| 火葬時 | 埋葬許可証の受領 | すべて | 火葬場 |
| 14日以内 | 世帯主変更届 | 故人が世帯主であり、残った世帯が2人以上の場合 | 市区町村役場 |
| 健康保険・介護保険の資格喪失届出 | すべて | 保険証に記載の保険者など | |
| 葬儀後すみやかに | 電気・ガス・水道・NHKの契約変更または解約 | すべて | 電気・ガス・水道の契約先 |
| 年金の受給停止手続き | 故人が年金を受け取っていた場合 | 年金事務所など | |
| クレジットカードの解約 | 必要に応じて | クレジットカード会社 | |
| 運転免許証の返納 | 運転免許証を持っていた場合 | 警察署 | |
| パスポートの返納 | パスポートを持っていた場合 | パスポートセンター | |
| 遺言書の調査 | 必要に応じて | 自宅・法務局・公証役場など | |
| 遺言書の検認 | 検認が必要な遺言書があった場合 | 家庭裁判所 | |
| 相続人の調査 | 必要に応じて | 市区町村役場など | |
| 相続財産の調査 | 必要に応じて | 自宅など | |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄 | 必要に応じて | 家庭裁判所 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 | 必要に応じて | 税務署 |
| 落ち着いたら | 遺産分割協議 | 必要に応じて | - |
| 10ヶ月以内 | 相続税申告 | 必要に応じて | 税務署 |
| 早めに | 死亡保険金の請求 | 必要に応じて | 保険会社 |
| 銀行・証券口座の解約・名義変更 | 必要に応じて | 銀行・証券会社 | |
| 車の名義変更 | 必要に応じて | 陸運支局など | |
| 不動産の名義変更(相続登記)
※改正法施行後の期限は3年以内 |
必要に応じて | 法務局 | |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 必要に応じて | 請求の相手方 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬費の請求 | 必要に応じて | 市区町村役場または健康保険組合 |
| 高額療養費の請求 | 必要に応じて | 市区町村役場または健康保険組合 | |
| 死亡一時金の請求 | 必要に応じて | 市区町村役場または年金事務所 | |
| 5年以内 | 未支給年金の請求 | 未支給年金がある場合 | 市区町村役場または年金事務所 |
| 遺族年金の請求 | 必要に応じて | 市区町村役場または年金事務所 |
なお、最近では市区町村役場に「おくやみ窓口」などを設け、役所内で行うべき手続きがワンストップで完了するケースも増えてきました。
何から手を付けたら良いのかわからないという場合には、まずは亡くなった方がお住まいだった市区町村役場に電話をしてから出向くと良いでしょう。これにより初期段階で行うべき手続きをある程度まとめて済ませることができ、少しすっきりするのではないかと思います。
また、期限のある手続きも、期限より早めに行う分には問題ありません。相続税申告など一部の手続きは、準備に相当な時間がかかります。そのため、期限ぎりぎりになってから取り掛かるのではなく、できるだけ早くから準備を進めておくと良いでしょう。
相続発生後のやるべき手続きと一般的な流れ
相続発生後にやるべき手続きの大まかな流れは、次のようになります。
なお、これはあくまでも一般的なケースの一例です。状況によっては順番が前後したり一部の手続きが不要になったりする場合もありますので、全体の流れをつかむイメージとしてご参照ください。
- 役所関係の手続きを済ませる
- 遺産の全体像を把握して財産目録を作成する
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人を確定する
- 遺産分割協議を行う
- 各財産の名義変更や解約を行う
- 相続税申告を行う
役所関係の手続きを済ませる
相続が起きたら、まずは役所関係の手続きを済ませましょう。
役所関係の手続きには、相続開始後7日以内や14日以内に行うべきものなど期限の決まっているものもいくつか存在します。まずは死亡届の提出などで身内が亡くなったらすぐに一度出向き、その後葬儀を終えた後で再度出向くと、効率良く手続きを終えやすいでしょう。
遺産の全体像を把握して財産目録を作成する
役所関係の手続きがひと段落したら、亡くなった人(「被相続人」といいます)の持っていた財産をまとめた財産目録を作成します。財産の状況がまとまっていないと、後に解説する遺産分割協議を行いづらいためです。
また、相続税申告が必要かどうかを大まかに判断する効果や、名義変更など相続手続きの漏れを防ぐ効果も期待できます。
遺言書の有無を確認する
財産目録の作成と同時進行で、被相続人の遺言書を探しましょう。遺言書の主な探し方は、遺言書の種類によって次のとおりです。
- 公正証書遺言:公証役場で検索をしてもらう
- 法務局での保管制度を使った自筆証書遺言:法務局で検索をしてもらう
- 法務局での保管制度を使っていない自筆証書遺言:被相続人の自宅などを捜索する
いずれの場合であっても、自宅の何らかの痕跡が残っている場合が少なくありませんので、まずは自宅を探すことから始めるとよいでしょう。
相続人を確定する
財産目録の作成や遺言書の捜索と同時進行で、相続人の確定を進めます。相続人が配偶者と子などシンプルな場合には、比較的容易に確定できるでしょう。
一方で、被相続人に前妻との子など長年会っていない子がいる場合や、兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合には、相続人の確定だけでも大変な作業となります。相続人を確定するには、被相続人の出生までさかのぼる戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本などの書類が必要です。
これらの書類は、不動産や預貯金など各財産の名義変更や解約の際にも必要となりますので、この段階で集めておくと良いでしょう。自分で取り寄せることが難しい場合には、当社が提供する「そうぞくドットコム不動産」など、代行取得のサポートをご利用ください。
遺産分割協議を行う
財産の全体像が分かり、かつ相続人が確定できたら、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いのことです。遺産分割協議が成立したら、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書は、後で行う各財産の名義変更や解約手続きに使用します。そのため、誰がどの財産を相続することとなったのか、誰がどう見てもわかるように明確に作成してください。
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要となります。一人でも納得しない相続人がいる場合には、遺産分割協議を成立させることはできません。
当人同士で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での話し合いである「調停」や、裁判所が決断をくだす「審判」へと移行します。なお、すべての財産について承継者の指定された有効な遺言書がある場合には、遺産分割協議は不要です。
各財産の名義変更や解約を行う
遺産分割協議が無事に成立したら、不動産や預貯金など被相続人が持っていた各財産の解約や名義変更手続きを行います。各財産の手続きについては、後ほど詳しく解説します。
相続税申告を行う
その相続に対して相続税がかかる場合には、相続税の申告を行います。相続税には基礎控除額が設けられており、遺産総額や被相続人が行った過去の一定の贈与金額の合計額が次の式で算定される基礎控除額以下であれば課税されません。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の申告と納税には期限があります。相続税の対象となりそうな場合には、早めから税理士などの専門家へ相談しておきましょう。
相続発生後の手続きと期限
相続手続きの中には、期限があるものがいくつか存在します。期限のある手続きや、手続きの順序は次のとおりです。
相続発生後すぐ
相続発生後すぐに行うべき手続きは、次のとおりです。
- 死亡診断書の取得:死亡を確認した病院から発行されます。多めにコピーを取っておきましょう。
- 死亡届の提出:原則として死亡後7日以内に行う必要があります。ただし、死亡届を出さなければ火葬の許可がおりませんので、通常は死亡当日か翌日あたりには行うことが多いでしょう。
- 死体埋葬火葬許可証の取得:死亡届を提出することで発行を受けられます。
相続発生後14日以内
相続発生後10日から14日以内に行う手続きは、次のとおりです。
- 年金受給権者死亡届の提出:年金を止めるための手続きです。
- 国民健康保険証や健康保険証、介護保険証の返却:手続き先は、市区町村役場など被相続人が加入していた健康保険の種類によって異なります。
- 世帯主の変更届:新たな世帯主を決める届出です。亡くなった人が住民票の世帯主であり、かつ残った世帯員が2名以上いる場合に必要となります。
葬儀後速やかに
次の手続きには、特に期限はありません。ただし、後の手続きをスムーズに進めるためには、このあたりで行っておくべき手続きです。
- 遺言書の調査:被相続人の遺言書を捜索します。
- 遺言書の検認:家庭裁判所で行います。遺言書があり、かつ遺言書が法務局での保管制度を利用していない自筆証書遺言などであった場合に必要となります。
- 相続人の調査:被相続人の除籍謄本などを取得し、相続人を確定します。
- 財産調査:被相続人の遺産を調査し、財産目録にまとめます。
相続発生後3ヶ月以内
相続開始後3ヶ月以内に行うべき手続きは、次のとおりです。
- 相続放棄:被相続人に借金が多く、相続してしまっては困る場合に家庭裁判所で行う手続きです。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったこととなるため、マイナスの財産もプラスの財産も一切相続できなくなります
なお、相続放棄の他に、プラス財産の限度でのみマイナス財産を相続する「限定承認」も存在します。こちらも、期限は相続放棄と同じく3ヶ月以内です。
相続発生後4ヶ月以内
相続発生後4ヶ月以内に行うべき手続きは、次のとおりです。
- 準確定申告:亡くなった人の確定申告です。
被相続人に事業所得や不動産所得があり毎年確定申告をして納税をしていた場合には、原則として準確定申告が必要になると考えてください。
また、それ以外でも、亡くなった年や確定申告を終えていない亡くなる前年に不動産などの資産を譲渡していた場合にも、準確定申告が必要となる場合があります。準確定申告が必要かどうか不明な場合には、税理士または管轄の税務署へ相談しましょう。
相続発生後10ヶ月以内
相続発生後10ヶ月以内に行うべき手続きは、次のとおりです。
- 相続税申告:遺産などに対してかかる相続税の申告です。
ただし、相続税には、上で解説をしたとおり基礎控除額が設けられています。
課税対象となる課税価格の合計額が、「小規模宅地等の特例」などを使うことなく相続税の基礎控除額以下におさまるのであれば、申告は必要ありません。申告が必要である場合はもちろん、相続税の申告が必要かどうか迷う場合にも、早期に税理士などの専門家へ相談しましょう。
相続発生後1年以内
相続発生後1年以内に行う手続きは、次のとおりです。
- 遺留分侵害額請求:遺言などで財産を多く受け取った人に対して、侵害された遺留分を請求する手続きです。
被相続人の配偶者や子など一定の相続人には、遺留分があります。この遺留分を侵害した内容の遺言書も有効ですが、遺留分を侵害された相続人は遺留分を侵害した相手に対して、遺留分侵害額請求をすることが可能です。
この遺留分侵害額請求の期限は、相続開始と遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内です。ただし、相続が起きたことをなど知らないままであっても、相続開始から10年が経過したときは時効によって権利が消滅します。
相続発生後2年以内
相続発生後2年以内に行うべき手続きは、次のとおりです。
- 埋葬料・葬祭費の請求:健康保険などから支給される埋葬料や葬祭費を受け取るための手続きです。
被相続人が国民健康保険の被保険者やその扶養家族であった場合には葬祭費が、健康保険や協会けんぽに加入していた場合は埋葬料が受け取れる可能性があります。埋葬料や葬祭費は2年で時効にかかりますので、忘れないように請求しておきましょう。
相続発生後5年以内
相続開始後、5年以内に行うべき手続きは次のとおりです。
- 遺族年金の受給申請:遺族が遺族年金を受け取るための手続きです。
遺族年金とは、亡くなった人に生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。遺族年金の受給には要件がありますので、受給権があるかどうかわからない場合には、住所地の市区町村役場またはお近くの年金事務所で相談をしましょう。
遺族年金の受給権は5年で時効にかかりますので、早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。
相続が必要となる手続きの種類
相続財産は、預貯金や不動産など多岐にわたります。ほとんどの財産において名義変更などの手続きが必要になりますが、代表的な物としては以下のようなものが挙げられます。
- 預貯金
- 不動産
- 株式
- 自動車
本稿では、これら4つの手続きについて詳しく解説します。
名義変更の期限と必要性
実は、相続財産の名義変更には期限がありません。相続した人がいつでも自由に行ってよいことになっています。
ただし、名義変更が行われるまでの相続財産は、相続人全員の共有財産となっています。ですから、預貯金は預金仮払い制度の適用を受ける場合以外は原則として引き出せず、財産を勝手に売却することもできません。
不動産は名義変更をしなくても利用し続けることができてしまいますが、そのまま放っておいて、仮に相続人が亡くなってしまった場合、次の相続人は、名義人をさかのぼって調査しなければならないなど、余計な手間をかけさせてしまうことになります。
権利や義務関係を明確にするためにも、自分の子孫に迷惑をかけないためにも、できるだけ早めに手続きをしておくことをおすすめします。
預貯金に関する相続発生後の手続き
相続の手続きをできるだけ早く行いたいのが預貯金です。
被相続人の死亡を銀行に伝えると、その時点で被相続人の口座は凍結されます。相続の手続きをするまでは、原則、葬儀費用や相続税のために引き出すこともできません。
また、被相続人が複数の金融機関に口座を持っていた場合は、それぞれで手続きをしなければならず、時間がかかります。だからこそ、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。
預貯金の相続手続きは、被相続人の口座を解約して、相続人の口座に振り込む形で行います。
必要書類
必要な書類は概ね以下の通りです。金融機関によって必要書類が異なるので、まずは被相続人の口座があった金融機関に問い合わせましょう。
- 預金名義書換依頼書や相続届(銀行が用意している書式)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳、キャッシュカード、証書など
- 遺産分割協議書(または相続人全員の同意書)や遺言書
多くの場合、預金名義書換依頼書や相続届には相続人全員の署名と捺印が必要です。
手続きの流れ
預貯金の相続手続きの流れは以下のようになっています。こちらも金融機関によって異なるので、詳しくは問い合わせましょう。また、前述の通り、被相続人が複数の金融機関に口座を持っていた場合はそれぞれで手続きをしなければなりません。
- 金融機関に電話をし、被相続人の死亡を伝える
- 口座が凍結され、数日後に預金名義書換依頼書や相続届が郵送されてくる
- 必要書類をそろえ、店頭窓口か郵送で金融機関に提出する
- 1~2週間後に手続きが完了する
不動産に関する相続発生後の手続き
不動産に関する手続きは、相続の中でも複雑になりがちだと言われています。理由は大きく2つあります。
まず、そもそも誰の名義になっているかわかりにくいという点が挙げられます。預貯金などと違い、不動産は名義変更をしなくても使い続けることができます。
また、名義変更には期限がありません。そのため、相続時に名義変更が行われず、被相続人どころかその先代の名義のままだったということもあり得るのです。この場合、先代の戸籍から確認していかなければならず、手続きは煩雑になります。
相続財産が不動産だけというケースでは、不動産を売却するなどして遺産分割を行うことがあります。名義変更だけでなく売却の手続きも必要になるので、時間や手間がかかります。場合によっては、専門家に依頼することも検討しましょう。
不動産の名義変更(相続登記)
必要なもの
相続に伴う不動産の名義変更を相続登記といいます。相続登記に必要なものは以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
- 被相続人の住民票の除票、もしくは戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 新しく名義人となる人の住民票
- 遺言書とその検認調書(公正証書遺言以外の場合)、もしくは遺産分割協議書
- 固定資産評価証明書(不動産のある市区町村の役場で取得)
- 登記申請書
- 登録免許税
登記申請書は、法務局で取得できるほか、法務省のホームページでもダウンロードできます。書式は遺言書の種類や相続方法によって変わるので注意しましょう。
また、登記には登録免許税がかかります。税額は
「固定資産評価額×0.4%」
で算出します。
手続きの流れ
不動産の名義変更は法務局で行います。大まかな流れは次のようになっています。
- 法務局で不動産全部事項証明書を取得し、名義人を確認する
- 登記申請書など必要書類をそろえる
- 必要書類を法務局に持参、もしくは郵送して提出する
- 1~2週間で手続きが完了し、登記識別情報通知が発行される
登記識別情報通知には、数字とアルファベットを組み合わせた12文字のパスワードのようなものが記されています。この識別番号を知っていることが不動産の権利者の証となるので、第三者に知られないように厳重に保管しましょう。
不動産の売却(換価分割)
相続財産に不動産がある場合、売却という選択肢も出てきます。相続人の誰かが不動産を相続した場合には、名義変更を行えば自由に売却できます。
一方、相続人が複数いて相続財産が不動産しかないようなケースでは、不動産を売却して現金に換え、それを改めて分割するという換価分割という方法が取られることがあります。換価分割の場合でも、相続登記をしなければ不動産の売却はできません。
方法としては、次の2つが考えられます。
- 相続人の代表者を名義人とし、相続登記を行う
- 相続人全員を名義人とし、相続登記を行う
相続人の代表者を名義人とする
メリットは、相続登記や売却を代表者1人で行えることです。一方、次のようなデメリットがあります。
- 不動産を売却して利益が出たとき、代表者1人に所得税が課税される場合がある
- 換価分割のために他の相続人に現金をわたしたときに贈与とみなされ、贈与税が課せられることがある
こうしたデメリットを被らないためには、遺産分割協議書を作成し、換価分割をすることを明記しておく必要があります。
相続人全員を名義人とする
余計な所得税や贈与税が発生する恐れはありませんが、売却のときには名義人全員の同意やそれを示す書類が必要になり、手続きが煩雑になる恐れがあります。
専門家に依頼する場合は司法書士に
不動産に関する手続きは、一応、相続人だけでもできるということになっています。しかし、必要書類の多さや手続きの複雑さもあり、素人が行うのは簡単ではありません。かかる手間や時間を考えると、専門家に依頼した方がいいことも多いでしょう。
専門家に依頼する場合に注意したいのが、登記ができるのは司法書士だけということです。これは法律で定められており、弁護士や税理士は登記手続きができません。相続財産に不動産がある場合は、司法書士に依頼しましょう。
株式に関する相続発生後の手続き
被相続人の死後、相続手続きが完了するまでは、株式の売却などは行えません。手続きの方法は、上場株式と非上場株式で異なります。
上場株式の相続
必要なもの
- 株券名義書換依頼書(証券会社が用意している書式)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書とその検認調書(公正証書遺言以外の場合)、もしくは遺産分割協議書
- 被相続人が利用していた証券会社の証券口座
現在、上場株券はすべて電子化されています。したがって、株式を相続するには、被相続人が取引をしていた証券会社に、相続人も口座を持っている必要があります。口座がなければ新しく開設しましょう。
手続きの流れ
上場株式の相続手続きは預貯金のものとよく似ています。証券会社によって多少の違いはありますが、大きな流れは以下の通りです。
- 証券会社に電話をし、被相続人の死亡を伝える
- 数日後、株券名義書換依頼書が郵送されてくる
- 必要書類をそろえ、店舗窓口や郵送で証券会社に提出する
- 1~2週間で手続きが完了する
非上場株式の相続
非上場株式の場合、株式を発行している会社に直接連絡し、株主名簿の書換を依頼することになります。必要な書類や手続きについては各会社に問い合わせましょう。
自動車に関する相続発生後の手続き
自動車の名義変更、すなわち名義の移転登録は、被相続人の死後15日以内と定められています。ただし、15日以内に相続する人が決まることはほとんどないので、これを過ぎても罰則はありません。ただし、いつまでも手続きをしなくていいというわけではありません。
名義変更をしていない自動車は相続人の共有財産となりますから、自動車税などの納税義務は相続人全員が連帯負うことになります。さらに、相続人の誰かがこの自動車で事故を起こした場合、事故とは無関係の相続人も責任を負うことがあります。
売却や廃車手続きをする場合も名義変更は必要になるので、できるだけ早く手続きしましょう。また、ローンが残っている場合、相続人が負債として引き継ぐことになる点には注意が必要です。
手続きの流れ
自動車の名義変更をするには、まず自動車検査証(車検証)で所有者を確認します。多くの場合は被相続人が所有者のはずですが、リース契約やローンの支払い中だと、保有者が販売店などになっていることがあります。
被相続人が所有者の場合
被相続人が所有者の場合、運輸支局で手続きを行います。必要な書類は概ね下記の通りです。
- 自動車検査証(車検証)
- 被相続人と相続人全員の戸籍謄本、もしくは戸籍全部事項証明書
- 遺産分割協議書
- 新しい名義人の印鑑証明書
- 新しい名義人の実印
- 車庫証明書
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書
- 500円分の登録印紙(手数料納付書に貼りつけ)
手数料納付書以下の書類は運輸支局で取得できます。また、軽自動車の名義変更は、新しい名義人の住所地の軽自動車検査協会事務所で行います。手続きが簡略化されており、戸籍謄本や遺産分割協議書などが不要になります。
被相続人以外(販売店など)が所有者の場合
リースやローンの場合、所有者が販売店や信販会社になっていることがあります。この場合は所有者に連絡して被相続人の死亡を伝え、手続き方法を確認します。
その他の相続発生後の手続き
その他、相続に伴って名義変更などの手続きが必要になるものとしては、以下のようなものがあります。
- 相続財産
- 手続き先
- 火災保険や損害保険など
- 各保険会社
- ゴルフ会員権やリゾート会員権
- 各管理会社
- 百貨店会員権
- 百貨店
- 電話加入権
- NTT
- 工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)
- 特許庁
まとめ
相続財産は多岐にわたり、名義変更だけでも時間と労力がかかります。名義変更には期限がありませんから、相続財産の種類が多い場合には、優先順位を決めて一つひとつ手続きを行っていきましょう。
また、手続きの時間が取れない、手続きが膨大になるといった場合は、司法書士をはじめとする専門家に依頼するのもひとつの方法です。
当社AGE technologiesが提供するそうぞくドットコム不動産は、相続で発生した自宅や土地などの不動産の名義変更手続きを、Webを使って効率化するサービスです。