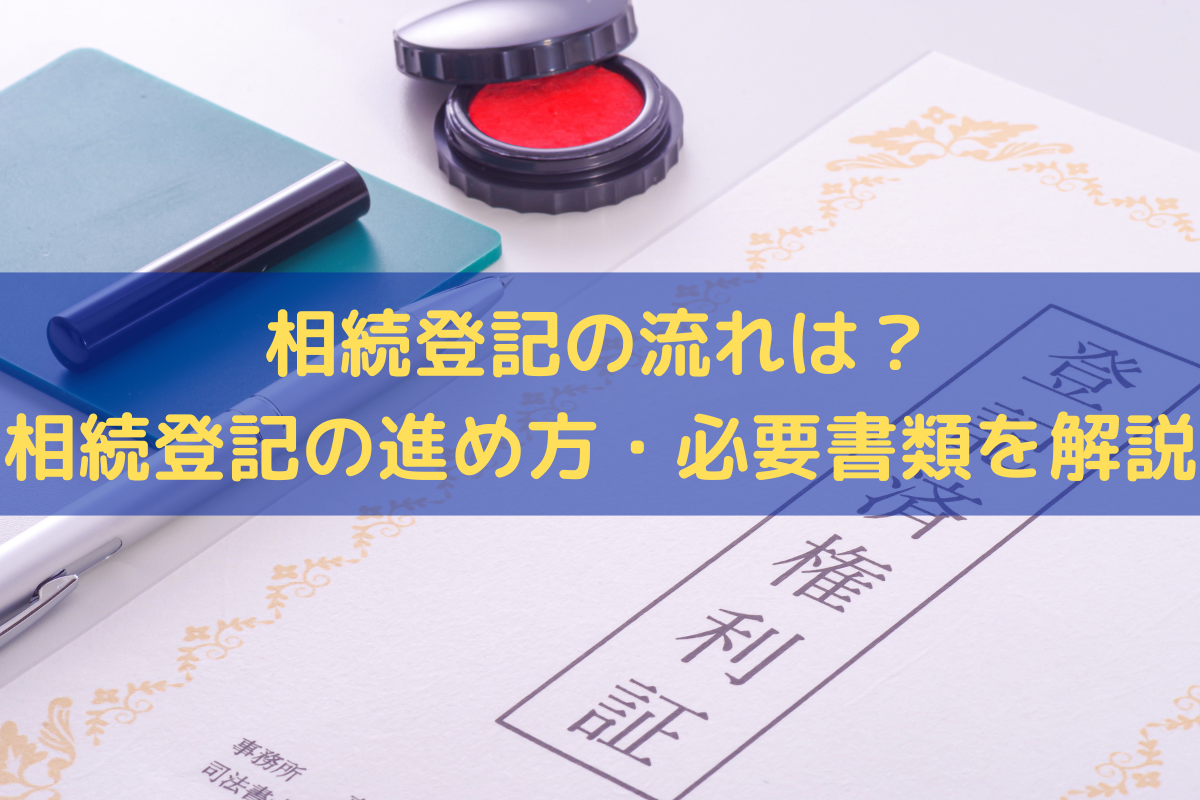不動産を持っている人が亡くなると、相続登記が必要となります。
相続登記とは、不動産の名義人を、故人から相続人などの名義へと変える手続きです。しかし、何から手を付けたら良いのかわからないという場合も少なくありません。
そこで今回は、相続登記の流れや必要書類などについてくわしく解説します。
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の名義となっている不動産を、相続人などの名義へと変更する手続きです。
不動産の所有者の氏名と住所は、法務局に登録(登記)されています。しかし、不動産の名義人として登記簿に記載されている人が亡くなったからといって、相続人などの名義へと勝手に書き換わるわけではありません。法務局は名義人が亡くなったことや、協議などの結果誰がその不動産を取得することになったのかなど、知る由がないためです。
そのため、不動産の所有者であった被相続人が亡くなったのであれば、すみやかに相続登記をする必要があります。相続登記をしなければ、いつまで経っても不動産が故人名義のままとなってしまい、さまざまな不都合が生じる可能性があるためです。
相続開始から相続登記をするまでの流れ
相続が起きてから、相続登記をするまでの流れは、どのような流れになるのでしょうか?それぞれのステップと全体の流れは、次のとおりです。
- ステップ1:遺言書の有無を確認する
- ステップ2:相続人を確認する
- ステップ3:遺産の全容を確認する
- ステップ4:遺産分割協議を行う
- ステップ5:必要書類を準備する
- ステップ6:登記申請をする
ステップ1:遺言書の有無を確認する
はじめに、被相続人が遺言書を遺していたかどうかを確認しましょう。遺言書の有無によって、その後の手続きが大きく異なるためです。
遺言書の主な探し方は、次のとおりです。
- 自宅内などを探す
- 生前に関与していた専門家に問い合わせる
- (公正証書遺言の場合)最寄りの公証役場で確認する
- (法務局での保管制度を活用していた場合)最寄りの法務局で確認する
このうち「③」と「④」の場合には所定の書類が必要となるため、あらかじめ公証役場や法務局で手続き方法を確認のうえ、書類を揃えて出向きましょう。
また、発見をした遺言書が法務局での保管制度を利用していない「自筆証書遺言」などであった場合には、手続きに使用する前に「検認」を受けなければなりません。検認とは遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きで、家庭裁判所で行います。
なお、この先のステップは、遺言書がなかった場合を前提として解説します。
ステップ2:相続人を確認する
次に、被相続人の相続人を確認しましょう。具体的には、後ほど解説する「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」や「相続人全員の戸籍謄本」などを取り寄せて確認します。
たとえば、父が亡くなり母と子どものみが相続人となる場合などでは、相続人が誰であるのか調べるまでもないケースが多いかもしれません。しかし、いずれにせよ相続登記に際して必要となる書類であるため、この段階で集めて確認しておくと良いでしょう。
ステップ3:遺産の全容を確認する
ステップ2と並行して、遺産の全容を確認します。どの遺産がどの程度あったのかがわからなければ、次のステップとなる遺産分割協議を行うことが難しいためです。
遺産の把握に必要なものは状況によって異なりますが、たとえば次のものなどが参考になるでしょう。
- 不動産:固定資産税の納付書に同封されている固定資産税課税明細書、法務局から取り寄せる不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)など
- 預貯金:通帳、銀行から取り寄せる残高証明書など
- 有価証券:証券会社から送られてくる取引明細書、証券会社から取り寄せる残高証明書など
- 車:車検証など
なお、生命保険は受取人の固有財産であるため、遺産分割協議を経るまでもなく、契約で指定された受取人のものです。ただし、手続きが漏れないように、この段階で把握しておくと良いでしょう。
ステップ4:遺産分割協議を行う
遺産の全容が把握できたら、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議を成立させるには、相続人全員が参加し、全員が協議内容に合意することが必要です。
なお、仮に相続人の中に重い認知症の人や行方不明の人がいる場合でも、この人たちを無視して協議を成立させることはできません。この場合には、遺産分割協議に先立って、これらの人の代わりに協議に参加する「成年後見人」や「不在者財産管理人」を選任してもらう手続きが必要となります。
また、仮に相続人同士で意見が対立するなどして協議がまとまらない場合には、「調停」や「審判」へと移行します。
調停とは、調停委員立ち合いのもと、家庭裁判所で行う話し合いです。一方、審判とは、裁判所が遺産分割の内容について決断をくだす手続きです。
ステップ5:必要書類を準備する
遺産分割協議が無事にまとまったら、相続登記に必要となる書類を準備します。必要書類については、後ほどくわしく解説します。
ステップ6:登記申請をする
必要書類が揃ったら、管轄の法務局へ、相続登記を申請しましょう。申請先の法務局については、法務局のホームページで確認できます。
相続登記の申請方法には、次の3つが存在します。
- 管轄の法務局の窓口へ持ち込んでの申請
- 郵送申請
- オンライン申請
このうち、オンライン申請は機器の準備などが必要であるため、自分の登記を数回行う程度であれば、おすすめできません。
管轄の法務局が近い場合には「①」を選択し、遠方の場合や開庁時間内に出向くことが難しい場合には「②」の方法を選択すると良いでしょう。
相続登記に必要な書類
相続登記には、さまざまな書類が必要となります。遺産分割協議書で相続登記をする場合における基本の必要書類は、次のとおりです。
ただし、状況によってはこれら以外の書類が必要になることもあるため、自分で相続登記を申請する際には、申請前に法務局の登記相談などで確認しておくと良いでしょう。なお、登記相談は予約制となっている場合がありますので、突然出向くのではなく、あらかじめ法務局に電話などで確認してから出向くことをおすすめします。
- 登記申請書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 被相続人の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 相続関係説明図
- 固定資産税評価証明書または評価通知書
登記申請書
登記申請書は、相続登記のメインとなる書類です。原則としてここに記載したとおりに登記がされるため、誤りのないよう、全部事項証明書などを見ながら正確に作成してください。
登記申請書の記載例は法務局のホームページに載っているので、こちらが参考となるでしょう。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果を記した書類です。相続登記をしようとする不動産を誰が取得することになったのかが分かるよう、明確に記載しましょう。表記があいまいであると、登記ができない可能性があります。
遺産分割協議書には、相続人全員が協議内容に合意していることの証明として、相続人全員の実印による捺印と署名が必要です。
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押した印が実印であることの証明として、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書を代理で取得するには印鑑カードやマイナンバーカードを預かる必要がありますので、よほど気心の知れた同居家族以外については、それぞれ自分で取得してもらうことが多いでしょう。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
被相続人の相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。それぞれ、その時点で本籍地を置いていた市区町村役場で取得します。
なお、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合には、これに加えて、被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も取得しなければなりません。
被相続人の除票
被相続人が不動産の名義人と同一人物であることを確認するため、被相続人の除票が必要です。除票とは最後の住所地を証する書類であり、最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。
相続人全員の戸籍謄本
相続人が存命であることを確認するため、相続人全員の戸籍謄本が必要です。それぞれ、本籍地の市区町村役場で取得します。
不動産を取得する相続人の住民票
新たな所有者の情報を正しく登記するため、不動産を取得する相続人の住民票が必要です。住民票は、住所地の市区町村役場で取得できます。
相続関係説明図
相続関係説明図は、相続登記の必須書類ではありません。しかし、相続関係説明図を添付することで戸籍謄本や除籍謄本などの原本の返還が受けられるため、添付した方が良いでしょう。
相続関係説明図とは、相続関係を簡略化して示した図です。家系図のうち、相続に関連する部分のみを抜き出したものであるとイメージすると良いでしょう。
相続関係説明図の記載例も法務局のホームページに載っていますので、こちらが参考になります。
固定資産税評価証明書または評価通知書
相続登記に際しては、後ほど解説をするとおり、登録免許税を納めなければなりません。
登録免許税は、固定資産税評価額をベースに算定します。そのため、不動産の固定資産税評価額を証するものとして、「固定資産税評価証明書」または「評価通知書」が必要です。
固定資産税評価証明書や評価通知書は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得できます。
相続登記の必要書類を郵送で取り寄せる流れ
相続登記の必要書類の中に、遠方の市区町村役場から取り寄せるべき書類が含まれている場合もあるでしょう。たとえば、被相続人の過去の除籍謄本などは、遠方にあることも少なくありません。
そのような場合には、わざわざその市区町村役場まで出向かずとも、郵送で書類を取り寄せることができます。市区町村役場から郵送で書類を取り寄せるまでの基本的な流れは、次のとおりです。
市区町村のホームページから請求用紙をダウンロードして印刷する
はじめに、書類の請求先である市区町村役場のホームページから書類の請求用紙を見つけ、印刷しましょう。最近では、ほぼすべての市区町村のホームページに、書類の請求用紙が掲載されています。
必要事項を記載する
請求用紙の準備ができたら、必要事項を記載します。市区町村のホームページに記載方法が掲載されていることが多いため、こちらを確認しながら慎重に作成しましょう。
請求用紙の記載に当たって不明な点があれば、役所の担当課に電話で問い合わせることで、回答をもらうことが可能です。
ただし、「亡くなった父の本籍が分からないけど、どこかな?」のような、個人情報に関わる質問に電話などで答えてもらうことはできません。個人の情報に不明な点があれば、先に他の書類を取得し、確認したうえで請求することが必要となります。
たとえば、亡くなった父の最後の本籍地が分からない場合には、本籍地入りの除票を先に取得することで、本籍を知ることができるでしょう。
運転免許証などのコピーを用意する
相続登記に必要な書類を郵送で取り寄せる際には、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど、本人確認書類のコピーの同封が必要です。そのため、本人確認書類のコピーを用意しましょう。運転免許証の裏面に変更事項の記載がある場合には、裏面のコピーも必要となります。
なお、戸籍謄本などの書類は重要な個人情報であるため、正当な権利者以外が請求することはできません。そのため、たとえば請求先の市区町村役場が持っている情報のみでは請求者が正当な権利者であるかどうかわからない場合などには、請求対象者と請求者との関係を示す他の証明書類が必要となる可能性があります。
特に、兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合にはこの証明が難しくなる傾向にあるため、あらかじめ必要書類を請求先となる担当課へ相談すると良いでしょう。
返信用封筒を準備する
必要書類を郵送で取り寄せる場合には、返信用封筒が必要です。そのため、返信用封筒を準備しましょう。
返信用封筒には、返送先となる自分の住所と氏名を、正確に記載します。なお、返送先は、同封した本人確認書類の住所氏名と同じであることが必要です。
返信用封筒には、切手の貼付が必要です。定型の普通郵便であれば84円切手となりますが、取得する書類の枚数が多い場合には重量オーバーとなる可能性があるため、不足が生じないよう多めに同封しておくと良いでしょう。
定額小為替を購入する
必要書類を郵送で取り寄せる場合、現金でお金を支払うわけにはいきません。現金書留以外の郵便で現金を送ることは違法ですので、絶対に行わないようにしましょう。
書類取得の手数料は、定額小為替で支払うことが一般的です。定額小為替とは郵便局で購入できる定額の為替であり、「300円」「450円」「750円」など、12種類の券種が存在します。請求先である市区町村役場のホームページなどであらかじめ必要な料金を確認し、お釣りのないよう準備しましょう。
なお、定額小為替の購入には、1通あたり200円の手数料がかかります。つまり、450円の定額小為替を1枚購入するためには、650円が必要であるということです。
宛名を書いて投函する
最後に、封筒に宛名を記載します。宛先には市区町村役場名のみならず、担当課名まで正確に記載しましょう。送付先は、市区町村役場のホームページに掲載されています。
ここまでで解説した次のすべての書類が揃っていることを確認のうえ、封をして投函します。
- 書類の請求用紙
- 本人確認書類のコピー
- 切手貼付済の返信用封筒
- 定額小為替
相続登記はいつまでに行うべき?
相続登記の申請は、いつまでに行うべきなのでしょうか?相続登記の期限は次のとおりです。
できるだけすみやかに行う
この記事を執筆している2023年2月現在、相続登記に期限はありません。ただし、相続登記を放置していていればその不動産の権利者が自分であることを第三者に主張できず、トラブルの原因となりかねません。
また、手続きを放置している間にもともと相続人であった人が亡くなるなどすれば、手続きのハードルがさらに高くなるリスクもあります。そのため、不動産の取得者が決まったら、できるだけすみやかに相続登記を済ませておくべきでしょう。
相続登記義務化の施行後は3年以内に行う
相続登記などについて定めている不動産登記法が改正され、2024年4月1日に施行されることが決まっています。この改正により相続登記は義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日(原則として、相続開始日)から、3年以内に相続登記をすべきこととされました。
また、この改正は施行日後に生じた相続のみならず、施行日より前に開始した相続についても対象となります。施行日前に開始した相続については期限が緩和されますが、施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
期限を過ぎたからといって相続登記ができなくなるわけではありませんが、正当な理由なく期限を超過した場合には、10万円以下の過料に処される可能性があります。
そのため、今後は相続登記の流れをより意識して、計画的に手続きを進める必要があるでしょう。
相続登記にかかる費用
相続登記を行うには、どの費用がどの程度かかるのでしょうか?主にかかる費用は、次のとおりです。
なお、このうち「司法書士報酬」は、司法書士へ手続きを依頼した場合にのみかかります。一方、「登録免許税」と「必要書類の取得費用」は、司法書士へ手続きを依頼した場合であっても自分で相続登記を行う場合であっても、同様にかかる費用です。
- 司法書士報酬
- 登録免許税
- 必要書類の取得費用
司法書士報酬
相続登記を司法書士へ依頼した場合には、司法書士報酬がかかります。
司法書士報酬は法令などで一律に決まっているわけではなく、個々の事務所がそれぞれ定めているものです。そのため、司法書士報酬を正確に知るためには、依頼を検討している先の事務所で、個別に見積もりを取る必要があるでしょう。
相続登記を司法書士へ依頼した場合の報酬の目安は、おおむね8万円から15万円ほどです。ただし、不動産の数が多い場合や不動産が法務局の管轄をまたいで点在している場合、相続人の数が多い場合などには、加算となる場合があります。
登録免許税
登録免許税とは、登記申請に際してかかる税金です。相続登記の場合の登録免許税は、原則として次の式で算定されます。
- 登録免許税額(相続)=不動産の固定資産税評価額×1,000分の4
※固定資産税評価額は1,000円未満切捨て
※登録免許税額は100円未満切捨て。ただし、計算結果が1,000円に満たない場合は1,000円
相続登記をする不動産の固定資産税評価額が2,000万円であれば登録免許税は8万円、固定資産税評価額が5,000万円であれば登録免許税は20万円ということです。評価額の高い不動産を登記する際には登録免許税も高額となりますので、あらかじめ金額を想定しておく必要があるでしょう。
必要書類の取得費用
上で紹介をしたとおり、相続登記にはさまざまな書類が必要となります。これらの書類を取得するためにかかる費用は相続の状況などによって異なりますが、おおむね5,000円から1万5,000円程度となることが多いでしょう。
ただし、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合には取得すべき書類が増える傾向にあるため、さらに1万円程度の費用がかかる可能性があります。
まとめ
相続登記を行う流れなどについて解説しました。相続登記を行う際には、全体の流れを意識して行うとスムーズでしょう。
しかし、相続登記には非常に多くの書類が必要となり、これらをすべて自分で集めることは容易ではありません。書類を収集する段階でつまずいてしまい、なかなか先へ進めないという場合もあるでしょう。そのため、面倒な書類の収集は、代行サービスを利用するのがおすすめです。