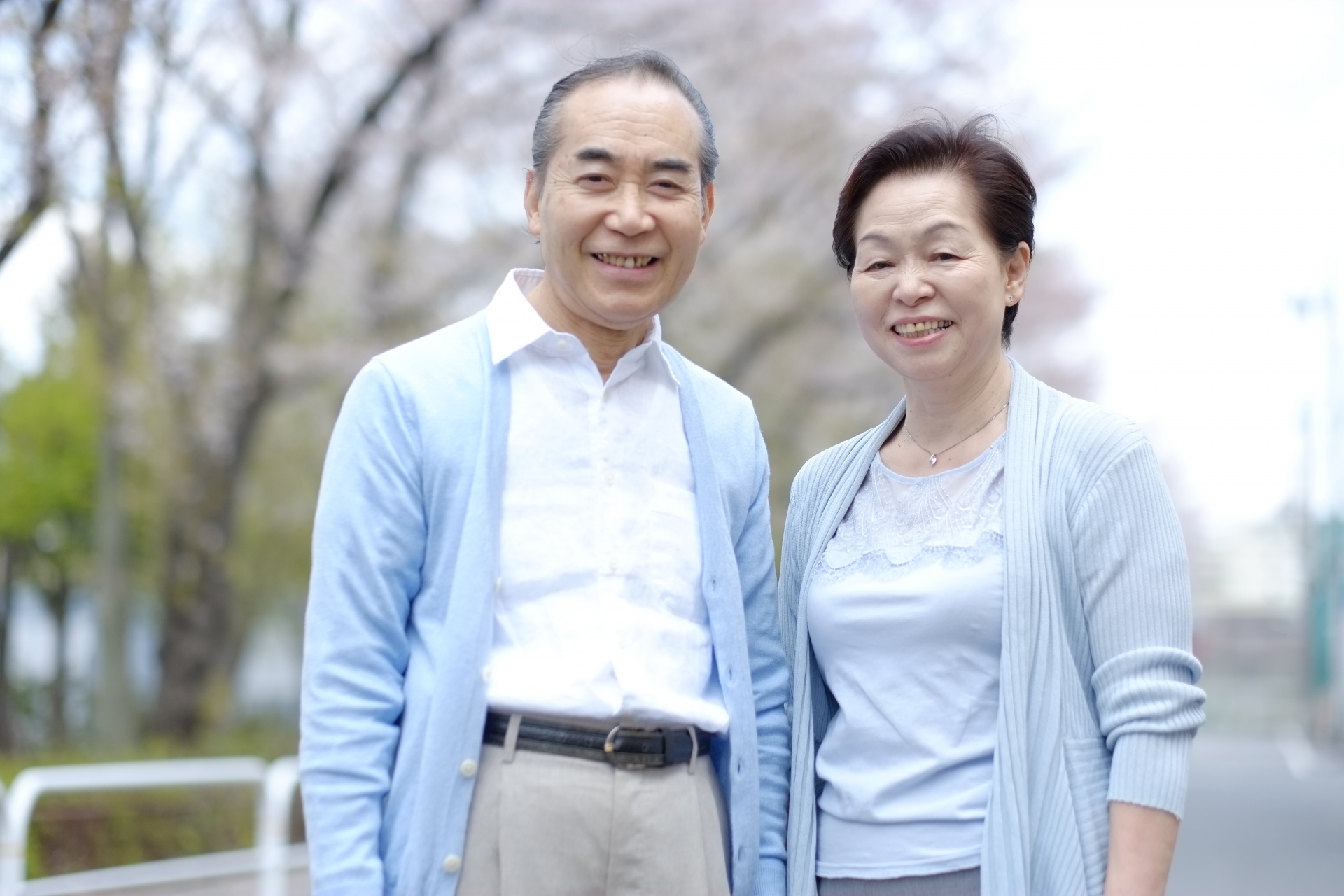相続税には、配偶者が相続や遺贈で受け取った財産のうち、1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きな額までに対する相続税が無税になる制度があります。
それでは、この制度を最大まで活用することが得策といえるのでしょうか?
今回は、相続税の配偶者控除の概要や、利用の際の注意点などについてくわしく解説します。
目次
相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除は、正式には「配偶者の税額の軽減」といいます。
この制度では、配偶者が受け取った遺産のうちかなり大きな額までの相続税が無税となるため、制度を活用することで相続税を大きく減額することが可能です。
まずは、相続税の配偶者控除の概要を解説します。
1億6,000万円か法定相続分まで無税になる
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、亡くなった方(「被相続人」といいます)の配偶者が相続や遺贈で受け取った財産のうち、次のうちいずれか大きな額までに対する相続税が無税になる制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
仮に遺産総額が1億6,000万円以下であれば、配偶者が全財産を相続してこの制度を適用することによって、相続税をゼロにすることが可能です。
また、配偶者が受け取った遺産がこれらの額を超える場合であっても、これらの金額までは相続税がかかりません。
相続税と配偶者控除の計算例

それでは、相続税の配偶者控除を適用した場合の相続税の計算について、具体的に例を出してみましょう。
ここでは、次の前提で計算していきます。
- 法定相続人:配偶者、長男、長女
- 遺産総額:2億円
- 実際に受け取った遺産の額:配偶者が1億円、長男が1億円、長女はゼロ
遺産総額から基礎控除額を控除する
はじめに、遺産総額から相続税の基礎控除額を控除します。
基礎控除額の計算式は、次のとおりです。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
この計算式で使うのは「法定相続人」の数です。
そのため、例でいう長女のように、実際には相続で財産を受け取らなかった人や、相続放棄をした人がいた場合、遺言などで相続人以外の人に財産を渡した場合などであっても、基礎控除額の計算に変動はありません。
これを例のケースに当てはめると、次のようになります。
- 相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×3名(配偶者、長男、長女)=4,800万円
相続税の基礎控除額が算定できたら、これを遺産総額から控除します。
- 2億円-4,800万円=1億5,200万円
この金額を、「課税遺産総額」といいます。
各法定相続人の法定相続分を計算する
課税遺産総額を法定相続人が法定相続分で取得したと仮定して、それぞれの取得金額を算定します。
ここでは、実際に誰がいくら財産を取得したのかは一切関係がありません。
あくまでも、法定相続分で取得したものとして仮で計算をする点に注意しましょう。
例のケースに当てはめると、次のとおりです。
- 配偶者:1億5,200万円×2分の1=7,600万円
- 長男:1億5,200万円×4分の1=3,800万円
- 長女:1億5,200万円×4分の1=3,800万円
相続税の総額を計算する
1つ前で計算した各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額をそれぞれ次に掲載した相続税の速算表に当てはめて、相続税額を計算します。
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参照元:国税庁ホームページ
例の場合には、次のようになります。
- 配偶者:7,600万円×30%-700万円=1,580万円
- 長男:3,800万円×20%-200万円=560万円
- 長女:3,800万円×20%-200万円=560万円
これらを合算して、相続税の総額を算定します。
- 1,580万円+560万円+560万円=2,700万円
相続税の総額を実際の取得金額で按分する
相続税の総額を実際の取得金額で按分して、相続税を誰がいくら納付すべきかを算定します。
例のケースでは、次のとおりです。
- 配偶者:2,700万円×1億円/2億円=1,350万円
- 長男:2,700万円×1億円/2億円=1,350万円
- 長女:2,700万円×0円/2億円=0万円
相続税の配偶者控除を適用する
最後に、相続税の配偶者控除や障害者控除、未成年者控除などの各種税額控除を適用します。
例のケースでは、相続税の配偶者控除のみが適用できるものとします。
計算式は、次のとおりです。
- 配偶者の実際の取得金額:1億円
- 相続税の配偶者控除の適用限度額:1億6,000万円>2億円×2分の1(配偶者の法定相続分)=1億円 ⇒ 1億6,000万円
- ①≦② ⇒ 全額が控除対象となる
そのため、各人の納付税額は、次のとおりです。
- 配偶者:1,350万円−1,350万円(相続税の配偶者控除)=0円
- 長男:1,350万円
- 長女:0万円
相続税の配偶者控除の適用条件
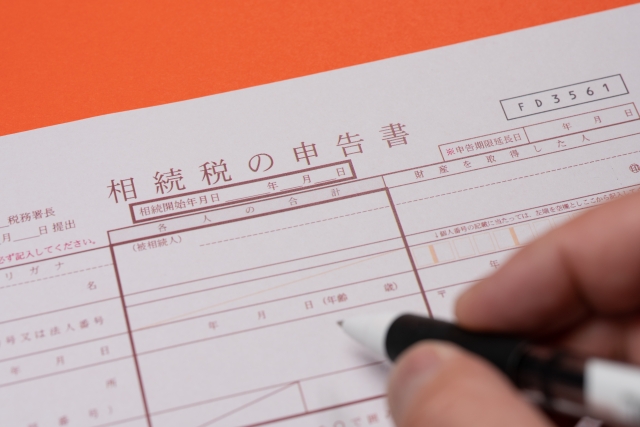
相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、一定の要件を満たさなければなりません。
その要件は、次の2点です。
- 婚姻関係にあること
- 期限までに遺産分割して相続税の申告をすること
婚姻関係にあること
相続税の配偶者控除の適用ができるのは、被相続人が亡くなった時点で籍の入っていた配偶者(夫または妻)のみです。
たとえ長年生活をともにしてきたとしても、籍が入っていない内縁の配偶者は、この制度の適用を受けることができないため注意しましょう。
また、子など配偶者以外の相続人も適用範囲外です。
期限までに遺産分割して相続税の申告をすること
相続税の配偶者控除の適用を受けるには、原則として相続税の申告期限内に遺産分割協議をまとめ、相続税の申告をする必要があります。
相続税の配偶者控除を適用した結果として相続税額がゼロになる場合であっても、特例の適用を受ける以上は申告をしなければならないため注意してください。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
仮にこの期限までに遺産分割協議がまとまらない場合であっても、申告期限が延長されるわけではありません。
期限までに遺産分割協議がまとまらなければ、期限内にいったん仮の申告を行い、その後協議がまとまった時点で申告をし直すこととなります。
ただし、配偶者の取得する遺産の金額が決まっていないのであれば、仮の申告の時点で相続税の配偶者控除の適用を受けることはできません。
この場合には、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したうえで期限までに仮の申告を行い、その後協議がまとまった時点で、相続税の配偶者控除についての適用の申告をすることとなります。
しかし、協議が難航して本来の申告期限からさらに3年が経過してしまうと、税務署の特別な承認がない限りもはや相続税の配偶者控除の適用は受けられなくなってしまいます。
特例の適用を検討している場合には、期限にも注意して遺産分割協議を行うようにしましょう。
相続税の配偶者控除は二次相続まで踏まえて検討しよう

相続税の配偶者控除は、相続税額にとても大きな影響を与える特例です。
そのため、その相続のことだけを考えるのであれば、配偶者にできるだけ多くの財産を相続させて相続税の配偶者控除を最大限活用することが最適解となるでしょう。
しかし、相続税の配偶者控除を安易に限度額いっぱいまで適用することはおすすめできません。
なぜなら、その後配偶者が亡くなった場合の二次相続のことまで考えると、相続税の配偶者控除を最大まで適用すると二次相続での相続税が高くなり、むしろ損になる可能性が高いためです。
そもそも、相続税の配偶者控除は、夫婦間での財産移転に対して無理に重い課税をしなくとも、その後子の世代に財産が移転する際に課税できれば良いとの考えがもととなっています。
では、くわしく解説していきましょう。
一次相続と比べた二次相続の特徴とは
一般的に、二次相続とは夫婦のうちどちらか後に亡くなる人の相続を指します。
仮に、夫が先に他界してその後妻が他界した場合には、夫の相続が「一次相続」、妻の相続が「二次相続」となります。
二次相続を一次相続と比べた場合、相続税の計算面で、主に次の特徴があります。
- 相続税の基礎控除額が減る
- 相続税の配偶者控除が使えない
相続税の基礎控除額が減る
相続税の基礎控除額とは、相続税のいわゆる非課税枠に相当するものです。
つまり、遺産総額が同じであればこの金額が大きければ大きいほど、相続税の額は安くなります。
相続税の基礎控除額は、上の計算過程の中でも紹介したとおり、次の式で算定します。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって異なり、法定相続人の数が少なければ少ないほど基礎控除額も安くなってしまいます。
通常、二次相続では法定相続人が1人少なくなっているケースが多いといえるでしょう。
たとえば、夫婦と2名の子がいる場合、一次相続で夫が亡くなった場合の法定相続人は妻と2名の子の計3名であり、相続税の基礎控除額は4,800万円となります。
一方、二次相続で妻が亡くなった場合の法定相続人は、すでに夫は他界しているため子2名のみとなり、相続税の基礎控除額は4,200万円です。
こうしたことから、二次相続では、相続税の基礎控除額が一次相続よりも少ない傾向にあるといえます。
相続税の配偶者控除が使えない
相続税の配偶者控除を使うことができるのは、被相続人の配偶者のみです。
一次相続で夫が亡くなった場合には、配偶者である妻が存在するため相続税の配偶者控除を使うことができます。
一方、二次相続で妻が亡くなった場合にはもはや配偶者が存在しないため、相続税の配偶者控除を使うことができません。
二次相続で税額が重くなったとしても、もはや相続税の配偶者控除ほど大きな減額が期待できる制度は存在しないため、税額を減らすことが困難となります。
相続税の配偶者控除を最大限使うことがベストな選択とは限らない
上記の理由から、仮に同じ額の遺産があった場合の相続税は、二次相続のほうが高くなりやすいといえます。
そのため、一次相続で相続税の配偶者控除を最大まで使いむやみに配偶者の財産を増やしてしまえば、一次相続の相続税がかなり安くなったとしても、二次相続での相続税が高額になってしまう可能性があるのです。
二次相続で高額な税金に驚いてしまわないためにも、あらかじめ二次相続の相続税まで試算をしたうえで、一次相続で配偶者が受け取る遺産の額を検討する必要があるでしょう。
特に、配偶者自身も財産を保有している場合には、二次相続での税金が高額になりやすいため注意が必要です。
なお、一次相続で配偶者に渡す金額がいくらであれば一次相続と二次相続で支払う相続税額の合計が安くなるのかについては、割合や金額に一律に明確な基準があるものではありません。
相続税が一次相続と二次相続とのトータルで最も安くなる一次相続での遺産配分を知るためには、相続人の状況のほか、配偶者自身の資産状況や配偶者の今後の収支予測などを踏まえて、個別でシミュレーションをする必要があります。
まとめ
相続税の配偶者控除は、適用を受けることで相続税を大きく減らすことができる特例です。
ただし、一次相続で安易に最大まで利用してしまうと、二次相続での相続税が高くなってしまう可能性があります。
相続税の配偶者控除を検討する際には、二次相続まで踏まえたシミュレーションをしておくと良いでしょう。
相続が起きた際に困ってしまう内容には、今回紹介した相続税についてのものの他、手続きについてのものも少なくありません。
中でも、故人名義の不動産を相続人などへと変える相続登記手続きには、戸籍謄本や除籍謄本、不動産の評価証明書など数多くの書類が必要となる他、登記申請書を一から作成する必要もあり、慣れていない方にとっては一苦労です。
そこで、そうぞくドットコムでは、相続登記に必要な戸籍謄本や除籍謄本、評価証明書などの取得を実費まで含んだ一律料金で代行している他、簡単な入力のみで登記申請書が作成できるサービスを提供しております。
相続での名義変更手続きでお困りの際には、ぜひそうぞくドットコムのサービスをご利用ください。