夫が再婚であり、前妻との間に子がいる場合、前妻の子は夫名義の家の遺産相続に関係するのでしょうか?また、その相続分は、どの程度なのでしょうか?
今回は、前妻の子の相続における権利や、前妻の子がいる場合における遺産相続の進め方などついて詳しく解説します。
目次
夫の持ち家の遺産相続は前妻の子にも関係する

結論からお伝えすると、夫名義である家の遺産相続において、前妻の子を無視して進めることはできません。なぜなら、離婚によって夫婦の関係は終了するものの、子との関係にまで影響するわけではないためです。
たとえ子の親権を元妻が取り、夫はかれこれ何十年も子と会っていない場合であったとしても、親子であることに変わりはありません。
そのため、仮に亡くなった夫に前妻との間の子がいるのであれば、その子も夫名義の家や他の財産について遺産相続する権利があります。つまり、遺言書などがない状態で夫が亡くなった場合、前妻との間の子も含めて遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)をしなければならないということです。
前妻の子の相続分はどのくらい?
前妻との間の子の法定相続分(遺産相続で主張することができる取り分の上限)は、後妻との間の子とまったく同じとされています。
たとえば、夫の相続人が現在の配偶者と、現在の配偶者との間の1名の子、そして前妻との間の1名の子の計3名である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
- 配偶者:2分の1
- 現在の配偶者との間の子:4分の1
- 前妻との間の子:4分の1
後妻の子であるか前妻の子であるかによって相続での取り分に違いがあるわけではありませんので、誤解の無いように注意しましょう。
なお、たとえば前妻が親権を取り、前妻の子とは何十年も会っていないなどの事情があったとしても、それだけで相続の権利がなくなったり相続の権利が減ったりすることはありません。
前妻の子がいる場合、相続後も夫の持ち家で暮らすことはできる?
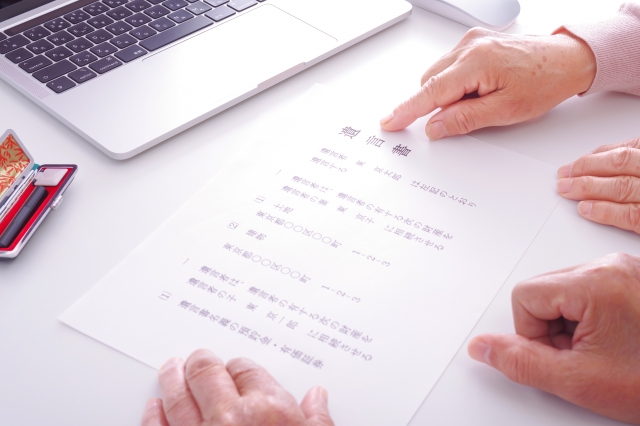
前妻の子がいる場合、夫の持ち家で夫の死後も暮らしたい場合には、どのような対策が検討できるのでしょうか?生前に検討したい主な対策としては、遺言書の作成が挙げられます。
遺言書の基本
後妻が夫亡きあとにも夫の持ち家で暮らすために検討したい方法は、夫が生前に遺言書を遺しておくことです。たとえば、遺言書の中で持ち家を妻(後妻)に相続させると指定しておくことで、原則として死後に持ち家を後妻に渡すことが可能となります。できます。
一般的に使用される遺言書の方式には、主に次の2つが存在します。
- 自筆証書遺言:自分で手書きをする遺言書
- 公正証書遺言:公証役場で作成する遺言書
このうち、自筆証書遺言は「本当に本人が書いたのか」などと争いの原因になってしまうリスクが存在します。そのため、より確実性を期すためには、公正証書遺言を作成しておくと良いでしょう。
ただし、遺言書を作成する際には、次の点に注意が必要です。
前妻の子がいる場合の遺言書作成時の注意点とポイント

前妻の子がいる場合、相続対策として遺言書を作成する場合には、次の点に注意をしましょう。これらを踏まえず、安易な内容で遺言書を作成してしまえば、トラブルの原因となる可能性があります。
- 遺留分に注意する
- 配偶者居住権の活用を検討する
遺言書は本人の意思で作成するものであることを理解する
夫が遺言書を作成する以上、その遺言書の内容を決めるのは夫自身です。
たとえ妻(後妻)として今後の生活のため夫の持ち家やその他の財産を相続したいと考えたとしても、夫が違う考えを持っていれば、無理に遺言書を書かせたり内容をコントロールしたりすることはできません。
ましてや、たとえば認知症を発症している夫の手を持って本人がよくわかっていないままに遺言書を書かせてしまうなどすれば、遺言書の偽造にあたり相続権が剥奪されてしまう可能性があります。
夫にとっては、前妻の子も自分の子であることには変わりありません。後妻として、無理に前妻の子の権利を減らそうなどとは考えないようにしましょう。
遺留分に注意する
遺言書を作成する際には、遺留分に注意をしなければなりません。では、順を追って解説していきましょう。
遺留分を侵害したらどうなるのか
遺留分とは、子や配偶者など一部の相続人に保証された、相続における最低限の取り分です。そして、前妻との子も被相続人の子である以上、遺留分の権利を持っています。では、遺留分と遺言書との関係はどのようになっているのでしょうか?
まず、先ほど解説したように、遺言書の内容は、原則として遺言を書く人の自由です。そのため、一部の相続人の遺留分を侵害したからといって、遺言書自体が無効になるわけではありません。
たとえば、仮に夫自身の意思でそのような内容で作成するのであれば、現在の配偶者に全財産を相続させるとの遺言書も有効です。しかし、遺留分を侵害した遺言書を作成した場合には、相続が起きた後で「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があります。遺留分侵害額請求とは、「侵害された自分の遺留分相当額を、金銭で支払ってくれ」という請求のことです。
この例では、すべての財産を相続した配偶者に対して、前妻の子から遺留分相当の金銭を支払えと請求される可能性があるということです。
遺留分割合はどのくらい?
遺留分の割合は、原則として2分の1です。たとえば、夫の相続人が現在の配偶者と、現在の配偶者との間の1名の子、そして前妻との間の1名の子の計3名である場合、それぞれの遺留分は次のとおりです。
- 配偶者:4分の1(=2分の1×2分の1)
- 現在の配偶者との間の子:8分の1(=2分の1×4分の1)
- 前妻との間の子:8分の1(=2分の1×4分の1)
つまり、どのような遺言書を作成したとしても、仮に夫の遺産総額が4,000万円であるのであれば、この8分の1に相当する500万円は前妻の子に権利があるということです。
遺言書作成時の注意点
遺言書を作成する際、前妻の子の遺留分をまったく考慮していなければ、後に遺留分侵害額請求がされてトラブルに発展する可能性があります。そのため、たとえ夫が後妻に多くの財産を渡したいと考える場合であっても、前妻の子も正式な相続人であり遺留分があることを踏まえたうえで、遺言書を作成するようにしましょう。
遺留分に対する主な対応パターンは、次の2つです。
- 前妻の子に遺留分は確保する内容で遺言書を作成する:はじめから、遺留分相当分の遺産は前妻の子に渡す前提で、遺言書を作成する方法です
- 遺留分侵害額請求に備えた金銭を確保する:遺留分を侵害する内容の遺言書を作成したうえで、仮に遺留分侵害額請求がされた場合に侵害額相当を支払えるだけの金銭を確保しておく
「①」は比較的シンプルで、わかりやすいかと思います。
はじめから遺留分相当額を渡す内容の遺言書としておくことで、後の遺留分侵害額請求などのトラブルを防ぐことが可能となります。
一方、「②」は、遺留分侵害額請求というリスクに備える対策方法です。
この方法の具体例としては、たとえば、配偶者を保険金受取人とした生命保険契約を締結しておくことなどが考えられます。夫の死亡により配偶者が生命保険金というまとまった金銭を手にすることができるため、仮に遺留分侵害額請求をされたとしても、受け取った生命保険金を原資として侵害した遺留分相当額を支払うことが可能となります。
また、生命保険金は原則として遺留分算定の基礎に含まれない点も、この方法がよく選択されている理由の一つです。
配偶者居住権の活用を検討する
では、家の他に夫にほとんど財産がない場合や、遺留分対策の生命保険に加入しようにも既に高齢で加入ができない場合などには、どのように対策を取れば良いのでしょうか?
この場合には、2020年4月1日に誕生した「配偶者居住権」の活用が検討できます。配偶者居住権とは、「家」という一つの財産を、次の2つに分けて相続したり、遺言書を使って遺贈したりすることができる制度です。
- 家の所有権
- 配偶者が亡くなるまで無償で家に住む権利
配偶者としては、なにも「家の所有権」自体が欲しいわけではなく、亡くなるまでは安心して住み慣れた家で暮らし続けたいだけである場合が少なくないでしょう。
また、家の持ち主である夫側としても、後妻である妻が亡くなるまでの住まいを確保してあげたいものの、その後妻が亡くなったあとは苦労をさせた前妻の子に家を渡してあげたいとの相反する想いを持つ場合もあるかと思います。
しかし、従来はこの希望を叶えるためには、原則として家の所有権自体をどちらかに渡すほかありませんでした。
一方、配偶者居住権の創設後は、次のような内容の遺言書を作成することが可能となっています。
- 家の所有権:前妻の子に相続させる
- 配偶者が亡くなるまで無償で家に住む権利:配偶者に遺贈する
このような遺言書を生前に作っておくことで、仮に家の他に主だった財産がない場合であっても、配偶者は安心して亡くなるまで無償でその家に住むことが可能となります。
そして、その後配偶者が亡くなった際には、前妻の子がその家を自由に活用することが可能です。
ただし、仮に配偶者がその後施設への入所を検討する場合であっても、家の所有権自体を持っていない以上、家を売って得たお金で施設に入るとの選択が取れなくなる点にも注意が必要です。
持ち家の遺産相続の過程で前妻の子の存在を知った場合の進め方

夫が亡くなった後で持ち家の遺産相続を進めようとしたところ、その過程で前妻の子の存在を知った場合には、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。一般的な進め方を解説します。
- 前妻の子の連絡先を調べる
- 前妻の子と連絡を取って持ち家の遺産相続について話し合う
- 遺産分割協議書を作成する
- 持ち家の相続登記を申請する
前妻の子の連絡先を調べる
はじめに、前妻の子の連絡先を調べるところから始めましょう。亡くなった夫の携帯電話や手帳などに連絡先が載っていれば、それを参考とします。
しかし、亡くなってからはじめて存在を知ったような子であれば、このような手掛かりがないことが少なくありません。この場合には、亡くなった夫の戸籍謄本や除籍謄本などを辿って、前妻の子の現在の住所地を探します。
前妻の子の存在に気がついたということは、手続きの必要性から夫の古い戸籍を取り寄せる中で、子の氏名などが載っていたということでしょう。この場合は、そこからまず子の転籍先などを順に辿り、現在の戸籍謄本を取得します。そのうえで、戸籍の附票を取り寄せることで、現在の住民票の住所を調べることが可能です。
しかし、このような手続きは、慣れていないと容易にできるものではありません。自分で調べることが難しい場合には、司法書士や弁護士、行政書士などの専門家へ相談すると良いでしょう。
前妻の子と連絡を取って持ち家の遺産相続について話し合う
前妻の子の住民票の住所地がわかったら、まずは手紙などで丁寧に事情を伝えると良いでしょう。そのうえで、遺産分割協議を行います。スムーズに分割内容が決まれば問題ありません。
この際、後妻側の立場であれば、「自分が多くもらって当然だ」との姿勢で話し合いに臨むようなことは、絶対に避けるべきです。前妻の子であっても被相続人にとっては実の子であり、正式な相続人です。むしろ、父親がいないことで不遇な想いをする場面もあったことでしょう。
そのような背景を汲み、少なくとも法定相続分はきちんと分ける前提で話し合いを進めてください。
そのうえで、万が一欲しい財産が重複するなど主張が食い違うなど協議がまとまらない場合には、調停へと移行します。調停とは、調停委員立ち会いのもとで行う、家庭裁判所で行う話し合いのことです。調停でも話し合いがまとまらなければ、裁判所に決断を下してもらう審判へと移行しましょう。
遺産分割協議書を作成する
問題なく遺産分割協議がまとまったら、その結果を記した遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、前妻の子を含め、相続人全員の署名と実印での捺印が必要です。
相続人全員の印鑑証明書も必要となりますので、前妻の子からは捺印の際に併せて印鑑証明書をもらっておくと良いでしょう。
持ち家の相続登記を申請する
遺産分割協議書や印鑑証明書などの必要書類がそろったら、相続登記を申請しましょう。これで、持ち家の相続手続きは完了となります。
まとめ
前妻の子も、夫にとっては実の子であり正式な相続人です。そのため、当然ながら夫の持ち家を遺産相続するにあたっては、前妻の子を無視して進めることはできません。
何の対策もないままに相続が起きてしまえば相続争いに発展してしまう可能性がありますので、前妻の子がいる場合には、生前早いうちから対策を取っておきましょう。
また、相続が起きてから前妻の子の存在を知った場合には、その連絡先を調べたり持ち家の名義変更に必要となる書類を集めたりするだけでも一苦労です。






