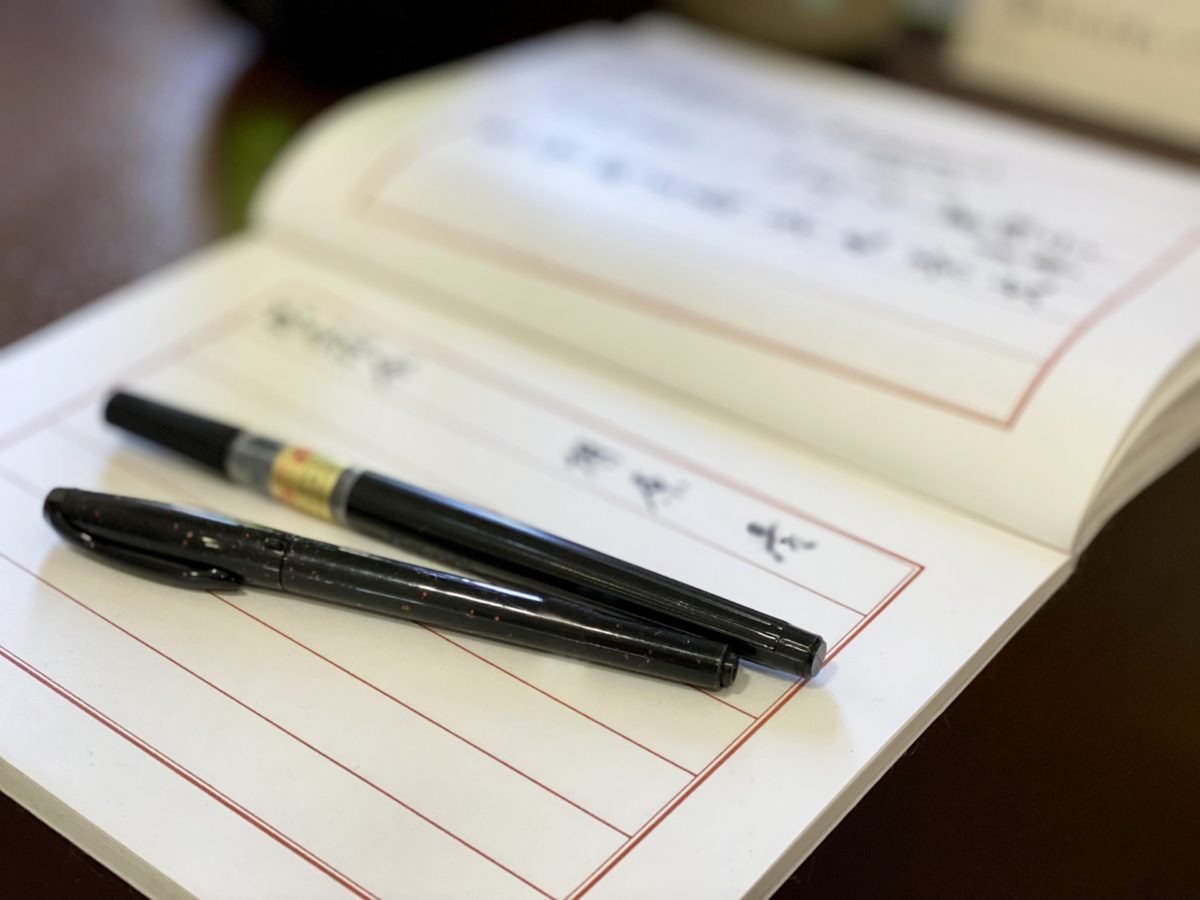お通夜に参列したさい、最初に挨拶するのは受付にいる人です。
参列者にとって受付係は遺族側の人ですから、近しい親族でなくても遺族の代理としてその仕事を勤めなければなりません。
では、お通夜の受付係を行う人は、どのような点に気をつけて役割を果たすべきなのでしょうか?
今回は、お通夜の受付係が担う具体的な仕事内容やお通夜の受付係をする際の注意点について、詳しく解説していきます。
目次
お通夜の受付の役割

お通夜では、故人が亡くなって初めて一般参列者が遺族と対面します。
お通夜に足を運ぶ参列者の多くが香典や供物を手に斎場を訪れますが、最初にお悔やみを述べて香典や供物を渡す相手がお通夜の受付係です。
本来出迎えるべき遺族はお通夜をつつがなく終えるために忙しくしているため、お通夜の受付係は「遺族の代わりに参列者を出迎える」という役割を果たさなければなりません。
さらに、遺族に代わって会葬のお礼に「会葬礼状・礼品」を渡し、参列者をお通夜の会場へ促すのも受付係の仕事です。
たとえ遺族に受付を頼まれた遠縁の人であっても、参列者にとっては挨拶をするべき「遺族」という立場になるため、受付係は参列者にも遺族にも失礼がないようその役割を果たすようにします。
お通夜の受付がやること

お通夜の受付には、参列者を出迎えてからお通夜の会場へ促すまでに一連の流れとして仕事があります。
そのため、お通夜の受付でやるべきことがわかってないと、流れが滞ったり間違ってしまう可能性があるのです。
では、お通夜の受付がやるべき仕事とはどのようなものなのでしょうか?
受付係が斎場に到着してからお通夜が始まるまでの一連の流れと仕事内容を解説しましょう。
- 事前準備を整える
- 参列者へ挨拶・受け答えする
- 芳名帳への記入をお願いする
- 香典や弔電・供物を受け取る
- 会葬礼状・礼品を渡す
やること①:事前準備を整える
お通夜の受付係が最初に行う仕事は、受付をするための事前準備です。
お通夜の受付では参列者に芳名帳の記入をしてもらい、香典や供物を預かって会葬礼状・礼品を渡すという流れがあるため、その内容に沿って準備をしなければなりません。
受付係が行う事前準備には、次のようなものが挙げられます。
- 芳名帳を用意する
- 芳名帳の筆記用具を準備する
- 会葬礼品・礼状を準備する
さらに、物品の事前準備をしつつ葬儀社の人と話し合い、万が一会葬礼品・礼状が足りなくなった際の段取りや、お通夜が始まった際の受付交代のタイミングも決めなければなりません。
この段階で、
- 挨拶して芳名帳への記入をお願いする人
- 香典を受け取り会葬礼品・礼状を渡す人
- 供物を受け取った時に祭壇へ運ぶ人
と役割分担も決めておき、預かった香典の管理方法まで細かく話し合うと良いでしょう。
やること②:参列者へ挨拶・受け答えする
お通夜の受付が始まったら、最初に行うことが参列者への挨拶です。
一般参列者にとって、受付にいる人は「遺族」になるため、遺族に代わって丁寧に受け答えしましょう。
まれに、受付の人と知り合いの参列者がその場で話をすることがありますが、参列者が多いお通夜でそのような行為をすると流れが滞ってしまいます。
受付では一言二言で会話を止め、速やかに着席できるよう促しましょう。
やること③:芳名帳への記入をお願いする
参列者と挨拶をしたら、芳名帳への記入を依頼します。
芳名帳は、葬儀がすべて終わった後に遺族が確認し、後日連絡をしたり香典返しを送る時に見返すという役割があるため、参列者全員に記入をお願いしてください。
用意する筆記用具は「筆ペン」「サインペン」が一般的ですが、人によって書きやすさに違いがあるのでできるだけ複数の種類を用意し、参列者が問題なく記帳できるようにしておきましょう。
やること④:香典や弔電・供物を受け取る
芳名帳の記入が済んだら、参列者から香典や弔電・供物が受付で手渡されます。
香典はお悔やみの気持ちを包んだお金なので、受け取ったら一つの場所にまとめて保管しておき、目を離さないように注意しましょう。
弔電や供物は、受け取った後遺族と葬儀社の人のもとへ運びます。
お通夜では、弔電や供物を送ってくださった人の名前を読み上げることがあるため、読み落としがないようすぐに遺族の手元へ届け、司会の人の段取りが組みやすくなるようにしましょう。
やること⑤:会葬礼状・礼品を渡す
香典や弔電・供物を受け取ったら、参列者へ会葬礼状・礼品を渡します。
多くの場合、会葬霊場と礼品は遺族が葬儀社を通して準備をしていますので、大まかな数や足りなくなった時の対応について事前に把握しておきましょう。
また、家族葬や小規模葬を理由に香典辞退をする場合でも、お通夜に参列する人には会葬礼状・礼品を渡します。
この場合は、芳名帳に記入して頂いた後にお渡しするので、受付をする前には葬儀の内容や規模も尋ねておくと良いでしょう。
お通夜の受付かkをする人

お通夜の受付には、故人やその遺族と付き合いがあり、なお且つお手伝いができる遠縁の人を選ぶようにします。
では、具体的にどのような人にお通夜の受付をお願いすれば良いのか、具体的な例を紹介していきましょう。
遺族の親族
一般的な葬儀で一番多いのは、「遺族の親族が受付をする」という例です。
たとえば、もし故人が高齢で亡くなった場合、喪主になるのはその子供で、故人の孫、兄弟までが2親等内に当たります。
2親等内の親族は故人にとって近しい遺族であるため、受付の仕事をするよりも僧侶を出迎えたりお通夜を仕切る仕事をしなければなりません。
故人からみて3親等以上の親族は、遺族よりも遠くお通夜を仕切る必要もないため、受付係を請け負うことができます。
遺族の親族に受付をお願いする際は、故人からみて3親等以上の親族を目安にすると良いでしょう。
遺族の友人・知人
遺族と家族ぐるみで付き合いのある友人や知人も、お通夜の受付を頼むケースが少なくありません。
とくに、遺族の親戚が遠くに住んでいてすぐに駆けつけることが難しい場合、親族に代わってお手伝いをしてくれるのは心強いものです。
普段から遺族と顔見知りで信頼がおける人なら、香典を預かる受付を任せても安心できるため、いざという場合には遺族の友人・知人に受付をお願いしてみましょう。
遺族の仕事関係者
故人に社会的地位があり多くの人に慕われている場合、故人や遺族の仕事関係者がお通夜の受付をすることもあります。
仕事関係者が受付をする場合、ある程度組織的に段取りを組んで動きますから、対応に忙しい遺族も安心して任せられることがメリットです。
また、遺族の仕事関係者の場合、「何かお手伝いできますか?」と自分から声を掛けてくれるケースも少なくありません。
もし人手が足りず困っているのであれば、心遣いをありがたく受け取って受付係をお願いしてみましょう。
お通夜の受付係のやり方・流れ

お通夜の受付係は、事前準備や段取りなどやらなければならないことが多いため、一連の流れを把握しておくことが大切です。
ここでは、お通夜の受付係のやり方について、流れに沿って順番に紹介していきます。
- お通夜の30分前に集まる
- 受付の準備をする
- 役割分担の確認する
- 参列者に対応する
- お通夜へ参列する
流れ①:お通夜の30分前に集まる
お通夜の受付係は、最低でも30分前には斎場に集まるようにします。
これは、受付係の最終確認と顔合わせの意味もあり、もし何かしらの理由で急遽受付係ができなくなった場合はこの時間で対応にあたります。
もともと、遺族や親族はお通夜の1時間前には斎場に入るのが一般的ですが、万が一のアクシデントの備え、受付係も30分から1時間前には集まるようにしましょう。
流れ②:受付の準備をする
受付係が揃ったら、受付に必要なものを準備します。
芳名帳・筆記用具・香典を保管しておく箱や紙袋・会葬礼状・礼品を準備し、足りないものがないか確認したら所定の位置に設置しましょう。
このとき、できれば葬儀社の人に会葬礼状・礼品の補充方法や供物・弔電が届いた時の対応についても質問し、受付が始まっても慌てないよう段取りをつけてください。
流れ③:役割分担の確認する
すべての準備が整ったら、受付の役割分担を確認します。
一般的に、お通夜の受付は2人から3人が担当することが多いため、
- 参列者へ挨拶する人
- 芳名帳への記帳をお願いする人
- 香典を受け取り会葬礼品・礼状を渡す人
というように、役割分担を決めて確認してください。
流れ④:参列者に対応する
斎場の受付時間になったら、順番に参列者へ対応します。
お通夜の参列者は、早ければ15分〜30分前に到着するので、できるだけスムーズに流れるよう段取り良く対応していきましょう。
参列者数が多い時は芳名帳を複数用意し、お通夜の開始時間に間に合うよう対応してください。
流れ⑤:お通夜へ参列する
お通夜の開始時間になったら、受付係も着席しなければなりません。
しかし、後から遅れて参列する人もいますし、香典の保管もあるため受付には誰かが残らなければなりません。
多くの場合、葬儀社の人が頃合いを見て交代を促してくれますが、忙しいとタイミングがずれてしまいます。
もしお通夜の時間になっても交代できない時は必ず一人は受付に残り、遅れてきた参列者にも対応できるようにしましょう。
お通夜の受付の挨拶例

お通夜の受付係は、遺族に代わって参列者に挨拶をしなければなりません。
基本的な弔事の挨拶ができればさほど難しくありませんが、最近では家族葬や小規模葬なども増えているため、葬儀の内容に合わせた挨拶が必要です。
では、お通夜の受付ではどのような挨拶をするのがふさわしいのか、具体的な挨拶例をシーン別に紹介しましょう。
基本の挨拶例
受付係は、遺族の立場に立って参列者のお悔やみを受けて挨拶をします。
参列者は受付に来た際に「この度はご愁傷様です」というお悔やみを述べますので、それに対し受付係は「本日はお忙しい中、ご参列を賜りありがとうございます」と挨拶をしてください。
また、天候の悪い日にお通夜に来てくださった人に対しては、「お足元の悪い中、ご参列をいただきありがとうございます」と述べると、より心のこもった挨拶になります。
どちらの例も基本になりますので、天候や状況に合わせて使い分けると良いでしょう。
香典や弔電・供物を受け取る際の挨拶例
参列者が受付で渡す香典や弔電・供物は、お悔やみの気持ちがこもったものです。
いただくものなので、つい「ありがとうございます」と言いそうになりますが、香典や弔電・供物は故人とその遺族に贈られるものです。
そのため、代理人である受付係が「ありがとうございます」と述べるのは相応しくありません。
この場合は、受付で預かった香典や弔電・供物は必ず故人と遺族に届けますという気持ちを込めて、「お預かりいたします」という挨拶をしましょう。
香典辞退の際の挨拶例
近年では、家族葬や小規模葬といった葬儀を行うケースも増えており、それにともなって遺族が「香典辞退」をすることも少なくありません。
前もって遺族から香典辞退の申し出を受けている場合もありますが、まれに香典辞退を受付で伝えるケースがあります。
もし香典辞退のお通夜で受付をする際は、あらかじめ受付に香典辞退を申し出る看板を用意しておきます。
その上で、香典を渡そうとする参列者に対し「申し訳ありません、故人の意志によりお香典は辞退させていただきます」と丁寧に伝えてください。
お通夜の受付係を依頼された際の対応

故人の訃報を受けて間もなく、遺族の方から「お通夜の受付をお願いしたい」という申し出を受けたら、どのように返せば良いのか悩みますよね。
参列するつもりなら返答もしやすいですが、何かしらの事情がある場合、お断りするのも気が引けます。
では、もしお通夜の受付係を依頼されたらどのように対応するべきか、具体的な例を挙げて解説しましょう。
基本的には引き受ける
まず押さえておいて欲しいことは、「お通夜の受付係を依頼されたら基本的に引き受ける」という考えです。
故人を亡くしたばかりの遺族はそれだけでも大変な状況です。
お手伝いできるところはしっかりと手伝い、少しでも遺族の負担が軽くなるよう心掛けましょう。
断る場合は理由を伝える
何かしらの事情がありお通夜の受付係ができない場合は、「〇〇なのでお手伝いできず、申し訳ございません」と伝えるようにします。
たとえば、病気や怪我などをしていて受付係が難しい場合、その理由を伝えないと遺族が誤解し、葬儀後のおつきあいに影響が出てしまいます。
やむを得ない事情があることを伝えれば、依頼した遺族も納得した上で了承してくれます。
受付係の依頼を断る際は、理由をはっきりと伝えてください。
依頼を受けたらできるだけその場で返答する
受付係を依頼する遺族は、連絡をした段階ですでに「やってもらえる」「やって欲しい」という強い希望を持っています。
やむを得ない事情があるなら無理強いはできませんが、その代わり遺族はやってもらえる人を短い時間で探すことになります。
お断りする際は少しでも時間の余裕ができるように、できるだけその場で返答するようにしましょう。
お通夜の受付にふさわしい服装

お通夜の受付係は、遺族の代理で参列者に対応するという役目があります。
したがって、参列者にも遺族にも失礼がないよう、お通夜に受付にふさわしい服装をしなければなりません。
では、お通夜の受付にふさわしい服装とはどのようなものなのでしょうか?
男女別に分けて詳しく解説していきます。
男性の服装
受付係をする男性は、正喪服か準喪服が基本です。
白いワイシャツに黒のネクタイをして、黒の靴下と黒い革靴で服装を整えましょう。
黒い革靴は光沢がないものを選び、髪の毛も清潔感があるよう整えてください。
結婚指輪程度のアクセサリーや時計であれば身につけても問題ありません。
ただし、できれば時計は派手ではないものを選び、時計として実用性のあるものを身につけましょう。
女性の服装
受付係をする女性は、正喪服か準喪服のワンピースやツーピースが基本です。
ベージュや黒のストッキングに、金具がなくエナメル質でないパンプスを用意し、誠実な服装を意識しましょう。
身につけて良いアクセサリーは、結婚指輪や真珠の一連ネックレスだけです。
なお、肌が露出した透け感がある素材の服は、受付係にはふさわしくありません。
派手なネイルや髪色、鮮やかなメイクもお通夜の受付係では失礼にあたるため、細部に至るまでチェックしてから受付係をするようにしてください。
お通夜で受付係をする際のマナー・注意点

お通夜で受付係をする時は、守るべきマナーや注意点があります。
では、どのような点に気を付けて受付係をすれば良いでしょうか?
具体的な例を交えながら紹介していきます。
- 必ず複数人で対応する
- 事前に役割分担しておく
- 葬儀社との連携を確認する
マナー・注意点①:必ず複数人で対応する
受付係の仕事は、参列者へのご挨拶から芳名帳への記入案内、香典の受け取りと会葬礼状・礼品の渡すなど多くの項目があります。
参列者が少なければ1人や2人でも良いですが、50人以上になるとかなり忙しくなります。
そのため、必ず複数人で対応し、参列者をスムーズに案内できるようにしましょう。
マナー・注意点②:事前に役割分担しておく
受付係の仕事を問題なく行うためには、事前の役割分担が重要です。
1人が多くの役割を担ってしまうと、そのぶん受付業務が滞り、結果として参列者にご迷惑を掛けることにもなりかねません。
受付係をする際は、必ず事前に話し合い役割分担を決めておくようにしましょう。
マナー・注意点③:葬儀社との連携を確認する
受付係は会場の外にいるため、お通夜の流れを知るためにも葬儀社との連携は欠かせません。
さらに、受付で必要な物品が足りなくなった場合、葬儀社の人に相談して代わりに対応してもらいます。
受付でスムーズな対応を行うためにも、葬儀社とよく相談して流れを確認しておき、連携を取って受付係の仕事に取り組めるようにしましょう。
まとめ

お通夜の受付を急に依頼されると少し不安になりますが、基本的な仕事内容や注意点を押さえておけば、問題なく受付係を努められます。
「受付係は遺族の代理で仕事をする」という点を意識して行動し、わからないことは葬儀社の人に相談しながらつつがなくお通夜の受付係が努められるよう準備しましょう。