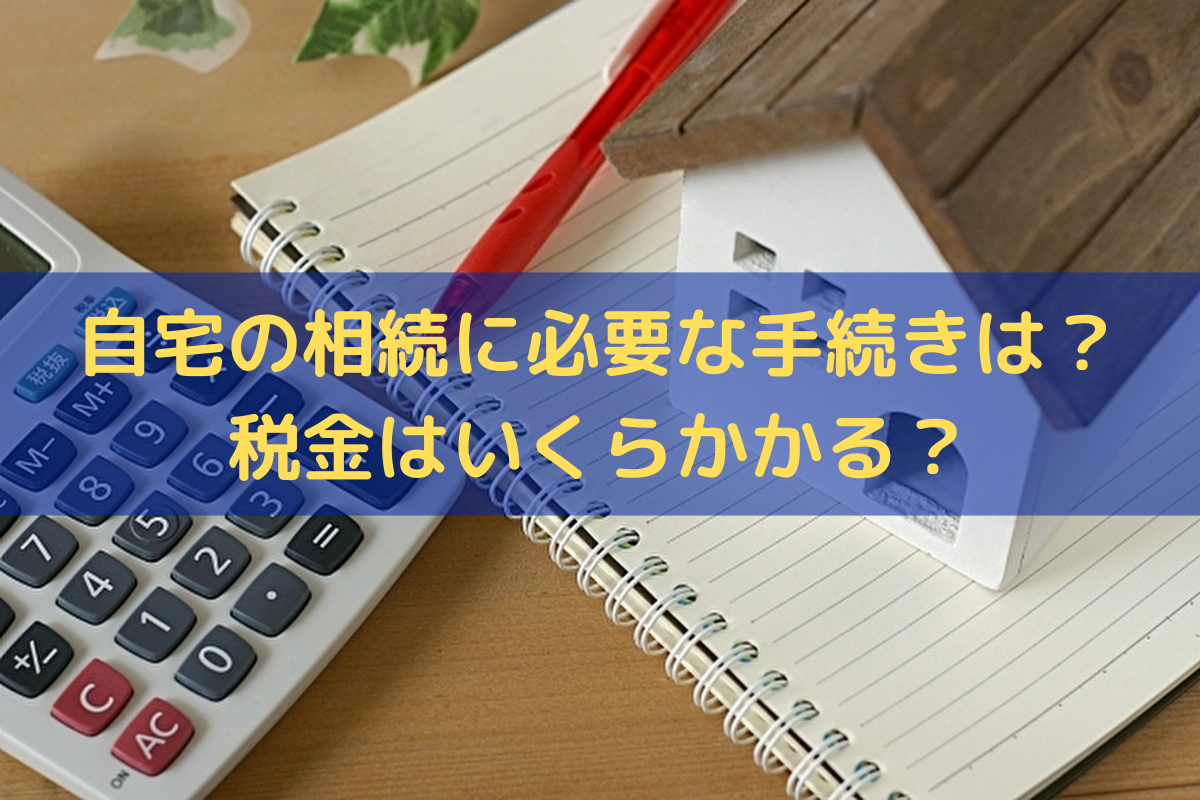自宅不動産を所有していた人が亡くなると、さまざまな手続きが発生します。たとえば、自宅不動産の名義変更である「相続登記」や、一定以上の遺産があった場合に必要となる「相続税申告」などです。
しかし、これらは日ごろから行う手続きでないため、どのような手続きであるのかイメージが湧かないという方も少なくないでしょう。そこで今回は、自宅の相続で必要な手続きについてまとめて解説します。
目次
自宅の相続で必要になる手続き

自宅の所有者が亡くなったときには、次の流れで相続手続きを進めます。
- 相続財産調査
- 相続人調査
- 遺産分割協議
- 相続税の申告
- 相続登記
たとえば、亡くなった人と同居していた配偶者や子供が自宅を相続して住み続ける場合、配偶者や子供が自宅に住む点ではそれまでと変わりません。
しかし、自宅の所有者が変わるため名義変更の手続きが必要で、ケースによっては相続税がかかり、申告や納税の手続きも必要になります。
相続開始後にやるべき手続きが何かを理解して、必要な手続きを漏れなく行うようにしましょう。
相続財産調査:遺産に含まれる財産を把握する
家族が亡くなって相続が開始したら、遺産にどんな財産が含まれるのか、まずは相続財産調査を行う必要があります。遺産の分け方を話し合う遺産分割協議の対象となる遺産がそもそも何か、相続税の計算の基礎になる遺産額がいくらか、確定させる必要があるからです。
財産を遺す人が生前に財産の一覧(財産目録)を作っていれば簡単に確認できますが、そうでない場合は、相続人が遺産を一つひとつ確認しなければなりません。
そのため、銀行口座の預金や土地・自宅などの不動産、株式、車など、亡くなった人が所有していた財産を漏れなく確認しましょう。また、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になるので、亡くなった人に借金がある場合は未返済額を確認します。
相続人調査:誰が相続人なのか確認する
亡くなった人の家族の中で、誰が相続人として遺産を相続できるのかは、法律でルールが決まっています。相続が開始したら、遺産の相続権を持つ人が誰なのか、確認をしなければなりません。
そのために行うのが相続人調査で、亡くなった人の戸籍を取り寄せて相続人が誰か確認します。亡くなった人の配偶者は相続人になれますが、子・親・兄弟姉妹の間では相続人になる順位が決まっていて、子が第一順位、親が第二順位、兄弟姉妹が第三順位です。
子・親・兄弟姉妹は、順位の高い人が相続人になり、先順位の人がいない場合には次順位の人が相続人になります。
遺産分割協議:遺産の分け方を話し合う
相続人が2人以上いる場合、遺産をどのように分けるか相続人で話し合って決めなければなりません。遺産の分け方を協議するのが遺産分割協議で、相続人となるすべての人が協議に参加して遺産分割方法について話し合います。
遺産分割協議に期限はありませんが、誰がどの財産を相続するのか決まらないと、相続税申告の減額特例を使えなかったり、遺産を活用できず相続人自身が困ったりする場合があるため、早めに協議をして決めるようにしましょう。話し合って合意できたら、協議した内容を遺産分割協議書としてまとめます。
なお、亡くなった人が生前に遺言書を作成しており、すべての財産の分け方を指定している場合は、遺産の分け方を話し合う必要がないため遺産分割協議は不要です。
相続税の申告:税額を計算して申告書を作成・提出する
遺産を相続する場合、相続税がかかる場合とかからない場合があります。そして、相続税がかかる場合には、相続が開始してから10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。
まず、遺産総額が3,600万円以下であれば相続税はかからず、逆に3,600万円を超える場合は、基本的に相続税がかかり申告が必要です。ただし、3,600万円を超える場合でも、特例制度を使えて相続税がかからずに済む場合があります。
- 配偶者控除:配偶者が遺産を相続する場合は少なくとも1億6千万円まで相続税がかからない
- 小規模宅地等の特例:居住用や事業用の土地を相続する場合に、一定の要件を満たすと土地の価格を最大80%減額してから相続税を計算できる
配偶者控除や小規模宅地等の特例を使った結果、相続税がゼロになる場合には納税は必要ありませんが、特例の適用を申請するために申告の手続きは必要になります。
相続登記:自宅の名義変更を行う
遺産分割協議をした結果、誰が自宅を相続するのか決まったら、自宅の名義を亡くなった人から相続する人に変更します。相続に伴って不動産の名義を変更する手続きが相続登記で、これは法務局で行う手続きです。
相続登記で必要になる手続き書類はケースによって異なり、たとえば遺産分割協議を行った場合には、主に次の書類を揃えて法務局に提出する必要があります。
- 登記申請書
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、住民票の除票
- すべての相続人の戸籍謄本と印鑑証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票
自宅の相続税評価額の求め方

相続税の計算では、遺産の総額を求めて基礎控除額を引いた上で、税率を掛けて税額を求めます。そして、遺産の総額を計算する際、個々の財産の価格として使うのは相続税評価額です。
財産の種類によっては、相続税評価額が一般的な取引価格(時価)とは異なる場合があります。不動産もその一つで、自宅の建物や土地の相続税評価額を計算するときには、法律で決められた一定のルールに従って計算しなければなりません。
ここでは建物と土地、それぞれの相続税評価額の計算方法について紹介します。
建物の相続税評価額
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同じです。そのため、相続税を計算するときには、まずは自宅の固定資産税評価額を確認するようにしましょう。固定資産税評価額は役所で固定資産課税台帳を見れば確認できます。
土地の相続税評価額
土地の相続税評価額の計算方法には、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があり、どちらの方式が適用されるかは土地ごとに決まっています。
路線価方式
路線価とは、路線に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格のことです。
路線価方式が適用される土地では、路線価に土地の面積を掛け合わせて、さらに土地の形状等に応じて補正を行って相続税評価額を求めます。
倍率方式
倍率方式が適用される土地では、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて相続税評価額を求めます。
土地ごとの路線価や倍率方式で掛け合わせる率は国税庁ホームページで確認できます。
自宅の相続税の計算方法・計算例
自宅にかかる相続税は、どのように計算すれば良いのでしょうか?まず、相続税は「自宅不動産にいくら」「預貯金にいくら」などと、遺産ごとに計算されるものではありません。この点を誤解のないように整理しておいてください。
ここでは、次の前提で相続税の計算の流れを解説します。
- 自宅不動産を含んだ「課税価格の合計額」が2億円
- 法定相続人は、配偶者、長男、二男の3名
- 遺産は配偶者が1億円、長男が1億円相続し、二男は相続しなかった
課税価格の合計額を計算する
はじめに、「課税価格の合計額」を計算します。課税価格の合計額とは、次の額を合計した金額から、被相続人の債務と葬儀費用を引いた金額です。
- 自宅不動産を含んだ遺産総額
- 生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」から、一定の非課税額(500万円×法定相続人の数)を控除した金額
- 相続で財産をもらった相続人などが、過去3年以内に被相続人から受けた贈与の総額
- 相続時精算課税制度を使って被相続人から受けた贈与の総額
これを正しく算定するためには、各遺産を正しく評価しなければなりません。そして、各遺産の評価には、非常に専門的な知識が必要です。
なお、後ほど紹介する「小規模宅地等の特例」の適用を受ける際には、各遺産を評価する段階で適用します。ここでは、この課税価格の合計額は2億円であると仮定して、次の計算へ進みましょう。
相続税の基礎控除額を計算する
次に、相続税の基礎控除額を計算します。相続税の基礎控除額の計算式は、次のとおりです。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例の場合には法定相続人が3名ですので、次のとおりとなります。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×3名=4,800万円
課税遺産総額を計算する
次に、課税価格の合計額から相続税の基礎控除額を控除し、課税遺産総額を算定します。
例の場合には、次のとおりです。
- 課税遺産総額=2億円-4,800万円=1億5,200万円
法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額を計算する
課税遺産総額に各法定相続人の法定相続分を乗じ、法定相続分に応じた取得価格を算出します。
この時点では、実際に誰がいくらの遺産を相続したのかは、一切関係ありません。例の場合には、次のとおりとなります。
- 配偶者:取得金額=1億5,200万円×2分の1=7,600万円
- 長男:取得金額=1億5,200万円×4分の1=3,800万円
- 二男:取得金額=1億5,200万円×4分の1=3,800万円
法定相続人ごとの税額を算出する
上で算定をした法定相続分に応じた取得価格を速算表に当てはめ、法定相続人ごとの税額を算出します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例のケースをこれに当てはめると、次のとおりです。
- 配偶者:税額=7,600万円×30%-700万円=1,580万円
- 長男:税額=3,800万円×20%-200万円=560万円
- 二男:税額=3,800万円×20%-200万円=560万円
相続税の総額を算出する
次に、上で算定をした法定相続人ごとの税額を合計し、相続税の総額を算定します。例の場合には、次のとおりです。
- 相続税の総額=1,580万円+560万円+560万円=2,700万円
財産を取得した人ごとの税額を計算する
最後に、相続税の総額を実際に相続した割合で按分し、各相続人が実際に負担する相続税額を算定します。例の場合には、次のとおりです。
- 配偶者:相続税額=2,700万円×1億円/2億円=1,350万円
- 長男:相続税額=2,700万円×1億円/2億円=1,350万円
- 二男:相続税額=2,700万円×0円/2億円=0万円
なお、後ほど解説をする「配偶者の税額軽減」や「未成年者控除」などは、この後で適用します。このケースで「配偶者の税額軽減」の適用を受ければ、配偶者が納めるべき相続税は結果的にゼロとなるでしょう。
相続税の節税につながる特例制度

将来の相続で相続税がかかりそうな場合でも、生前に対策をすれば相続税の負担を軽減できる場合があります。
- 納税後に相続人の手元に残る財産が増えて、実質的により多くの財産を渡せる
- 相続税の納税資金の準備で相続人が困らずに済む
自宅の相続でも、相続税の特例制度を使えば相続税を節税できる場合があります。
特例制度の要件を満たす人に自宅を相続させたり、特例制度の要件を満たすように生前に対策をしたりして、少しでも税負担を軽減するようにしましょう。
配偶者は1億6千万円の遺産まで相続税がかからない
配偶者が遺産を相続する場合は、少なくとも1億6千万円の遺産まで相続税がかかりません。
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)と呼ばれる特例制度で、自宅のような高額な財産を相続する場合でも、配偶者であれば相続税がかからずに済むことが多くなります。
そのため、財産額が1億6千万円以下であれば、自分が死んだときに配偶者に相続税がかかったり納税資金の準備で困ったりすることは、基本的にないと考えて良いでしょう。
ただし、配偶者が遺産を相続した場合に、その配偶者が亡くなったときに子供がその財産を相続する場合には、相続税がかかることがあります。
配偶者が遺産を相続する一次相続では相続税がかからなくても、配偶者から子へ相続する二次相続でかかる相続税がむしろ増えてしまうケースがあるので、注意が必要です。
1億6千万円まで配偶者に相続税はかからないため、一次相続で配偶者がより多くの財産を相続するほうが節税になると考えがちですが、二次相続まで考慮すると節税にならない場合があります。
小規模宅地等の特例を使えると節税効果が大きい
配偶者や同居の子供など、一定の要件を満たす人が居住用や事業用の土地を相続する場合、土地の価格を最大80%減額した上で相続税を計算することができます。
小規模宅地等の特例と呼ばれる制度で、自宅の相続でこの特例を使えれば大きな節税効果を発揮するため、ぜひとも活用したい特例制度の一つです。
たとえば、子供が自宅の建物と土地を相続する場合、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に子供が居住していることが、特例を受けられる条件の一つになります。
そのため、将来自宅を子供に相続させる予定の場合には、生前から同居するなどしてその土地に子供が住むようにして、特例を使えるようにして相続税負担を軽減すると良いでしょう。
自宅の相続をする場合に使える可能性があるその他の控除・特例
上で紹介をした「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」のほか、相続税で活用できる可能性のある控除には、次のものなどが存在します。それぞれの概要は次のとおりです。
ただし、それぞれの控除には要件がありますので、実際に適用を受ける際には、税務署または税理士などの専門家へご相談ください。
未成年控除
未成年者控除とは、遺産を受け取った人が未成年者である場合において、相続税の額から一定の金額を差し引ける控除です。未成年者控除の額は、次のように計算します。
- 未成年者控除額=その未成年者が満18歳になるまでの年数(1年未満切上)×10万円
上で挙げた計算例で、仮に長男の年齢が15歳3か月であれば、長男の納付税額は次のとおりとなります。
- 未成年者控除額:3年×10万円=30万円
- 納付税額:1,350万円-30万円=1,320万円
障害者控除
障害者控除とは、遺産を受け取った人が一定の障害者である場合において、相続税の額から一定の金額を差し引ける控除です。障害者控除の額は、次のように計算します。
- 障害者控除額=その障害者が満85歳になるまでの年数(1年未満切上)×10万円(特別障碍者の場合には20万円)
上で挙げた計算例で、仮に長男が特別障害者であり、25歳5ヶ月であれば、長男の納付税額は次のとおりとなります。
- 傷害者控除額:60年×20万円=1,200万円
- 納付税額:1,350万円-1,200万円=150万円
相次相続控除
相次相続控除とは、相次いで相続が起きた場合に適用できる控除です。次の2つの要件を満たす場合には、この控除が受けられる可能性があります。
- 今回の相続の開始前10年以内に開始した相続(以後、「前回の相続」といいます)で、今回の被相続人が財産を取得したこと
- 前回の相続で、今回の被相続人に相続税が課されたこと
これは、「前回の相続で課税された相続税額のうち1年あたり10パーセントの割合で逓減した後の金額」を今回の相続に係る相続税額から控除しようというものであり、計算式はやや複雑となっています。
各相続人の相次相続控除額=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10
※C/(B-A)が100/100を超えるときは、100/100とする
- A:今回の被相続人が前回の相続で課せられた相続税額
- B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額)
- C:今回の相続等で財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
- D:今回のその相続人の純資産価額
- E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満切捨)
上の例で、仮に被相続人が3年2ヶ月前の相続で1億円の遺産を受け取り2,000万円の相続税を負担していた場合には、長男の相続税は次のようになります。
- 相次相続控除額:2,000万円×2億円/(1億円-2,000万円)×1億円/2億円×(10-3)/10=700万円(※「2億円/(1億円-2,000万円)」が100/100を超えるため、ここは100/100)
- 納付税額=1,350万円-700万円=650万円
自宅を相続する場合の相続税の申告手続き方法
自宅の相続などで相続税がかかる場合、相続税の申告はどのように進めれば良いのでしょうか?主なポイントは次のとおりです。
できるだけ早く税理士に相談する
相続税の申告には非常に専門的な知識が必要であり、これを自分で行うことは困難です。自分で行った場合には、計算を誤って税務署から調査に入られたり、適用できたはずの特例の適用を漏らして相続税を払い過ぎてしまったりするリスクなどが生じるでしょう。
そのため、相続税の申告は無理に自分で行わず、税理士へ依頼することをおすすめします。
また、相続税の申告書を正しく作成するには、プロである税理士であっても、相当な時間が必要です。そのため、申告期限ギリギリになってから相談するのではなく、相続が起きたらできるだけ早く相談しておくと良いでしょう。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は、相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内です。この日までに申告と納税を終える必要があるほか、上で紹介をした「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの特例の適用を受けるためには、原則としてこの日までに遺産分割協議がまとまっていなければなりません。
申告期限までに遺産分割協議がまとまっていなければ、期限内にいったん仮の申告と納税を行い、その後遺産分割協議がまとまってから再度申告をし直す必要が生じます。そのため、相続税の申告が必要である場合には、申告期限を意識しながら遺産分割協議をまとめる必要があるでしょう。
【ケース別】自宅の相続に関する注意点

自宅のような高額な財産が遺産に含まれる場合には、誰が相続するかを巡ってトラブルになる場合があります。
また、配偶者居住権など法律で定められた制度は、うまく活用すれば相続人にとってメリットになる一方で、デメリットが生じる場合もあるため注意が必要です。
ここでは、自宅の相続で注意すべき点について、ケース別に紹介していきます。
親名義の自宅を子供が相続する場合
子供が2人以上いる場合、親が亡くなり実家を誰が相続するのかを巡って揉めて、相続トラブルになる場合があります。
「自分の家族は仲が良いから大丈夫」と思っている場合でも、いざ相続の話をしてみると考え方の違いが明らかになって、揉めるケースが少なくありません。
そのため、親名義の自宅を将来子供が相続する場合には、親が生きているうちに将来の相続に向けた話し合いをしておきましょう。
親が亡くなった後に子供同士で話し合うと揉めてしまうケースでも、親が生きているうちに話し合えば、親も話し合いに参加できて意見の交換や調整がしやすくなります。
なお、親が亡くなった後、子が共有名義で不動産を所有する共有分割という遺産分割方法がありますが、共有分割はおすすめできません。
不動産を複数の人が共同で所有すると、売却などをしたい場合でも他の所有者の同意が必要になり、不動産の有効活用の妨げになることが多くなります。
夫名義の自宅を妻が相続する場合
配偶者が自宅を相続する場合、配偶者居住権という権利をうまく使うと節税になる場合があります。
配偶者居住権とは、文字通り配偶者が家に住み続ける権利のことで、2020年から始まった比較的新しい制度です。
たとえば、夫が亡くなり、3,000万円の不動産を所有権と配偶者居住権に分けて相続し、所有権2,000万円を子供が、配偶者居住権1,000万円を妻が相続するケースを考えましょう。
妻が亡くなり子供が相続する際、配偶者のみに認められた権利である配偶者居住権は消滅して子供への相続の対象にならないため、相続税はかかりません。
そのため、妻が亡くなり子が遺産を相続すると、結果的に子供は配偶者居住権相当分の1,000万円分の権利を相続税をかけずに取得でき、相続税の節税になります。
ただし、配偶者居住権にはデメリットもあり、たとえば配偶者にのみ認められた権利であるため、他人への売却ができません。
もしも自宅を相続した後に売却して、売却で得た資金で老人ホームに入る予定の場合には、配偶者居住権を設定して売却できない状態にしてしまうと困ることになります。
そのため、自宅を相続した後に妻がどのようなライフプランを描くのか、この点を踏まえた上で配偶者居住権を設定するかどうかを決めることが大切です。
自宅を相続したくない場合

自宅を相続できれば家族が住む場所を確保できて安心というケースがある一方で、逆に相続人が自宅を相続したくないというケースもあります。
たとえば、相続人である子はすでに実家を離れて暮らしていて、実家を相続しても住む予定がなく使い道がなくて困る場合です。
もちろん、自宅を相続した後に売却するという選択肢もありますが、立地などが悪くて買い手が見つからないと、固定資産税や維持費などがかかるだけの”負動産”になりかねません。
そこで、自宅を相続すると困るだけの場合には、最初から遺産を相続せず相続放棄をする方法が考えられます。
相続放棄をすれば遺産の相続権を放棄できる
相続放棄とは、相続人が遺産の相続権を正式に放棄することです。
相続放棄をすれば、その人は最初から相続人ではなかった扱いになるため、遺産を一切相続せずに済みます。
自宅だけでなく他の遺産もすべて相続できなくなりますが、自宅を相続すると負動産になって困りそうな場合は、相続放棄をするのも検討すべき選択肢の一つです。
相続放棄ができるのは原則3ヶ月以内
相続放棄ができるのは相続開始後3ヶ月以内で、3ヶ月を過ぎると原則として相続放棄はできません。
3ヶ月を過ぎると、遺産を相続することを認めたことになり、自宅などの遺産を相続人は相続することになります。
自宅を相続したくない場合でも、期限を過ぎると基本的に放棄できなくなるので、相続放棄をする場合は期限を超えないように早めに検討を行いましょう。
相続放棄をするには裁判所で手続きが必要
口頭で「私は遺産の相続権を放棄します」と他の相続人などに伝えただけでは、法的に相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄をするには家庭裁判所で手続きが必要で、手続き先は亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄をする場合は、申請書にあたる相続放棄申述書に必要書類を添付して裁判所に提出します。
- 相続放棄申述書を作成する
- 戸籍謄本など必要書類を揃える
- 管轄の家庭裁判所に書類を提出して申請する
- 裁判所から届く照会書に回答を記入して返送する
- 相続放棄が認められると相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄をするときには、相続放棄をする人の戸籍謄本や亡くなった人の住民除票または戸籍附票などが添付書類として必要になります。
手続きの流れなどが家庭裁判所によって違う場合があるので、実際に相続放棄をする場合は、あらかじめ管轄の家庭裁判所に必要書類などを確認するようにしましょう。
まとめ
自宅不動産を所有していた人が亡くなると、相続登記や相続税申告など、さまざまな手続きが発生します。それぞれの手続きの概要を知り、専門家のサポートを受けながら必要な手続きを一つずつ進めていきましょう。
しかし、すべての手続きを専門家に依頼していては、費用がかさんでしまいます。そこでぜひ、「そうぞくドットコム不動産」の利用をご検討ください。
当社AGE technologiesが提供するそうぞくドットコム不動産は、相続で発生した自宅や土地などの不動産の名義変更手続きを、Webを使って効率化するサービスです。
ポイントは、①手続きに必要な戸籍や住民票などの書類を代行取得 ②申請書の作成は専用のサービスを使ってかんたん作成 ③全国の不動産で利用可能、遠方地域の不動産もリモートで手続き可能の3点で、利用することでもう役所に行く必要がなくなります。