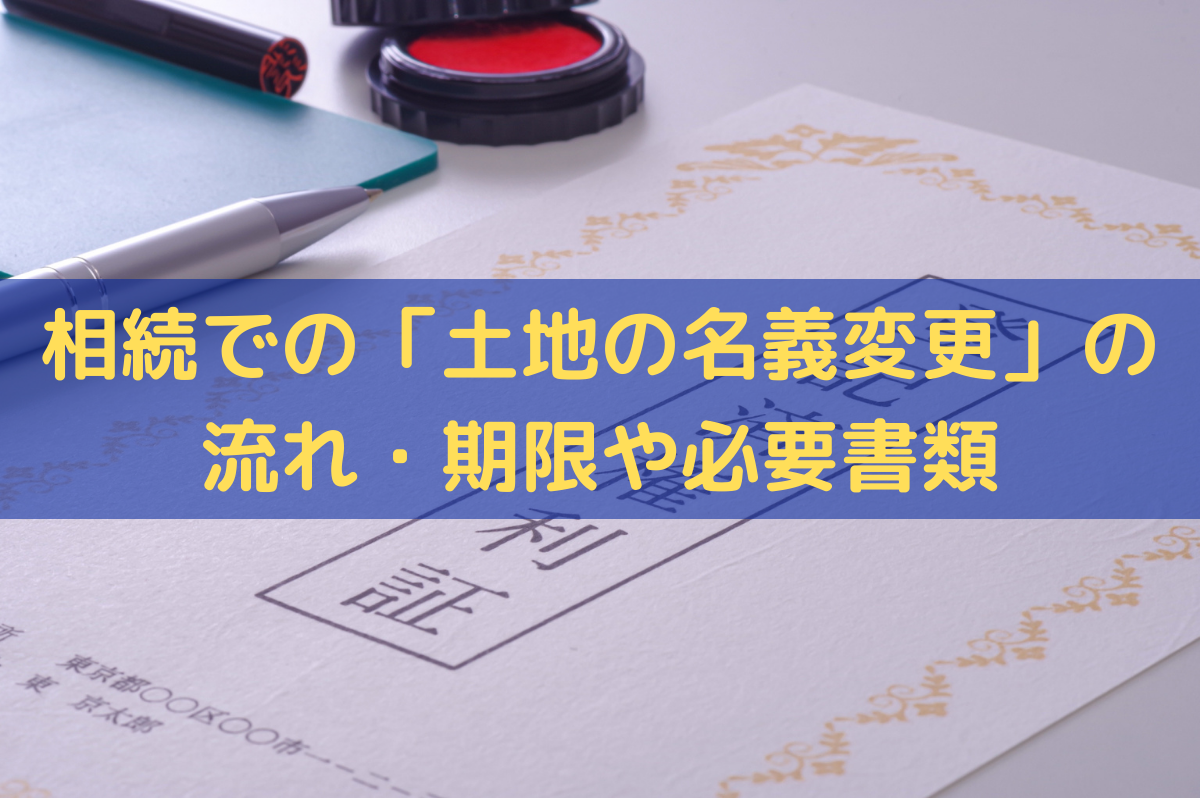土地の名義人に相続が起きると、その土地の名義変更をしなければなりません。この手続きを、「相続登記」といいます。
では、土地の名義変更(相続登記)は、どのような手順で進めていけば良いのでしょうか?今回は、相続登記の流れや必要書類などについて詳しく解説します。
目次
相続における土地の名義変更とは
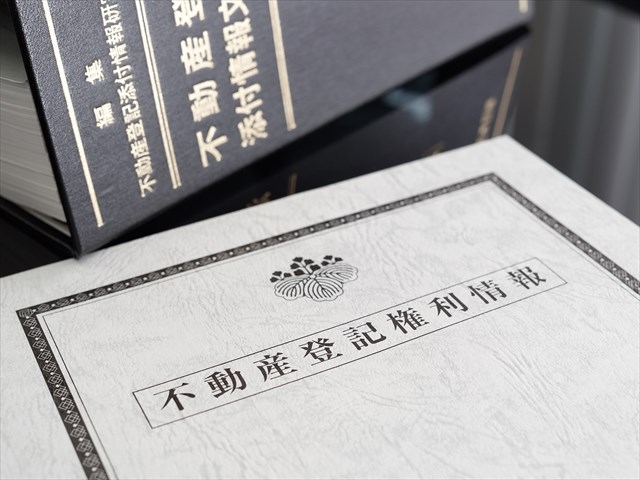
相続における土地の名義変更とは、故人名義となっている土地を相続人などの名義へと変える手続きです。この手続きを「相続登記」といい、法務局で手続きを行います。
故人名義のままでは土地を売却したり、お金を借りる際の担保として抵当権の設定をしたりすることができません。そのため、名義人が亡くなったら他の手続きの前提として、まずは相続登記をする必要があるのです。
土地の名義変更(相続登記)までの流れ

土地の名義人が亡くなったからといって、いきなり法務局へ出向いても手続きをすることはできません。土地の名義変更(相続登記)をするには、次のような手順を踏む必要があります。
- 土地の名義を相続する人を決める
- 必要書類を準備する
- 土地の名義変更(相続登記)をする
土地の名義を相続する人を決める
土地の名義変更(相続登記)をする前提として、まずはその土地を相続する人を決めなければなりません。土地を相続する人を決める方法には、主に次の2つがあります。
遺言
亡くなった人(「被相続人」といいます)が生前に遺言書を遺しており、その遺言書で土地の取得者が定められていたのであれば、原則として遺言書に記載されていた人が土地を取得します。この場合には、次で解説をする遺産分割協議は必要なく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
遺産分割協議
特に遺言書が遺されていなかった場合などは、遺産分割協議をして土地の取得者を決定します。遺産分割協議とは、相続人同士で行う遺産分けの話し合いのことです。相続人全員が同意するのであれば、遺産をどのように分けても構いません。
ただし、遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、たとえ相続人の中に認知症の人や行方不明の人がいたとしても、これらの人を無視して協議を成立させることはできません。
この場合には、成年後見人や不在者財産管理人などこれらの人の代わりに遺産分割協議に参加する人を、遺産分割協議に先立って家庭裁判所で選んでもらう必要があります。
また、遺産分割協議は多数決などではなく、全員が合意しなければ有効に成立させることはできません。仮に当人同士で協議がまとめられない場合には、調停へと移行することになります。
調停とは、調停委員立ち会いのもと、家庭裁判所で行う話し合いのことです。調停でも話し合いが成立しないのであれば、最終的に裁判所が決断をくだす審判手続きへと移行します。
必要書類を準備する
土地を取得する人が無事に決まったら、土地の名義変更(相続登記)をするために必要となる書類を準備します。必要書類は、後ほど詳しく解説します。
土地の名義変更(相続登記)をする
必要書類の準備ができたら、相続登記の申請をします。
申請先は土地の所在地を管轄する法務局
土地の名義変更である相続登記の申請先は、その土地の所在地を管轄する法務局です。どこの法務局へ申請しても良いわけではありませんので、事前に管轄をよく確認しておきましょう。
申請は窓口申請がおすすめ
登記を申請する方法には、次の3つがあります。
- 窓口で申請する
- 郵送で申請する
- オンラインで申請する
登記に不慣れな方ほど、窓口での申請をおすすめします。なぜなら、申請時に不備が見つかった場合、軽微な不備であればその場で修正できる可能性があるためです。
このうち、オンラインでの申請は、数回程度登記申請をするのみであればおすすめできません。オンライン申請をするにはパソコンの設定など様々な準備が必要となり、手間が余分にかかってしまう可能性が高いためです。
土地の名義変更(相続登記)はいつまでにすべき?

相続手続きの中には、期限のあるものが数多く存在します。たとえば、必要に応じて3ヶ月以内に行うべき相続放棄や、10ヶ月以内に行うべき相続税申告などです。
では、土地の名義変更(相続登記)には期限はあるのでしょうか?
期限はないがすみやかに
2021年現在、土地の名義変更(相続登記)には期限はありません。しかし、期限がないからといって放置することなく、できるだけすみやかに済ませておくべきでしょう。
その主な理由は、次のとおりです。
- 故人名義のままでは売却や抵当権設定などができない
- 権利が守られない可能性がある
- 長期間放置すればするほど手続きが煩雑になる
故人名義のままでは売却や抵当権設定などができない
土地が亡くなった人の名義のままとなっていては、その土地を売ることやお金を借りる際の担保である抵当権の設定をすることなどができません。たとえ今すぐには売却などの予定がなかったとしても、いずれ売却などをしようとした際には、まず相続登記をする必要が生じます。
売却しようとしたときに相続登記が未了では、相続登記に時間がかかり売却の機会を逸してしまうかもしれません。
権利が守られない可能性がある
せっかく相続などで名義を取得することが決まったにも関わらず、名義変更をしないままでは、いざというときに権利が守られない危険性があります。
たとえば、遺言書で長男が土地を相続することになっていたにも関わらず、名義変更を放置していると、その間に二男にお金を貸している債権者が二男の法定相続分だけを差し押さえて競売にかけてしまうかもしれません。
このような事態が生じれば、競売されてしまった部分を長男が取り返すことは困難です。土地の相続手続きを放置すると、このようなトラブルの原因となる場合があります。
長期間放置すればするほど手続きが煩雑になる
土地の相続登記は、相続が起きてから手続きするまでの期間が長ければ長いほど煩雑になる傾向にあります。なぜなら、手続きを放置する間に相続人の状況が変わってしまう可能性が高まるためです。
たとえば、元気であった相続人が認知症になってしまうと、成年後見人を選任するなどしなければ原則として手続きを進めることができません。また、相続人の中に亡くなる人が生じる可能性もあります。
代替わりが起きて相続人が増えれば、それだけ相続をまとめることが難しくなってしまうでしょう。
改正により2024年度以降は3年以内に
2024年度以降は、相続登記に期限が設けられることが決まっています。これは、相続登記がされないまま放置され、もはや所有者が誰なのかわからない「所有者不明土地」の増加が社会問題になったことで、不動産登記法などの法律が改正されたためです。
改正法が施行される2024年度以後は、土地の取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎた場合には10万円以下の過料の対象となりますので、今後は期限にも注意をして手続きを進めるようにしましょう。
土地の名義変更(相続登記)の必要書類

土地の名義変更(相続登記)には、さまざまな書類が必要です。ここでは、遺産分割協議で土地の取得者を決める場合の一般的な必要書類を紹介します。
必要書類は状況によって異なる場合がありますので、登記申請の前に法務局の登記相談などで確認をすると安心です。
- 登記申請書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 被相続人の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 土地の名義を相続する人の住民票
- 固定資産税評価証明書または固定資産税通知書
登記申請書
登記申請書は、土地の名義変更(相続登記)のメインとなる書類です。原則としてこの申請書の記載どおりに登記がされることとなりますので、間違いのないよう慎重に作成する必要があります。
登記申請書は、預貯金などの相続手続き書類などとは異なり、穴埋め形式で作成するものではありません。自分で一から作成する必要があります。
基本的なケースであれば法務局のホームページに記載例が載っていますので、こちらを参考にして作成すると良いでしょう。ある程度作成できたら、申請の前に法務局の登記相談を予約して確認してもらうと安心です。
遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果をまとめた書類です。誰がどの土地を取得することになったのかが分かるよう、明確に記載してください。
記載があいまいな場合には、登記ができない可能性があります。土地は、全部事項証明書(登記簿謄本)を参考に、次の事項を記載して特定することが一般的です。
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
また、相続人全員が協議内容に納得していることの証拠として、相続人全員が実印で捺印を行います。
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押した印が実印であることの証明として、相続人全員の印鑑証明書を添付します。印鑑証明書は住所地の市区町村役場で取得できる他、最近ではマイナンバーカードを持っていればコンビニエンスストアなどから取得できる市区町村も少なくありません。
取得にかかる手数料は市区町村によって異なりますが、1通200円から400円程度であることが一般的です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
被相続人の相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本を添付します。これらはそれぞれ、被相続人がその時点で本籍を置いていた市区町村役場で取得できます。
手数料は全国一律で、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本と原戸籍謄本は1通750円です。なお、相続人が兄弟姉妹や甥姪などである場合には、これらに加えて被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も必要となります。
郵送での請求方法
請求先の役所が遠方であるなどの理由で窓口へ出向くことが難しい場合には、郵送で取り寄せることも可能です。その場合には、次のものを送付して請求します。
- 戸籍等の請求用紙:市区町村のホームページからダウンロードして必要事項を明記します
- 定額小為替:戸籍謄本などの代金を支払うために必要となる金券です。最寄りの郵便窓口で購入できます
- 本人確認書類:請求者の運転免許証などのコピーを同封します
- 返信用封筒:返送先を明記し必要分の切手を貼付します
なお、場合によっては請求の対象者と請求者との関係性を示す戸籍謄本などのコピーの添付を求められる場合もあります。
被相続人の除票
登記名義人と被相続人との同一性を示すため、被相続人の除票が必要です。除票は、被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。費用は市区町村によって異なりますが、1通200円から400円程度です。
相続人全員の戸籍謄本
相続人の生存を確認するため、相続人全員の戸籍謄本が必要です。それぞれ本籍地のある市区町村役場で取得しますが、マイナンバーカードを持っていることを条件にコンビニエンスストアなどで取得できる市区町村が増えています。
手数料は、全国一律で1通450円です。
土地の名義を相続する人の住民票
新たな所有者の情報を正しく登記するため、土地の名義を取得する人の住民票が必要です。住民票は、住所地の市区町村役場で取得できますが、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアで取得できる市区町村が増えています。
取得にかかる手数料は市区町村によって異なりますが、1通200円から400円程度であることが一般的です。
固定資産税評価証明書または固定資産税通知書
登記申請をする際には、登録免許税という税金を支払わなければなりません。この登録免許税の額を正しく計算するために、名義変更しようとする土地の固定資産税評価証明書が必要です。
固定資産税評価証明書は、土地の所在地の市区町村の窓口で取得します。窓口の名称は「税務課」や「固定資産課」など、市区町村によってさまざまです。
取得手数料は1通300円程度であることが多いですが、無料で取得できる「固定資産税通知書」を発行している市区町村もあります。あらかじめ請求先の市区町村へ確認すると良いでしょう。
土地の名義変更にかかる費用はどのくらい?

土地の名義変更(相続登記)をするには、「登録免許税」と「必要書類の取得費用」がかかります。この2つは、自分で相続登記手続きをした場合であっても司法書士へ手続きを依頼した場合であっても、同様にかかる費用です。
司法書士へ相続登記手続きを依頼した場合には、これらに加えて専門家報酬が別途かかります。では、それぞれどのくらいの金額となるのか、くわしく解説しましょう。
司法書士報酬
土地の相続登記手続きを依頼した場合の司法書士報酬は、おおむね6万円から10万円程度です。ただし、司法書士報酬は法律などで定められているわけではなく、それぞれの事務所が個別で定めているため、必ずしもこの範囲内であるとは限りません。
また、報酬の計算方法も事務所ごとに異なっています。たとえば、相続登記をする土地の数が多かったり相続人の数が多かったりした場合などに、報酬が加算されることが多いでしょう。
事務所によっては、遺産分割協議書の作成や必要書類の収集から依頼した場合に報酬が加算される場合もあります。司法書士報酬を正確に知るためには、相続登記の依頼を検討している事務所に個別で見積もりを依頼することが必要です。
登録免許税
登録免許税とは、相続登記の申請をするに際して法務局で納めるべき税金です。相続に伴う土地の名義変更にかかる登録免許税は、原則として次のように計算されます。
- 登録免許税額(相続)=土地の固定資産税評価額×4/1,000
たとえば、相続登記をする土地の固定資産税評価額が2,000万円である場合の登録免許税は8万円、固定資産税評価額が4,000万円である場合の登録免許税は16万円ということです。
土地の固定資産税評価額が高額であれば登録免許税も高額となりますので、どの程度の登録免許税がかかるのか、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
なお、相続人ではない人が遺言で土地を受け取ったこと(「遺贈」といいます)に伴い土地の名義変更手続きをする場合の登録免許税は次のとおりです。
- 登録免許税額(遺贈)=土地の固定資産税評価額×20/1,000
たとえば、土地の固定資産税評価額が2,000万円である場合の登録免許税は40万円、固定資産税評価額が4,000万円である場合の登録免許税は80万円にもなります。遺贈の場合には、通常の相続よりもさらに高額な登録免許税がかかるため注意しましょう。
必要書類の取得費用
先ほどお伝えしたように、土地の名義変更である相続登記をするためには、さまざまな書類が必要となります。必要書類の取得にかかる費用は、相続人が子などの場合でおおむね1万円程度となることが一般的です。
また、相続人が兄弟姉妹や甥姪である場合には必要書類が多くなる傾向にあるため、2万円から3万円程度となることが多いでしょう。ただし、被相続人が転籍を繰り返している場合や相続人の数が多い場合などには、これ以上の費用がかることもあります。
土地の名義変更を行う方法と選び方
土地の名義変更を行う方法は、「自分で行う方法」と「司法書士へ依頼する方法」の2つが存在します。どちらを選択するべきであるのかは、それぞれ次のとおりです。
自分で名義変更をする
相続における土地の名義変更は、自分で行うことも選択肢の一つとなります。自分で名義変更を行うことで、司法書士報酬分の費用を節約することが可能です。
ただし、相続による土地の名義変更は、さほど簡単なものではありません。自分で行うのは、次の条件をすべて満たした場合のみにしておくと良いでしょう。
- 平日の日中に何度も時間が取れる
- 調べながら書類の作成や収集ができる
- 土地の名義変更を特に急いでいない
- 専門家のアドバイスを必要としていない
- 特殊な相続ではない
平日の日中に何度も時間が取れる
土地の名義変更の手続き先や事前相談先である法務局は、平日の日中しか開庁していません。また、必要書類のうち多くの取り寄せ先である市区町村役場も、原則として平日日中のみの開庁です。
そのため、自分で土地の名義変更をするには、平日の日中に何度も時間が取れることが必要となります。
調べながら書類の作成や収集ができる
土地の名義変更に必要な書類を問題なく作成したり必要書類を漏れなく集めたりすることは、慣れていないと容易なことではありません。
そのため、一つずつ調べながら書類の作成や収集をする必要があります。このようなことが苦手な場合には、自分で土地の名義変更をすることは困難でしょう。
土地の名義変更を特に急いでいない
自分で土地の名義変更をする場合には、司法書士へ依頼した場合と比較して、完了までに時間がかかる傾向にあります。なぜなら、一つずつ調べながら進めていく必要があるうえ、申請後も法務局から補正(修正)が入る可能性が高いためです。
そのため、土地の名義変更の完了を急ぐ場合には、自分で行うことはおすすめできません。
専門家のアドバイスを必要としていない
相続において土地の名義変更をするにあたっては、たとえば争いのない相続において「土地を誰の名義にすべきか?」など、専門家のアドバイスを受けたい場合もあることでしょう。このような場合には、はじめから司法書士へ土地の名義変更手続きを依頼すべきです。
法務局では登記手続きの相談には乗ってくれるものの、原則として、登記の前段階となるこのような相談へは乗ってもらえません。
特殊な相続ではない
特殊な相続である場合には、自分で名義変更を完了させることはより困難です。この場合には、司法書士へ依頼した方が良いでしょう。
特殊な相続とは、たとえば土地が最近亡くなった父の名義ではなく、父よりも前に亡くなった祖父(父の父)名義となっている場合などです。
司法書士へ依頼する
相続による土地の名義変更を司法書士へ依頼すれば、司法書士報酬分の費用が追加でかかります。しかし、この場合には自分でさまざまな書類を取得したり書類を作成したりする必要はないため、時間や労力を大きく削減することができるでしょう。
また、自分で行うよりも早くスムーズに手続きが完了する可能性が高い他、手続きの漏れやミスなどを防ぐことも可能となります。これらのメリットを享受したい場合には、司法書士へ依頼すると良いでしょう。
自分で土地の名義変更を行う際の手順
自分で土地の名義変更を行う際の一般的な手順は、次のとおりです。
- 誰が土地を相続するかを決める
- 土地の名義変更に必要となる書類を準備する
- 土地の名義変更登記を申請する
誰が土地を相続するかを決める
はじめに、土地を誰が相続するのかを決める必要があります。
土地を相続する人を決める基本の方法は、相続人全員の話し合いである「遺産分割協議」です。遺産分割協議がまとまったら、その結果を記した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名と実印での捺印を行います。
亡くなった人(「被相続人」といいます)が有効な遺言書を遺していた場合には、遺産分割協議ではなく、遺言書の内容で土地の取得者が決まります。
土地の名義変更に必要となる書類を準備する
相続で土地の名義変更をするためには、上で解説をしたとおり、さまざまな書類が必要となります。自分で土地の名義変更をする場合には、これらの書類も自分で集めることが原則です。
土地の名義変更登記を申請する
必要書類の準備ができたら、土地の名義変更登記(相続登記)を申請します。登記の申請先は、その土地の所在地を管轄する法務局です。登記申請の方法としては、窓口へ持参する方法の他、郵送で行う方法があります。
なお、オンライン申請制度もありますが、オンライン申請をするためには周辺機器やシステムの設定などが必要となるため、自分や家族の登記を数回おこなう程度であればおすすめできません。
司法書士に依頼して土地の名義変更を行う際の手順
司法書士へ依頼して土地の名義変更を行う際の一般的な手順は、次のとおりです。
- 依頼先の司法書士を選定する
- 誰が土地を相続するかを決める
- 司法書士にて書類の作成や収集を行う
- 司法書士から指定された書類に署名や捺印をする
- 司法書士が土地の名義変更登記を申請する
依頼先の司法書士を選定する
はじめに、依頼先の司法書士を選定するところからスタートです。選定にあたっては、依頼することができる範囲や報酬などを事前にしっかりと確認すると良いでしょう。
誰が土地を相続するかを決める
次に、誰が土地を相続するのかを決めます。この段階は、自分で土地の名義変更を行う場合と変わりません。
ただし、司法書士へ依頼した場合には、遺産分割協議の前段階となる相談には乗ってもらえることが多いでしょう。たとえば争いのない相続において、「土地を被相続人の配偶者名義とすべきか、子の名義とすべきか」などです。
司法書士にて書類の作成や収集を行う
司法書士へ土地の名義変更を依頼した場合には、必要となる書類の収集は、司法書士にて行ってくれることが多いでしょう。
ただし、印鑑証明書を代行取得するためには印鑑カードなどを預かる必要がありますので、これのみは自分での取得が必要となることが一般的です。
司法書士から指定された書類に署名や捺印をする
次に、司法書士が作成した必要書類に、署名と捺印をします。自分で一から書類を作成する必要はありませんので、安心です。
司法書士が土地の名義変更登記を申請する
司法書士へ依頼した場合には、司法書士が土地の名義変更登記を申請します。自分で法務局へ申請に出向く必要はありません。
まとめ
土地の名義変更である相続登記の手続きには、さまざまな書類が必要となります。
中でも、除籍謄本などはあまり見たことがないという方も多く、すべてを揃えるには非常に手間がかかってしまうことでしょう。
相続登記の手間を削減したいもののできるだけ費用は抑えたいという場合には、そうぞくドットコムの利用がおすすめです。