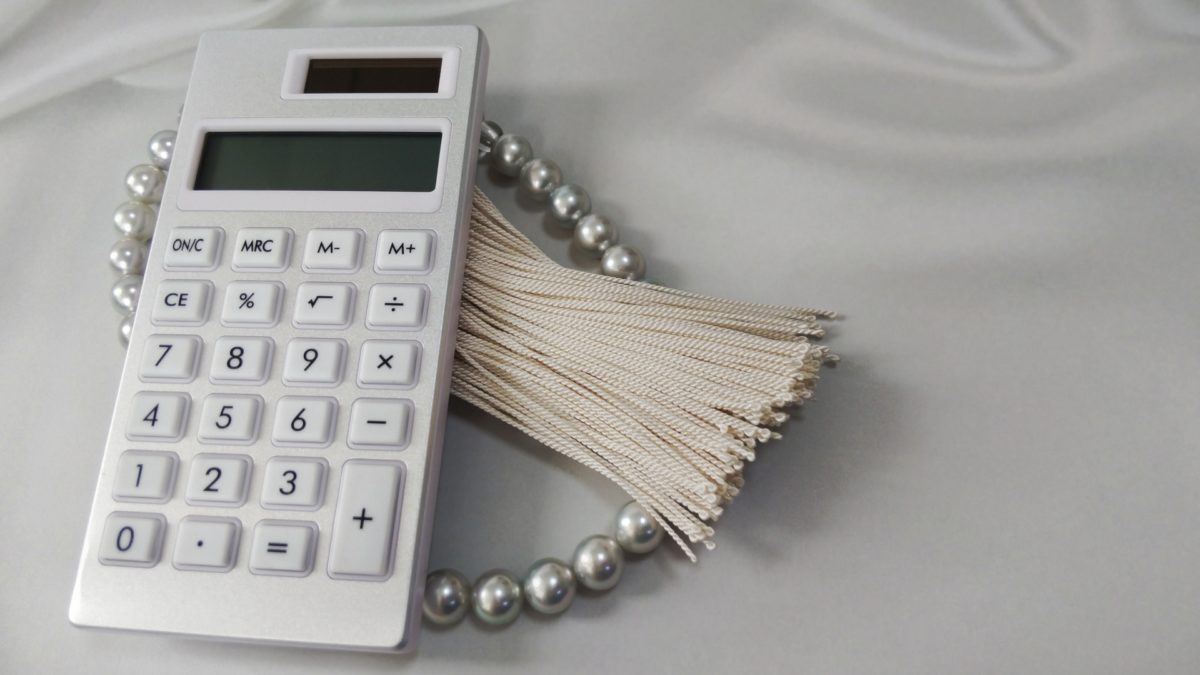故人を丁重に弔い見送るための葬儀には、高額な費用が必要です。
そのため、「できれば事前にある程度の金額を把握しておきたい」「費用が抑えられる方法が知りたい」といった希望がある人も少なくありません。
そこで今回は、葬儀費用の平均的な金額・内訳・費用を抑えられる方法や、葬儀費用で多い疑問点について詳しく解説します。
【形式別】葬儀にかかる平均的な費用

葬儀にかかる平均的な費用は、どのような葬儀形式を行うかによって異なります。
ここでは、葬儀にかかる平均的費用を形式別に分けてお伝えします。
検討している葬儀形式と照らし合わせて確認してください。
- 一般葬:150万円〜200万円
- 家族葬:70万円〜100万円
- 一日葬:40万円〜60万円
- 直葬・火葬式:15万円〜20万円
一般葬:150万円〜200万円
一般葬とは、日本で昔から行われてきたスタンダートな形式の葬儀です。
参列者数の制限はなく、お通夜・告別式と二日に分けて葬儀が行われます。
一般葬では、少なくても50人以上、多ければ100人を超える参列者が訪れるため、葬儀会場も大きくそれ見合った設えや通夜振る舞い・精進落としの準備をしなければなりません。
したがって、平均費用は低く見積もっても150万円、多ければ200万円近くの金額が必要です。
家族葬:70万円〜100万円
家族葬は、近年注目されるようになった小規模葬の一つです。
小規模葬とは、一般葬よりも小さな会場を用意し少人数で行われる葬儀のことで、家族葬の場合は最大でも30人ほどの規模になります。
故人の遺族・親族を中心に、ごく親しい人だけでひっそりと行われる葬儀なので、お通夜・葬儀を合わせても平均費用は70万円〜100万円です。
一日葬:40万円〜60万円
一日葬とは、簡単にいうと告別式だけを行う形式の葬儀です。
お通夜を行わないため日程が短く、体力的に不安が多い高齢者や、仕事でなかなか時間が取れない遺族に注目されています。
一日葬の平均費用は、葬儀日程が短い分会場を借りる時間が短縮されるため、平均費用が40万円〜60万円とかなり抑えられた金額です。
ただし、告別式だけという形式を受け入れられない地域や葬儀社も多く、一日葬を希望する場合は事前に葬儀社へ相談し、取り扱いがある葬儀社へ依頼しなければなりません。
また、参列者に制限がなければその分大きな会場を借りることになりますので、費用を抑える目的で検討している人は参列者数まで考慮しましょう。
直葬・火葬式:15万円〜20万円
直葬・火葬式は、お通夜・告別式がなく火葬だけが行われる形式の葬儀です。
簡単な設えと棺だけが用意され、一晩故人を見守った後すぐに遺体が火葬されます。
直葬・火葬式は、葬儀の中でも必要最低限な形式なので、集まる人もごく身内のみで実費しか掛かりません。
平均費用も、各葬儀形式の中で一番低く15万円〜20万円です。
しかし、平均費用が安くでもあまり小さな葬儀形式にすると、呼ばれなかった親族や友人・知人から苦言を述べられることもあります。
費用だけではなく、故人の立場まで考えた葬儀形式を選びましょう。
葬儀費用の内訳

葬儀では、会場から供花・供物まで、さまざまなものを準備します。
準備の際に掛かった金額はすべて葬儀費用に計上されるので、少しでも費用を抑えたい場合は葬儀費用の内訳をよく知ることが大切です。
ここでは、葬儀に掛かる一般的な費用の内訳を詳しく解説していきます。
- 会場費用
- 控室の費用
- 祭壇費用
- 白木の位牌費用
- 仮祭壇費用
- 棺費用
- 仏具一式・死装束・棺掛け費用
- 供花・供物費用
- 骨壷費用
- ドライアイス費用
- 遺体搬送費用
- 飲食費用
- 会葬礼状・会葬御礼品費用
会場費用
会場費用は、葬儀を行うための場所を借りるときに必要な経費です。
会場の大きさは葬儀形式によって異なり、30人程度の小規模な部屋から、50人以上が集まれる広い部屋まで、参列者の人数に合わせて選べます。
故人が社会的地位を持っていたり、交友関係が広く100名以上の参列者が予測されたりする場合は、葬儀場ではなく広い会館を借りなければなりません。
参列者の人数に合わせて会場の広さを決めますので、葬儀形式と参列者の人数をあらかじめ予想しておきましょう。
控室の費用
葬儀場の控室は、遺族が待機したりお通夜で泊まる際に必要です。
お通夜では、一晩中線香を切らさないよう見守らなければならないため、遺族が仮眠したり着替えたりするために利用します。
控室の費用は泊まる人数や部屋数によって異なるため、泊まる人数を葬儀社伝えて相談し、適切な広さの部屋を選びましょう。
祭壇費用
故人の遺影や白木の位牌を設え、花などを飾ってお参りするための場所が祭壇です。
祭壇には、白木祭壇・花祭壇といった種類があり、使われる花が造花か製菓によっても費用が異なります。
また、会場の広さによって祭壇の大きさが変わることもあり、どの祭壇にするかは葬儀の規模や会場の広さに合わせなければなりません。
祭壇費用は、高いものになると100万円以上するものもありますが、会場との兼ね合いや規模に合わせて選ぶと良いでしょう。
白木の位牌費用
白木の位牌は、故人の葬儀から49日を迎えるまでの間、本位牌を用意するまで必要です。
白木の位牌は本位牌よりも大きく、僧侶に戒名を書いていただきます。
本位牌が用意できるまでは、白木の位牌を祭壇に安置して供養をしましょう。
仮祭壇費用
仮祭壇とは、葬儀終了後から四十九日を迎えるまで、一時的に遺骨を安置して供養をするための祭壇で、後飾り祭壇とも呼ばれます。
仮祭壇は故人の自宅に設置するものなので、葬儀社と相談して設置場所を決め、組み立ててもらうようにしてください。
お仏壇がある場合はそちらに安置しても良いですが、四十九日を迎えるまでは弔問客から供花や供物をいただくこともあります。
いただいたものが飾れるよう、仮祭壇をお願いした方が良いでしょう。
棺費用
遺体を納める棺は、故人の体の大きさや材質・作りによって費用に違いがあります。
最近では、環境問題や遺体の状態を踏まえた上で、次のような棺が利用されるケースが増えてきました。
| 棺の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 木棺 | 木材を使用したスタンダードな棺。ヒノキ・桐・加工板などの素材があり、彫刻をほどこしたりプリント装飾されたものもある。 |
| 布棺 | 周囲に布を貼り付けた棺。カラーが豊富で、刺繍や模様が施されたものもある。 |
| エコ棺 | 間伐材や段ボールを使用した棺。二酸化炭素の排出量が軽減され、環境への影響が考えられている。 |
| エンバー棺 | 長期保存するためにエンバーミング処理された遺体を納める棺。アクリル素材で作られており、ドライアイスを使わず遺体を納められる。 |
すべての葬儀社で取り扱いがあるわけではありませんが、故人らしさを出したり遺族の意向で、さまざまな種類の棺が選ばれています。
費用との兼ね合いも考慮して、適切な棺を選んでみましょう。
仏具一式・死装束・棺掛け費用
葬儀費用の内訳の中で、細かく確認しなければならないのが「仏具一式」「死装束」「棺掛け」の費用です。
仏具一式には、線香や焼香、りん、ろうそくといった、お参りに必要な道具が揃っており、手元にあるようなら頼む必要はありません。
死装束は、故人に着せる旅立ちの服装ですが、故人の遺言や遺族の意向で着せたい洋服があるのなら、そちらを着せて棺に納めても問題ありません。
棺掛けとは、棺の上に掛ける布のことで、仏式では僧侶の袈裟と同じ布、神式では白い布、キリスト教では黒い布を棺に掛けます。
仏具一式や死装束、棺掛けの費用は、手持ちの有無や宗教の違いによって異なりますので、詳細をよく見て判断してください。
供花・供物費用
供花や供物は、葬儀や自宅の仮祭壇に飾られるお供物です。
供花には、花輪や花スタンド、花籠などがあり、葬儀の規模や会場の大きさに合わせて遺族が用意したり、参列者からいただいた供物を飾ったりすることもあります。
最低でも喪主・子供・孫名義の花スタンドや親族名義の花飾りが必要なので、遺族・親族で話し合って頼むようにしてください。
骨壷費用
骨壷は、火葬した故人の遺骨を納めるための壺です。
骨壷には種類があり、目的によって大きさを選んで用意します。
具体的な大きさと種類は以下のとおりです。
| 骨壺の大きさ | 種類 |
|---|---|
| 2寸・2.3寸・3寸・4寸 | 手元供養や分骨に適した大きさの骨壷 |
| 5寸・6寸・7寸 | 一般的な納骨をするための骨壷 |
| 8寸・尺寸 | 複数人の遺骨を一緒に納めるための骨壷 |
どの骨壷を選ぶかで費用は異なります。
火葬後の供養方法も考え、必要な骨壷を選んでみましょう。
ドライアイス費用
ドライアイスは、故人の遺体の腐敗防止を目的として使用されます。
平均すると一回の使用で約10kg、一日保存するために20kg〜30kg必要ですが、夏場はこの倍を用意しなければなりません。
また、火葬場の予約が取れず火葬日まで時間が空く場合は、延びた日程分のドライアイスも必要です。
ドライアイスの費用は、使用する日程の長さや季節によって変わることを覚えておきましょう。
遺体搬送費用
遺体の搬送費用は、送迎距離で計算されます。
例えば、10kmなら1万2千円、20kmなら1万5千円、30kmなら1万7千円という感じです。
また、混んでいる時間帯はその分の金額がプラスされることもあり、費用はそれぞれの葬儀社によって異なります。
ある程度の目安が知りたい場合は、各葬儀会社に問い合わせてみましょう。
飲食費用
飲食費用は、通夜振る舞いや精進落としなど、参列者への接待で必要です。
参列者数に比例しているので、小規模葬なら安く、一般葬の中でも大きい葬儀なら高くなる傾向があります。
参列者数が少ない場合は一人一席を設けても良いですが、全体的な人数がわからない場合はオードブルなどで対応してみましょう。
会葬礼状・会葬御礼品費用
会葬礼状・会葬御礼品は、葬儀に参列したいただいた方にお礼として渡すものです。
一般葬では参列者数がはっきりしないため、多めに頼んで少し余るようにしておき、後日弔問客に渡すこともあります。
自分たちで用意する場合も、多めに頼んでおくと急なお返しに困ることがありません。
会葬御礼品は、消えものと呼ばれるお茶・のり・お菓子、ハンカチやタオルといった軽い品物を用意します。
費用は用意する数で変わりますので、葬儀の形式や規模に合わせて必要な数を揃えましょう。
葬儀費用を抑えるポイント

葬儀費用は金額的に負担が大きいので、できれば抑えたいという人も多いことでしょう。
では、具体的にどのようにして抑えれば良いのか、そのポイントをお伝えしましょう。
- 費用の内訳を確認して不要なものを省く
- 小規模葬を行う
- 会場を借りる日程を短くする
費用の内訳を確認して不要なものを省く
葬儀費用は、内訳をよく見ていくと、不要なものまでセットになっていることがあります。
先ほどお伝えしたように、死装束や仏具などが揃っているのであれば、改めて頼む必要はありません。
葬儀を小規模葬で行うのなら、会場の広さと内訳の金額を確認し、適切な広さの会場をお願いすることもできます。
葬儀社と契約する前には見積書をよく見て、内訳を確認し不要なものを省いてみましょう。
小規模葬を行う
あらかじめ費用の予算が決まっているなら、最初から小規模葬で行うことも一つの手です。
例えば、50万円ならすぐ用意できるという場合は一日葬、100万円なら小さな家族葬というように、費用に合わせて葬儀形式を選びます。
予算内で済むのなら、後からお金を用意する必要はありません。
目安になる予算がはっきりしている場合は、それに合わせた小規模葬を検討してみましょう。
会場を借りる日程を短くする
葬儀費用の中で大きな割合を占めるのが、会場を借りる費用です。
遺体の安置から葬儀日まで借りるとすると最低でも3日、火葬場の予約が取れなければそれ以上掛かることもあります。
遺体の安置は自宅、お通夜と葬儀の日だけ会場を利用する場合であれば、費用は2日分しかかかりません。
さらに、一日葬ならその日だけの費用で済みます。
葬儀費用を抑えたいと考えており、自宅での安置や一日葬が可能という方は、会場を借りる日程を短くすると良いでしょう。
葬儀費用でよくある疑問

葬儀費用は、なかなか経験しない事柄に関するお金なので、その扱い方や万が一のときの不安を抱える方も少なくありません。
ここでは、葬儀費用でよくある疑問とその答えをお伝えします。
困ったときの参考にしてください。
葬儀費用は誰が払う?
葬儀費用で意外に多いのが、「誰が費用を払うのか?」という疑問です。
結論からお伝えすると、葬儀費用を支払う人に決まりはありません。
ただし、一般的には故人に近しい遺族・親族が払うケースがほとんどです。
具体的な例は次のとおりなので、こちらを参考にして話し合うと良いでしょう。
喪主
喪主は、故人の配偶者や子供など一親等内の人が該当するため、葬儀社も喪主に費用を相談することが多いです。
ただし、喪主となる人が高齢だった場合は、その子供や親族が喪主に変わって対応することもあります。
施主
施主は葬儀の流れそのものを支持する立場にある人なので、葬儀費用の支払いまで担当することがあります。
ただし、施主となっている人が故人からみて三親等以上である場合は、葬儀費用の話し合いだけ請け負って、支払いを喪主やその子供に任せる方が良いでしょう。
喪主に近しい親族
喪主とその家族に支払える能力がない場合は、喪主に近しい親族が払うこともあります。
この場合、もし後から生命保険や相続でお金が用意できそうなら、立て替えてくれた親族にお返しした方が良いでしょう。
相続人で分担する
遺産が相続されることを考えて、相続人で分担して葬儀費用を払うという人もいます。
分担すれば負担が軽減されますし、相続する際に配分で揉めるリスクも減ることでしょう。
葬儀費用が払えない時は?
預貯金がない状態だと、葬儀費用が払えないというケースもあります。
このような場合は、次のような方法で払うようにしましょう。
葬儀ローンを利用する
葬儀ローンは、葬儀費用を分割支払いするための仕組みです。
近年では、カード会社と提携している葬儀会社も増えてきており、小規模葬の費用をカードで支払うという人もいます。
カードがなくても分割払いできることもありますので、葬儀会社に相談してみてください。
死亡保険金から支払う
故人の死亡保険金が入るのなら、葬儀会社に相談して支払日にちを決め、保険金が入り次第払う方法もあります。
ただし、死亡保険金は入るまでに最低でも1〜2ヶ月かかるので、死亡保険金から払う予定の場合は早めに手続きしてください。
葬祭扶助制度を利用する
生活保護を受けており、葬儀の費用を工面できないという場合は、葬祭扶助制度を利用しましょう。
葬祭扶助制度は、最低限の葬儀ができる費用を負担してもらえる制度で、お金が下りるのではなく、町村役場が負担する形式です。
ただし、具体的な金額は10万円ほどなので、火葬のみの葬儀になることを理解しておきましょう。
葬儀費用は確定申告できる?
葬儀費用は、確定申告できません。
葬儀費用を申告することで軽減されるのは、相続税です。
例えば、葬儀費用200万円を支払った人が1,000万円相続した場合、200万円を申告すれば、その分の相続税が軽減されます。
まとめ
葬儀費用は金額が大きいため、内訳や平均金額、費用を抑えるポイントを知ることが大切です。
葬儀形式や規模によっても費用に違いがあるので、事前によく調べてみてください。