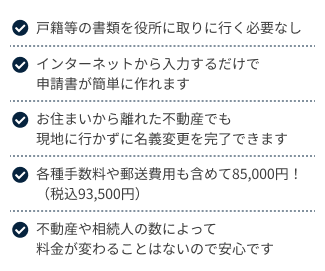相続税の計算は、複雑でわかりにくいと感じている方も少なくないものです。
今回は、事例を使って相続税の具体的な計算方法を紹介するともに、申告不要の判断方法などについても詳しく解説します。
相続税はすべての人にかかる税金?

相続税と聞くと、何となく「高くて怖い税金」だと感じている方も少なくないようです。
しかし、相続税はすべての人にかかる税金ではありません。
まずは、相続税がかかる人の割合やどのような人に相続税がかかるのかについて解説しましょう。
相続税とは
相続税とは、亡くなった人から相続や一定の生前贈与などにより取得した財産に対してかかる税金です。
相続税がかかる場合には、相続などで財産を受け取った人が納税をしなければなりません。
相続税がかかる人の割合
相続がかかる人の割合は、実はそれほど多くはありません。
国税庁が公表しているデータによれば、相続税がかかる相続の割合はおおむね8%前後で推移しています。
つまり、亡くなった方が100名いれば、そのうち90件以上では相続税はかからず、数件のみに納税義務があるという状況です。
なお、これは全国平均での割合です。
東京などの地価の高い地域では、自宅不動産を持っているだけで財産額がかさむため納税対象者は比較的多く、地価の低い地域では納税対象者の割合は比較的低いといえるでしょう。
また、相続税は2015年に大改正がされました。
この改正以前の納税対象者はおおむね4%程度で推移しており、改正により倍増しています。
相続税がかかるのはどんな人?
相続税がかかるかどうかは、次のように判断できます。
- 課税価格の合計額>相続税の基礎控除額:相続税がかかる
- 課税価格の合計額≦相続税の基礎控除額:相続税がかからない
つまり、課税価格の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合に相続税がかかるということです。
相続税の基礎控除額や課税価格の合計額の計算方法や考え方については、後ほど詳しく解説します。
相続税の計算方法を具体例で解説

ここでは、具体例を出しながら、相続税の計算方法について解説します。
父が亡くなり、父の配偶者である母と長男、長女の3名が相続人である場合で計算してみましょう。
課税価格の合計額を計算する
まずは、課税価格の合計額を計算します。
課税価格の合計額とは、大まかに言えば相続税の対象となる財産のことだと考えてください。
課税価格の合計額は、次のように計算をします。
- 相続や遺贈によって取得した財産の価額を合計する
- ①に、相続時精算課税の適用を受けて贈与を受けた財産の価額を合計する
- ②から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出する
- 遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算する
それぞれ、下記で補足します。
相続や遺贈によって取得した財産
土地や建物、預貯金、有価証券などのいわゆる相続財産がここに計上されます。
仮に、この合計が1億8,000万円だったとしましょう。
土地の評価が最大8割減で評価できる「小規模宅地等の特例の適用」を受ける場合には、この段階で加味します。
また、亡くなった人が保険料を支払っていた生命保険金や会社などから支給される死亡退職金は、民法上の相続財産ではないものの、相続税の対象となります。
相続税法の規定により相続財産とみなすこととされているためです。
なお、相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金にはそれぞれ「500万円×法定相続人数」の非課税枠があるため、非課税枠を控除した残りがあれば、その残った金額だけが加算されます。
例えば、長男のみが3,300万円の生命保険金を受け取った場合には、次のようになります。
- 相続人が受け取った生命保険金の合計額:3,300万円
- 生命保険金の非課税限度額:500万円×3名=1,500万円
- 相続税の課税対象となる生命保険金:3,300万円−1,500万円=1,800万円
- 相続や贈与によって取得した財産の合計額:1億8,000万円+1,800万円=1億9,800万円
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産
相続時精算課税とは、要件を満たして税務署へ一定の届出を行うことにより、累計2,500万円までの贈与に対する贈与税が非課税となる制度です。
その代わりに、相続時精算課税制度の特例を受けて贈与を受けた財産の全額が相続税の対象となります。
そのため、相続時精算課税制度の適用を受けていた場合は、課税価格の合計額の計算に含める必要があるのです。
当然ながら無自覚のうちに相続時精算課税制度が適用されていることは考えづらく、適用を受けている以上は税理士へ相談したり一定の手続きをしたりしているはずですので、相続時精算課税制度の適用を受けている場合のみ注意すれば良いでしょう。
例では、相続時精算課税制度は使っていないものとします。
債務控除や葬儀費用
亡くなった人に未払費用や借入金があった場合には、未払費用や借入金相当額を課税対象となる財産から控除することができます。
また、実際にかかった葬儀費用も控除が可能です。
例の場合には、700万円の借入金があり、300万円の葬儀費用がかかっていたとします。
この場合、課税価格の合計額の計算上、控除できる金額は1,000万円(=700万円+300万円)です。
相続開始前3年以内の贈与財産
相続などにより財産を取得した人が相続開始以前3年間に贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産の額は相続税の対象となります。
亡くなる直前に急いで贈与をするなどして、相続税逃れをすることを防ぐためです。
相続時精算課税制度を使った贈与は何年前のものであってもすべて加算するのに対し、相続時精算課税制度を使っていない通常の贈与は過去3年分のみを加算しますので、この違いにも注意しましょう。
例の場合には、対象となる贈与は特になかったものとします。
課税価格の合計額の計算
ここまでのことを踏まえて課税価格の合計額を計算すると、次のようになります。
課税価格の合計額=1億9,800万円(相続や遺贈によって取得した財産)+0円(相続時精算課税の適用を受けた贈与財産)−1,000万円(債務控除や葬儀費用)−0円(相続開始前3年以内の贈与財産)=1億8,800万円
相続税の基礎控除額を引いて課税遺産総額を計算する
次に、前で計算をした課税価格の合計額から相続税の基礎控除額を控除して、課税遺産総額を計算します。
相続税の基礎控除額の計算方法は、次のとおりです。
相続税の基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額の計算式は、次のとおりです。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
これに当てはめると、法定相続人の数ごとの相続税の基礎控除額は次のようになります。
- 1人:3,600万円
- 2人:4,200万円
- 3人:4,800万円
- 4人:5,400万円
- 5人:6,000万円
- 6人:6,600万円
例のケースでは法定相続人は3人ですので、相続税の基礎控除額は4,800万円です。
相続税の基礎控除額に用いる法定相続人の数の注意点
相続税の基礎控除額に用いる法定相続人の数を考える際には、次の3点に注意しましょう。
- 相続で財産をもらわなかった相続人がいる場合や遺言で相続人以外の人が財産を受け取った場合であっても、法定相続人の数は変わらない
- 相続放棄をした人がいても、法定相続人の数は変わらない
- 養子には次の算入制限がある
- 実子がいない場合:2人まで
- 実子がいる場合:1人まで
課税遺産総額の計算
相続税の基礎控除額を計算ができたら、課税価格の合計額から基礎控除額を控除します。
例の場合には、次のとおりです。
- 課税遺産総額=1億8,800万円−4,800万円=1億4,000万円
法定相続人が法定相続分で取得したと仮定する
課税遺産総額が計算できたら、この課税遺産総額を法定相続人が法定相続分で取得したと仮定します。
この段階では、実際に誰がいくらの財産を取得したのかは、一切考慮しません。
例のケースでは、次のようになります。
- 配偶者:1億4,000万円×2分の1=7,000万円
- 長男:1億4,000万円×4分の1=3,500万円
- 長女:1億4,000万円×4分の1=3,500万円
相続税の総額を計算する
次に、1つ前で計算した法定相続分に応じた相続分を速算表に当てはめて、相続税の総額の基となる税額を計算しましょう。
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例の場合には、次のとおりです。
- 配偶者:7,000万円×30%−700万円=1,400万円
- 長男:3,500万円×20%−200万円=500万円
- 長女:3,500万円×20%−200万円=500万円
これが計算できたら、それぞれの相続税の総額の基となる税額を合計します。
例の場合には、次のとおりです。
- 1,400万円+500万円+500万円=2,400万円
これが、相続税の総額となります。
各人ごとの相続税額を計算する
相続税の総額を、実際に相続や遺贈などで財産を受け取った人が受け取った割合で按分します。
例の場合に、配偶者と長男がそれぞれ2分の1ずつの割合で財産を相続し長女は一切相続しなかったと仮定すると、それぞれの相続税額は次のようになります。
- 配偶者:2,400万円×2分の1=1,400万円
- 長男:2,400万円×2分の1=1,400万円
- 長女:2,400万円×0=0円
各人の納付税額を計算する
最後に、税額の特例などを適用して各人の納付税額を計算します。
相続税の税額に影響を与える主な税額控除や税額加算には次のものがあります。
- 相続税額の2割加算:相続等で財産を取得した人が、被相続人の配偶者、子、親、代襲相続人である孫以外の人であった場合に、相続税額の2割に相当する金額が加算されます
- 配偶者の税額軽減:配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円か配偶者の法定相続分のどちらか多い金額までは相続税はかかりません
- 未成年者控除:相続人が未成年者の場合に相続税の額から一定の金額を差し引けます
- 障害者控除:相続人が85歳未満の障害者の場合に相続税の額から一定の金額を差し引けます
例の場合には配偶者の税額軽減のみが適用できるとすれば、それぞれの納付税額は次のようになります。
- 配偶者:1,400万円−1,400万円(※)=0円
- 長男:1,400万円
- 長女:0円
※配偶者の相続した財産が1億6,000万円以下であるため、全額が控除される
相続税の申告が必要かどうかはどう判断する?

相続税がかからない場合で一定の場合には、相続税の申告さえもする必要がありません。
ここでは、相続税の申告が必要かどうかを判断する方法を解説します。
基礎控除額と課税遺産総額を比べる
相続税の申告要否の判断には、上の計算過程のうち次の2つを比較します。
- 課税価格の合計額
- 相続税の基礎控除額
このうち、課税価格の合計額が相続税の基礎控除額であれば相続税がかからないことは、先ほどお伝えしたとおりです。
ただし、申告が必要かどうかを判断する際には、次の点に注意してください。
特例は適用せずに判断する
相続税申告の要否は、相続税の申告が適用の要件となっている特例をいったん加味せずに判断します。
申告が要件となっている特例として代表的なものは、小規模宅地等の特例です。
小規模宅地等の特例とは、要件と満たすことで土地を最大8割減で評価することができる制度で、実際に相続税の計算をする際は、課税価格の合計額を計算する段階で加味します。
しかし、申告の要否を判断するために課税価格の合計額と相続税の基礎控除額を比較する際には、小規模宅地等の適用はないものとして計算をして比較してください。
また、配偶者の税額軽減特例も申告が要件となっています。
そのため、この特例を使った結果全員の納付税額が0となった場合であっても、申告自体はする必要があることには注意しましょう。
まとめ
相続税の計算には段階が多く、それぞれで要件の異なる特例も数多く存在するため、すべてを理解することは容易ではありません。
しかし、基本的な事項を押さえておくことで、申告が不要かどうかや、相続税の大まかな判断は自分で行うことができるでしょう。
生前からおおよその相続税額を把握しておくと早めからの対策を検討することもできますので、ご自身やご家族に相続税がかかりそうかどうか、一度試算をしておくことをおすすめします。