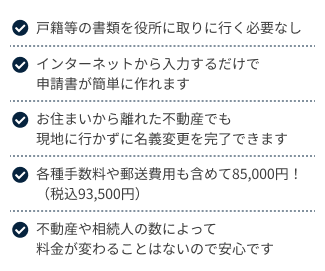家族が亡くなって相続が起きたとき、遺産を誰が相続するのかは法律で決まっています。
親族であれば誰でも遺産の相続権があるわけではありません。
財産を残す人にとっても受け継ぐ人にとっても、相続の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。
そこで、この記事では相続権を持つ人が誰なのかや相続権の割合、遺言書と相続権の関係や相続権を持つ人の確認方法を紹介します。
遺産の相続権を持つ人の範囲はどこまで?

相続が起きたとき、遺産を相続する人として法律で定められている人が「法定相続人」です。
法定相続人になるのは「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」ですが、配偶者とそれ以外の人では相続権に関する法律の規定が異なります。
配偶者は常に相続権を持つ
家族が亡くなって相続が起きたときに配偶者が存命であれば、その配偶者は法定相続人として遺産を相続できます。
配偶者は常に相続権を持つので、「子」「親」「兄弟姉妹」といった他の相続人の有無は関係ありません。
なお、相続における配偶者とは婚姻関係にある配偶者を指すので、内縁の妻や夫は含まれません。
子・親・兄弟姉妹の間では相続権の順位が決まっている
「子」「親」「兄弟姉妹」も相続人になれますが、相続人になる順位が決まっています。
上位の順位の人がいない場合には相続権が次順位の人に移る仕組みです。
逆に言えば、先順位の人がいると次順位以降の人には相続権がなく遺産を相続できません。
- 第一順位:子などの直系卑属
- 第二順位:親などの直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹
まず、第一順位として相続権を持つのは子で、子が既に亡くなっている場合でもその子(つまり孫)がいれば第一順位として相続権を持ちます。
そして、第一順位の人がいない場合に第二順位として相続権を持つのが親です。
親がすでに亡くなっている場合でも、その親(つまり祖父母)がいれば第二順位として相続権を持ちます。
さらに、第一順位、第二順位の人がともにいない場合に第三順位として相続権を持つのが兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合でも、その子(つまり甥・姪)がいれば第三順位として相続権を持ちます。
相続人ごとの相続権の割合

配偶者や子・親・兄弟姉妹が相続人になった場合、遺産のうちどれくらいの割合を相続する権利があるのか、「相続権の割合」が法律でそれぞれ決まっています。
遺産を相続する相続人という点では同じでも、相続権の割合は誰が相続人になるかによって変わるので注意が必要です。
そして、相続権の割合に関しては「法定相続分」と「遺留分」の2つがあります。
ここでは、法定相続分・遺留分それぞれの意味と、誰が相続人になった場合にどれだけの法定相続分や遺留分があるのか、解説していきます。
法定相続分
法定相続分とは、遺産を分ける際の目安になる割合です。
遺言書が残されていない場合には法定相続分に従って遺産を分けることも多く、あくまで目安なので相続人同士で話し合って法定相続分以外の割合で遺産を分けることもできます。
逆に、相続人同士の話し合いがまとまらずに裁判を通して遺産の分け方を決める場合には、遺産分割割合を裁判所が決める際に使うことが多いのが法定相続分です。
法定相続分は誰が相続人になるのかによって異なり、具体的には次の割合になります。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者:全財産 |
| 配偶者と子 |
|
| 子のみ | 子:全財産 |
| 配偶者と親 |
|
| 親のみ | 親:全財産 |
| 配偶者と兄弟姉妹 |
|
| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:全財産 |
たとえば、相続人が配偶者と子2人の計3人のケースでは、配偶者の法定相続分が2分の1、子2人の法定相続分が2分の1なので、子1人あたりの法定相続分は2分の1を2人で割って4分の1になります。
遺留分
遺留分とは、遺産を最低限相続できる割合として法律で保障された権利です。
被相続人(財産を残す人)は遺言書を書くことで財産の渡し方を自分で決められますが、相続人の権利である遺留分は遺言書によっても侵害することができません。
そのため、仮に遺留分を下回る遺産しか渡さない内容の遺言書が見つかった場合には、遺留分が認められている相続人は侵害された権利を主張して取り戻すことが可能です。
遺留分は誰が相続人になるのかによって異なり、具体的には次の割合になります。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者:2分の1 |
| 配偶者と子 |
|
| 子のみ | 子:2分の1 |
| 配偶者と親 |
|
| 親のみ | 親:3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 |
|
| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:なし |
ただし、法定相続分と違って遺留分は「配偶者」「子」「親」のみに認められています。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
そのため、兄弟姉妹が相続人のケースでは、仮に遺言書の内容が兄弟姉妹に一切遺産を渡さない内容だったとしても、兄弟姉妹は何ら権利を主張できないことになります。
ケースごとの相続権の考え方

「配偶者は常に相続人になること」そして「子・親・兄弟姉妹の間では相続権の順番が決まっていること」、この2点が相続の基本です。
ただし、これとは別に相続には細かい規定があり、誰が相続権を持つのか間違えやすいケースがあります。
ここでは以下の場合について解説するので、それぞれのケースで相続権がどうなるのかを見ていきましょう。
ケース①:相続放棄をした人がいる場合
何らかの理由で遺産を相続したくない場合、相続人は相続放棄の手続きを裁判所ですれば遺産を相続せずに済みます。
相続放棄をした人は最初から相続人ではなかった扱いになるため、相続権はありません。
そして、相続放棄をした人がいるケースでは、相続権は次順位の人に移ることになります。
たとえば、相続が起きたときに配偶者・子1人・親1人がいて配偶者と子の2人が相続人になるケースでは、子が相続放棄をすると、相続権が親に移るので配偶者と親の2人が相続人になります。
なお、仮に子の子(つまり孫)がいる場合でも、子が相続放棄をした場合は孫には相続権は移りません。
子などの先の世代の人が相続権を失っていても、孫などの後の世代の人に相続権が移る代襲相続が起きるケースもありますが、相続放棄では代襲相続の規定は適用されないことになっています。
ケース②:行方不明者がいる場合
行方不明者であっても相続人であることに変わりはありません。
そのため、行方不明者でも相続権があります。
ただし、実際問題としては行方不明の人が財産の相続権を行使することはできません。
そのため、行方不明者がいるケースでは他の相続人が不在者財産管理人の選任申立てをしたり、失踪宣告の申立てをすることが一般的です。
行方不明になってから7年経過していない場合には「不在者財産管理人の選任申立て」を、7年以上経過している場合には「失踪宣告の申立て」を行います。
ただし、震災などによる行方不明者の場合は、行方不明になってから1年以上経過していれば失踪宣告の申立てが可能です。
なお、失踪宣告の申立てをして裁判所に認められると、行方不明者は法律上死亡したものと見なされるため行方不明者の相続権はなくなります。
ケース③:養子がいる場合
養子にも遺産の相続権があるので、養親が亡くなったときには遺産を相続できます。
実子なのか養子なのかで違いはなく、相続分についても差はありません。
ただし、普通養子縁組と特別養子縁組では、養子が持つ相続権に次のような違いがあります。
- 普通養子縁組:養親が亡くなった場合でも実親が亡くなった場合でも養子は遺産の相続権を持つ
- 特別養子縁組:養子が相続権を持つのは養親が亡くなった場合だけで、実親が亡くなった場合は相続権を持たない
そのため、実親が亡くなって相続が起きても養子には相続権はありません。
ケース④:内縁の妻や夫がいる場合
配偶者は常に相続権を持ちますが、相続における配偶者とは婚姻関係にある者を指します。
そのため、内縁の妻や夫には相続権はありません。
自分の死んだ後に内縁の妻や夫に財産を渡したい場合には、生前に遺言書を作成して財産を渡す相手として指定しておく必要があります。
ケース⑤:前妻や前夫がいる場合
相続権は婚姻関係にある配偶者に認められるため、すでに離婚済で婚姻関係にない前妻や前夫には相続権はありません。
逆に、婚姻関係にあれば相続権は認められるため、たとえば別居状態だったり離婚協議中でまだ離婚が成立していないときに相続が起きれば相続権が認められます。
つまり、別居中や離婚協議中で実態として婚姻関係がどんなに破綻していても関係ありません。
あくまで、法的な婚姻関係の有無で相続権が判断されることになります。
ケース⑥:再婚相手の連れ子がいる場合
相続人になる子は、血縁関係がある直系卑属です。
再婚相手の連れ子とは血縁関係がないため、相続権はありません。
再婚相手の連れ子に財産を渡したい場合には、養子縁組をしたり遺言書で財産を渡す相手として指定するなど、何らかの対策を講じる必要があります。
ケース⑦:胎児がいる場合
法律で「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と規定されているので、胎児にも相続権が認められます。
ただし、無事に生まれた場合に限られるため、流産や死産だった場合には胎児に相続権はありません。
そのため、胎児が無事に生まれてくるかどうかによって相続人の関係が変わることになります。
相続が起きた時点で胎児がいるケースでは、胎児が生まれるのを待ってから遺産分割協議などを行うことが一般的です。
ケース⑧:未成年者がいる場合
未成年者であっても相続権があるため、遺産を相続できます。
ただし、未成年者の場合、遺産分割協議に参加するなどの法律行為を自分ではできません。
そのため、親などの親権者が代理人となって未成年者の代わりに相続関係の手続きを行います。
しかし、未成年の子だけでなく親も相続人の場合には、親と子の間に利害関係が生じて利益相反となってしまい、親は子の代理人になれません。
このような場合には「特別代理人の選任申立て」を裁判所に行い、特別代理人に就任した弁護士などが未成年者の代わりに相続手続きを進めます。
ケース⑨:法定相続人で既に亡くなっている人がいる場合
相続が起きたときに本来の法定相続人ですでに亡くなっている人がいる場合には、「代襲相続」が起きる可能性があります。
代襲相続とは、本来の相続人が亡くなっている場合などに、その人に子がいれば子に相続権が移ることです。
たとえば、親が亡くなった時点で相続人である子が既に亡くなっている場合でも、その子(つまり孫)がいれば孫に相続権が移ります。
なお、子に関しては孫や曽孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)など何世代先まででも代襲相続が起きますが、本来の相続人が兄弟姉妹のケースでは代襲相続は一世代限りです。
兄弟姉妹の子(つまり甥・姪)に代襲相続によって相続権が移ることはありますが、甥・姪が亡くなっていてさらにその子にまで相続権が移ることはありません。
ケース⑩:相続欠格・相続人廃除に該当する人がいる場合
「相続欠格」とは、相続人としての資格に欠ける人のことで、遺言書を偽造したり被相続人を殺害するなどした人が該当します。
相続欠格に該当する人に遺産の相続権はありません。
また、「相続人廃除」とは、虐待や重大な侮辱をした相続人の相続権を剥奪することです。
虐待や重大な侮辱を受けた人が裁判所に申立てをするか、あるいは遺言書に廃除する旨を記載することで、相続人の相続権を剥奪できます。
そのため、相続人廃除に該当する人には遺産の相続権はありません。
なお、相続欠格や相続人廃除に該当する人がいる場合には、その人に子がいれば子に相続権が移る代襲相続の規定が適用され、いなければ次順位の人に相続権が移ります。
ケース⑪:相続権を持つ人がいない場合
相続権を持つ人がいればその人が遺産を相続しますが、ある人が亡くなったときに相続権を持つ人が誰もいないケースも当然あります。
このような場合には「相続財産管理人」が選任され、相続人や債権者の捜索が行われた後に誰も現れなければ遺産は国に帰属します。
相続権と遺言書の関係
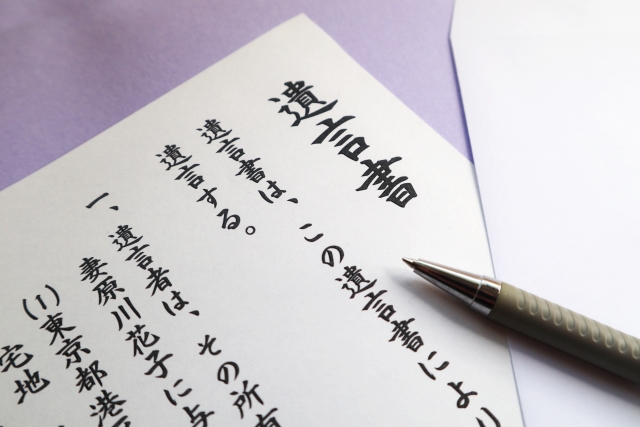
財産を残す人は自分の財産を誰にどれだけ渡すのかを決める権利があり、生前に遺言書を書いておけば財産の分け方を決められます。
しかし、財産をもらう人にも相続権という権利があるので、財産をもらう側の権利を無視してまで何でも遺言書で指定できるわけではありません。
遺言書を書いて財産を相続させる人の権利と財産を相続する人の権利、この2つの権利には法律で優先順位が決まっています。
法定相続分よりも遺言書が優先する
相続人が相続する遺産の割合の目安である法定相続分よりも、遺言書で書かれた遺産の分け方が優先します。
そのため、法定相続分を下回る割合しか財産を渡さない内容の遺言書でも有効です。
遺留分は遺言書でも侵害できない
遺留分は一定の相続人に最低限保証された権利であり、遺言書でも遺留分は侵害できません。
仮に遺留分を下回る割合の遺産しか渡さない旨の遺言を書いてしまうと、相続人は侵害された遺留分を権利として主張できます。
結果的に自分が書いた遺言の内容とは違う形で遺産が相続人の間で分割されてしまう可能性もあるので、遺言書を作る際には遺留分に十分に注意しなければいけません。
相続権がない人に財産を渡したい場合は遺言書を活用する
相続人の遺留分を侵害しない内容であれば、遺言書を書く人が財産の渡し方を自由に決められます。
財産を渡す相手として指定できるのは相続人だけではないので、相続権を持たない人であっても構いません。
たとえば、家族以外の人で自分の介護をしてくれた人に財産を渡したいようなケースでは、遺言書を活用すれば財産を渡したい人に渡せて自分なりの想いを実現できます。
相続権がある人の確認方法

相続が起きたときには、最初に相続権を持つ人が誰なのかを調査する必要があります。
相続人の範囲を正しく把握していないと、たとえば遺産分割協議が無効になる可能性があるので注意が必要です。
ここでは、相続権がある人が誰なのかを確認する方法について紹介します。
戸籍収集による相続人調査
誰が相続人なのかは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍を集めることで確認できます。
まずは死亡当時の戸籍を市区町村役場で取り寄せて、そこから過去の戸籍に遡っていく形ですべての戸籍を揃えましょう。
ただ、戸籍収集は手間も時間もかかり、慣れていない人が自分でやろうとしても大変です。
専門家に依頼すればスムーズに終わるので、相続が起きた際には戸籍収集(相続人調査)を弁護士などに依頼することも検討してみてください。
遺言書の有無の確認
遺産の相続権を持つ人が誰なのかを確認する上では、遺言書の有無の確認も必要です。
たとえば、隠し子がいて認知する旨が遺言書に記載されていた場合、認知された子は相続人として相続権を有することになります。
また、相続人の廃除を行う旨が遺言書に記載されていた場合も、相続人の関係が変わります。
そのため、相続が起きたときには、自宅や法務局に自筆証書遺言書が保管されていないかどうか、公証役場に「公正証書遺言書」が保管されていないかどうか、すぐに確認するようにしてください。
まとめ
配偶者は常に相続権を持ち、「子」「親」「兄弟姉妹」の間では相続人になれる順番が決まっています。
相続が起きたときに相続人になれる人は法律で決まっているので、親族であれば誰でも相続人になれるわけではありません。
また、相続放棄をした人がいる場合や代襲相続が起きる場合など、遺産の相続権を持つのが誰なのかを間違えやすいケースには特に注意が必要です。
相続に関するさまざまな手続きをミスなく終えるためにも、相続が起きたときには弁護士や司法書士、税理士といった相続の専門家に相談・依頼するようにしてください。