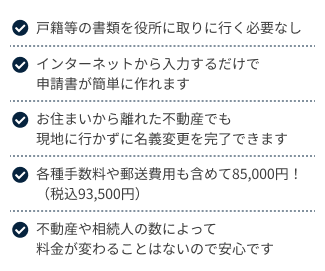自分が死んで相続が起きたとき、人によっては孫に遺産を相続させたいと考える場合があります。
例えば、孫世代が教育費や子育て費用などで何かとお金がかかっていて、子ではなく孫に自分の財産を渡したほうが遺産を活用してもらえそうなケースです。
しかし、相続が起きたときに遺産を誰が相続するのか、相続人になる人は法律で決まっています。
孫が相続人になる場合もありますが、相続人にならず遺産を相続できない場合も少なくありません。
孫に遺産を相続させるためには、生前に何らかの対策が必要になることが多く、遺産相続のルールや生前の相続対策について理解しておくことが大切です。
そこで今回は、遺産を相続できる人の範囲や孫に遺産を相続させる方法、孫に遺産を渡すときの注意点などについて解説します。
目次
遺産を相続できる人の範囲とは?

相続が起きたとき、亡くなった人(=被相続人)の財産を誰が相続するのか、遺産を相続できる人の範囲は法律で決まっています。
つまり、親族だからという理由だけで、誰でも遺産の相続権を主張できるわけではありません。
具体的には、遺産の相続権に関して次のようなルールがあります。
- 常に相続人になる人:配偶者
- 第一順位:子
- 第二順位:親
- 第三順位:兄弟姉妹
配偶者は常に相続人になる
相続が起きたときに配偶者が生きていれば、その配偶者は相続人になるため遺産を相続できます。
配偶者は亡くなった人の資産形成に大きく貢献した存在であり、遺産の相続権が当然認められるべきだからです。
次に解説する「親」や「兄弟姉妹」のように、「順位が上の人がいると遺産を相続できない」といったことはありません。
内縁関係の場合は相続権は認められませんが、婚姻関係にある配偶者であれば遺産を相続できます。
子・親・兄弟姉妹では順位が決まっている
子・親・兄弟姉妹の間では、相続人になる順位が決まっており、子が第一順位、親が第二順位、兄弟姉妹が第三順位です。
順位が上の人が遺産を相続する相続人になり、順位が上の人がいない場合は次の順位の人が相続人になります。
例えば、ある人が亡くなったときに子と親がいる場合、相続人になる順位が高い子が相続人になり、順位が低い親は相続人にはならないため遺産を相続できません。
孫には基本的に遺産を相続する権利はない
のちほど解説する代襲相続によって孫が遺産を相続するケースはありますが、相続人になる人は原則として配偶者・子・親・兄弟姉妹です。
代襲相続が起きて孫が相続人になるようなケースは多いとはいえず、孫には基本的に遺産を相続する権利はありません。
そのため、もしも孫に遺産を相続させたいのであれば、何らかの対策をする必要があります。
孫に遺産を相続させる方法と相続分

基本的に、孫には遺産を相続する権利がありませんが、生前に対策をすれば孫に遺産を渡すことができます。
孫に遺産を渡す主な方法は次の2つです。
- 遺言書を書いておく
- 養子縁組をして相続人にする
遺言書を書いておく
生前に遺言書を書いておけば、相続人ではない人にも遺産を渡せます。
そのため、仮に現時点で相続が起きた場合に孫が法律上の相続人にならないとしても、遺言書を作成して財産を渡す相手として孫を指定しておけば、孫に遺産を渡すことが可能です。
なお、遺言書の作成方法については、次の記事で解説しています。
そして、誰にどれだけの財産を渡すのかは、遺言書を書く人(=財産を遺す人)が自由に決められます。
ただし、遺言書の内容を考える際、一定の相続人に認められた権利である「遺留分」との関係には注意しましょう。
相続人の遺留分を侵害する内容で遺言を遺すと、実際に相続が起きたときに遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求を行い、遺言の内容どおりに孫に遺産が渡らない可能性があります。
養子縁組をして相続人にする
先ほど、相続人になれる人は法律で順位が決まっており、子は第一順位であることを紹介しました。
ここで、この子に含まれる人の範囲ですが、実子だけでなく養子も含まれます。
遺産の相続に関して、養子には実子と同じ権利が認められており、実子と養子で相続権に違いはありません。
たとえば、配偶者と子が相続人の場合、子の法定相続分は2分の1であり、その子が実子の場合でも養子の場合でも法定相続分は2分の1で同じです。
そのため、養子縁組を行って孫を養子にすれば、実子と同じく相続人になるため、遺産を渡すことができます。
なお、養子縁組をすると、孫とそれ以外の相続人の間でトラブルになる場合があるため、養子縁組を活用する際には注意が必要です。
相続対策としての養子縁組については、次の記事でも解説しているので参考にしてください。
代襲相続で孫が相続人になるケース

代襲相続とは、本来の相続人に代わってその相続人の子が相続人になる相続のことです。
次のようなケースでは代襲相続が起こり、本来の相続人に代わってその相続人の子が相続人として遺産を相続します。
- 本来の相続人が既に死亡している
- 本来の相続人が相続欠格により相続権を失っている
- 本来の相続人が相続人廃除により相続権を失っている
たとえば、本来の相続人である子が相続開始時点で既に亡くなっていて、子に子(つまり孫)がいる場合は、代襲相続の規定に基づき孫が相続人になります。
なお、相続欠格と相続人廃除の意味は、それぞれ次のとおりです。
- 相続欠格:被相続人を故意に死亡させるなどして、相続人としての資格に欠けること
- 相続人廃除:相続人から虐待や重大な侮辱を受けた場合などに、その相続人の相続権を剥奪すること
いずれにしても、代襲相続が起きる理由である(本来の相続人の)死亡・相続欠格・相続人廃除は、基本的に意図してその状況を作り出せるものではありません。
孫に遺産を相続させるために意図的に代襲相続を起こせるものではないため、孫に遺産を相続させたい場合には、さきほど解説したように、遺言書や養子縁組を活用することになります。
生前贈与で孫に財産を渡す方法

孫に財産を渡す方法としては、遺産を相続させる方法のほかに生前に贈与する方法もあります。
生前贈与であれば相続まで待つ必要がなくなり、孫が早くから財産を活用できる点がメリットです。
ただし、財産を生前に贈与する場合には贈与税がかかることがあります。
贈与の方法を工夫すると税額を減らせて節税できる場合があるので、納税後に孫の手元に残る財産を少しでも多くするためにも、生前贈与では贈与税を考慮に入れることが大切です。
ここでは、贈与税の節税方法として、次の3つの方法について紹介します。
- 孫が20歳になってから贈与する
- 暦年贈与を行う
- 贈与税の特例制度を活用する
孫が20歳になってから贈与する
贈与税の課税方式には暦年課税と相続時精算課税があり、一般的に適用されるのは暦年課税です。
- 贈与税の税額 = (1年間に贈与された財産の総額 - 基礎控除額110万円) × 税率 - 控除額
暦年課税では年間の贈与額が110万円を超えると贈与税がかかり、税率には一般税率と特例税率の2種類があります。
- 一般税率:特例税率が適用される人以外に適用される税率
- 特例税率:祖父母や父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫などへ贈与した場合に適用される税率
贈与する金額が410万円(基礎控除後の金額が300万円)を超える場合は、一般税率が適用されるケースよりも特例税率が適用されるケースの方が税額が安くなります。
たとえば、現金500万円を孫に贈与する場合の税額は、一般税率で53万円、特例税率で48万5000円です。
つまり、孫が現金500万円を贈与されて、贈与税を納税した後に手元に残る金額は、一般税率では447万円、特例税率では451万5000円になり、特例税率のほうが4万5000円多く孫の手元に残ります。
そのため、例えば孫が19歳の場合には、すぐに贈与するのではなく、特例税率が適用されるようになる20歳になるまで待ってから贈与すると良いでしょう。
贈与する祖父母の立場からすれば贈与額は変わりませんが、特例税率の適用を受けられる年齢に孫がなるまで待つことで、納税後に孫の手元に残り、活用できる資産の額が増えることになります。
暦年贈与を行う
贈与税(暦年課税)は、1年間の贈与額から基礎控除額110万円を引いて税率をかけて税額を求めるため、贈与額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
そのため、孫に毎年贈与する金額を110万円以下に抑えて複数年に渡って贈与を続ければ、贈与税をかけずに財産を贈与できます。
これは、暦年課税の仕組みを利用して贈与税の節税を行う「暦年贈与」と呼ばれる贈与の方法です。
1年間に贈与する金額は110万円以下とそれほど大きくはありませんが、贈与を何年も行うことで累計で大きな額を贈与できて節税効果も結果的に大きくなります。
なお、実際に暦年贈与を行う場合には、次の点には注意が必要です。
- 贈与をするときには贈与契約書を作成する
- 贈与をする日付や金額は毎年変える
まず、贈与契約書を残していないと、相続が起きたときに孫が困る場合があります。
税務署から確認されたときに、贈与契約書がなく生前贈与の証拠を示せないと、生前贈与自体が否認されて相続財産の一つと見なされて、相続税が課されてしまう場合があるからです。
生前贈与による節税対策を行った意味がなくなってしまうので、贈与の度に贈与契約書を作って保管しておくようにしてください。
また、暦年贈与をするときに毎年同じ日に同じ金額を贈与していると、「最初からまとまった金額を贈与する意思があったのではないか」と税務署に疑われる場合があります。
最初からまとまった額の贈与をするつもりだったと見なされると、まとまった額に対して贈与税が課されることがあるので注意が必要です。
税務署から指摘を受けることがないように、暦年贈与では年によって贈与額や贈与する日付を変えたほうが良いでしょう。
贈与税の特例制度を活用する
贈与税には、一定の要件を満たす場合に使えるさまざまな特例制度が用意されています。
- 住宅取得等資金の贈与の非課税制度
- 教育資金の一括贈与の非課税制度
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度
贈与する資金の使途が決まっており、孫が住宅取得費用や教育費用、結婚・子育て費用として使うことがわかっている場合には、非課税制度を利用すると良いでしょう。
それぞれの制度を利用できる人の要件は細かく決まっているので事前の確認が必要ですが、制度によってはかなり大きな金額の贈与をしても贈与税がかからずに済みます。
祖父母の遺産を孫が相続するメリット・デメリット

遺言書の作成など生前に対策を取っておけば孫に遺産を渡せますが、孫が祖父母の遺産を相続することには、メリットとデメリットの両方がある点を踏まえておく必要があります。
メリットのほうが大きい場合は問題ありませんが、デメリットが大きい場合には、よく考えずに孫に遺産を相続させると、むしろ問題が起きることがあるため注意してください。
メリット
養子縁組を活用したり遺言書を遺したりして孫が遺産を受け取れるようにすれば、財産を渡す側の祖父母としては、渡したい人(孫)に自分の財産を渡せることがメリットです。
また、養子縁組をすることで相続人の数が増えると、相続税の基礎控除額が増えて節税になる場合があります。
さらに、本来であれば親→子→孫と2回の相続が発生して孫世代に財産が渡るところ、祖父母から孫世代に遺産を渡せば、相続税の課税回数が減るため節税になる場合がある点もメリットの一つです。
デメリット
孫を養子にすれば相続人として遺産を相続できますが、相続人の数が増えることで権利関係が複雑になり、遺産分割協議で合意するのが難しくなったり相続を巡って揉めたりする可能性があります。
また、孫を養子にすることで他の相続人の遺産の取り分が減るようなケースでは、相続分が減った相続人が不満を抱き、親族同士でトラブルが起きることもあるので注意が必要です。
孫に財産を渡すためとはいえ、孫をトラブルに巻き込んだり精神的苦痛を与えることになったりしては問題なので、トラブルにならないか事前にしっかりと検討したほうが良いでしょう。
また、孫を養子にした場合は、(代襲相続のケースなどを除いて)孫にかかる相続税が2割加算される点もデメリットです。
相続税の2割加算とは、配偶者・子・親以外の人が遺産を取得する場合に、その人に課される相続税が2割増しになるという規定です。
養子は基本的に2割加算の対象外になりますが、孫養子の場合だけは例外的に相続税が2割加算されることになっています。
孫に遺産を渡すときの注意点

さきほどデメリットで紹介した点は、孫に遺産を渡すときに特に注意すべき点です。
以下の2点について、しっかりと検討してから孫に遺産を渡すかどうかを決めることが大切です。
- 他の相続人とトラブルになる場合がある
- 相続税が増える場合がある
他の相続人とトラブルになる場合がある
例えば、亡くなった方(被相続人)の子である兄弟2人が相続人になるケースを考えてみましょう。
この場合には、兄と弟の法定相続分は2分の1ずつであり、それぞれが遺産の半分を相続することになります。
しかし、仮に被相続人が生前に兄の子(故人から見れば孫)を養子にしていた場合、兄・弟・兄の子の3人が相続人になるので、相続分はそれぞれ3分の1です。
弟は自分の取り分が2分の1から3分の1に減ってしまうので、例えば兄弟の仲が悪い場合には、兄の子が養子になること自体に不満を抱くかもしれません。
その結果として、親族間で相続を巡ってトラブルになる可能性があります。
相続税が増える場合がある
孫を養子にすれば、相続人の数が増えることで基礎控除額が増えて節税になる場合がある一方、税額が2割加算されるため逆に税負担が大きくなる場合があります。
どちらの効果が大きいかはケースごとに異なりますが、2割加算の規定による増税効果のほうが大きい場合には、養子縁組を行った結果として相続税が増えてしまう点に注意が必要です。
もちろん、養子縁組をして孫を養子にしたほうが相続税が減る場合もあるので、相続対策として孫を養子にする場合には、事前に相続税のシミュレーションをしたほうが良いでしょう。
まとめ
孫が代襲相続人になって遺産を相続できる場合もありますが、多くのケースでは孫は相続人になりません。
そのため、孫に遺産を渡したい場合には、養子縁組や遺言書など生前に何らかの対策をしておく必要があります。
また、孫に財産を渡したいのであれば生前贈与を行うのも一つの方法です。
孫に財産を渡す方法として何が一番よいのかしっかりと検討を行って、最適な方法で財産を渡すようにしましょう。